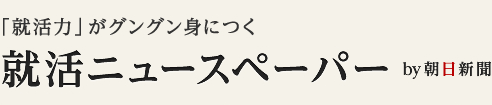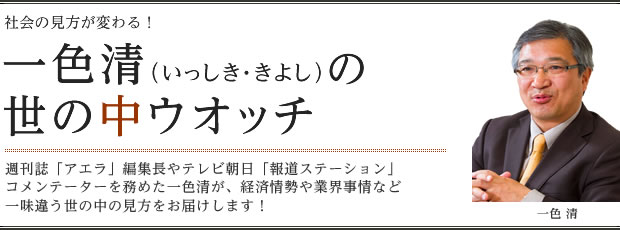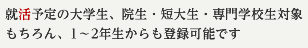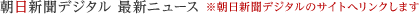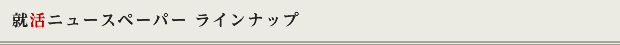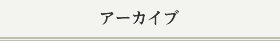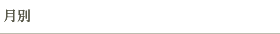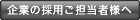小説仕立ての経済人の一代記で、主人公のモデルは、出光興産の創業者である出光佐三氏です。九州で興した石油販売業を一代で日本有数の石油元売り会社に育てた人です。敗戦で仕事がなくなっても、一人の従業員も解雇しない。英国に海上封鎖されたイランに自社のタンカー「日章丸」を命がけで向かわせ、イラン原油の日本初輸入を実現させる。談合体質の業界や役所を向こうに回し、一人信じるところを貫き通す。
小説ですから細部は想像で描いていたり、劇的な場面をクローズアップしていたりするのは否めないでしょうが、基本的な事実関係は確かなものです。もう一度人生をやり直せるならこんな人のもとで働きたいと多くの読者は思うのではないでしょうか。
私は今から20数年前、朝日新聞の経済部記者として短い間でしたが、石油業界を担当したことがあります。佐三氏はすでに亡くなっていて、弟の計介氏が社長を務めていました。今から思うと勉強不足を恥じるばかりですが、小説で初めて知ったことがたくさんありました。
当時、同業他社の広報マンからは、「出光の悪口」をよく聞かされました。「労働組合もないんですよ」「(お堀端の本社ビルから)社員は皇居遥拝させられるんですよ」「借金が多すぎて銀行から人が来ているそうですよ」などなど。出光だけ悪口を言われるわけは、出光が同業他社と足並みをそろえないからだとは分かっていましたが、しょっちゅう言われるとやはりイメージは悪くなったことを思い出します。「前近代的経営の会社」とでもいいましょうか。出光佐三氏がこれまで本などにあまり書かれてこなかったのは、こうした「評判」もあったのではないかと思います。
会社の評判って何でしょう。すさまじいサービス残業とかセクハラ、パワハラの横行といった明らかな「ブラック企業」は別として、評判の善しあしは、どちらから見ているかによるように思います。「労働組合がない」はふつうよくない要素と考えられますが、「人を大事にする家族主義」という見方ができる場合もあるでしょう。「若くて活気のある会社」という評判は、「競争が激しく仕事がきつい」と裏腹である場合が多いと思います。「なかなか仕事を任せてもらえない」という評判は、「時間をかけて人材育成をする」ということと同じです。
結局、会社選びは評判のよしあしではなく、自分に向いているかどうかの基準で考えた方がいいと思います。例えば、カリスマ社長とウエットな関係で結びつく会社が向くのか、仕事は仕事と割り切るドライな関係の会社が向くのかとか。うわべの評判があてにならないのは、経済記者だった私が証言します。
それにしても、思い出すと、出光の広報マンは他社の悪口を言わなかったなあ。あれも佐三氏の教育の賜物だったのでしょうか。