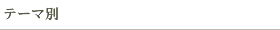■開発のきっかけ
──御社がアンモニア燃料船開発にターゲットを定めたきっかけは何でしたか。
高野 「2050年までにゼロエミッション」という目標にコミットしようという意識が大きいです。そこから逆算してどうしたらGHGをゼロにできるのかと考えたとき、従来の燃料と比較し、GHGの排出を大幅に削減できる代替燃料を導入することが不可欠であり、その中でもアンモニアに注目しました。先ほど申し上げたように物質として取り扱いやすいということと、燃やしてもCO₂を排出しない物質というところが大きいですね。
雨宮 弊社は代替燃料として水素やメタノールなどの可能性についても模索していますが、例えば外航船はかなりの距離を走らなくてはいけません。水素を燃料にすると、液体密度が低く非常に大きな燃料タンクを搭載する必要があり、その観点においてはアンモニアのほうが現実的か、と考えています。また、アンモニアは国内の電力会社をはじめ発電用途として、需要が増える見込みです。水素を取り出せる水素キャリアとしての役割もあり、アンモニアの需要が急拡大する見込みであることもアンモニアにより注目している理由の1つです。
■世界初のアンモニア燃料商用船
──もともと御社に、アンモニアを燃料にするというアイデアや技術はあったのですか。
雨宮 我々は海運会社ですので、アンモニアをエンジンの燃料とする技術は持ち合わせていませんでした。今、我々が取り組んでいるアンモニア燃料船開発はNEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)のGI(グリーンイノベーション)基金から助成を受け、アンモニアエンジンを開発するジャパンエンジンコーポレーション、IHI原動機、本船の設計を担当する日本シップヤード、船舶の検査・認証機関である日本海事協会とコンソーシアムを組んで展開しています。
──開発はいつスタートしたのですか。
雨宮 コンソーシアムを組み、応募してGI基金の採択を受けるという流れで、採択を受けたのは2021年です。
弊社は2024年、世界初のアンモニア燃料商用船である「魁」というタグボートを竣工させました。取り組みのスタートは他社と比べても早く、その分、知見もあると自負しています。
──なぜ、世界で初めて「魁」を竣工できたのですか。
高野 これは弊社一社だと成し遂げられなかったことだと思います。メーカー、エンジンメーカー、造船所とコンソーシアムを組んだからできたことです。
弊社には「これまでを極め、これからを開く」というフレーズがあります。伝統的な会社でありつつ、新たに発生するであろうビジネスを、どんどんパイオニアとして切り開いていくという力強いメッセージが、社員全員に広がっていると思います。
 SDGs(持続可能な開発目標)関連の業務に携わっている若手・中堅社員に直撃インタビューする「SDGsに貢献する仕事」。第26回は海運業界最大手の日本郵船が登場します。創業140年を迎える伝統ある企業ですが、「これまでを極め、これからを拓く」というキャッチフレーズのもと、業界の先端を行くチャレンジを続けています。なかでも、温室効果ガスであるCO₂を排出しない「アンモニア燃料船」開発に向けた取り組みは世界的な注目を集めています。これまでにない海運の姿をつくりだそうとする、アンモニア燃料船プロジェクトの社員2人にじっくり話を聞きました。(編集長・福井洋平)
SDGs(持続可能な開発目標)関連の業務に携わっている若手・中堅社員に直撃インタビューする「SDGsに貢献する仕事」。第26回は海運業界最大手の日本郵船が登場します。創業140年を迎える伝統ある企業ですが、「これまでを極め、これからを拓く」というキャッチフレーズのもと、業界の先端を行くチャレンジを続けています。なかでも、温室効果ガスであるCO₂を排出しない「アンモニア燃料船」開発に向けた取り組みは世界的な注目を集めています。これまでにない海運の姿をつくりだそうとする、アンモニア燃料船プロジェクトの社員2人にじっくり話を聞きました。(編集長・福井洋平)


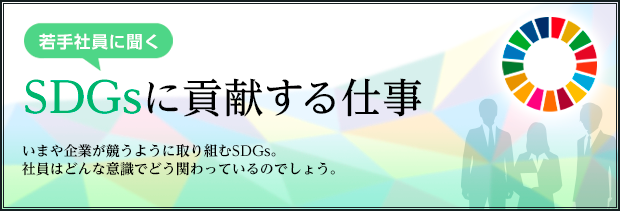
 ■アンモニア燃料船開発チームのお仕事
■アンモニア燃料船開発チームのお仕事 ■開発のきっかけ
■開発のきっかけ ■AMFGC
■AMFGC (AFMGCのイメージ画像=日本郵船提供)
(AFMGCのイメージ画像=日本郵船提供) ■現状と今後の課題
■現状と今後の課題 ■アンモニア商用船「魁」
■アンモニア商用船「魁」 ■「魁」への反応
■「魁」への反応 ■今後の課題
■今後の課題