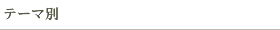■大阪大学での研究
──大阪大で共同研究にも取り組まれていましたが 、研究テーマは何でしたか。
ポリ乳酸はバイオマスプラスチックとして、成形加工がすごくしやすい優秀な素材ですが、海洋や土壌の環境下では分解しづらい素材です。コンポストと呼ばれる堆肥中で生分解性を評価すると、60度近くあり、微生物活性も活発なのできれいに生分解されます。しかし一般的な土壌や海洋に放出されたときには温度や微生物活性が低いので、分解にすごく時間がかかります。その海洋生分解性を向上させるのが研究テーマでした。まだ、実用化には至っていないです。
──海でも分解されやすくすることができるんですか?
ポリ乳酸とより分解しやすい素材を一緒に合成する「共重合」と呼ばれる方法で、海洋生分解性を上げられないか、3年近く研究しています。もともと分解しやすい材料を入れることで、そこを基点にしてポリ乳酸も微生物に食べられやすくなります。
──一般的なプラスチックは分解されづらいのですか。
一般的なプラスチックやポリエチレンは、基本的には微生物が食べてくれません。
──共同研究は会社側から提案されたのですか。
はい。我々のほうから大阪大学に持ちかけてスタートし、宇山浩先生と共同研究を行いました。最初は社命で任期付きの共同研究をスタートさせましたが、1年後に宇山先生から「面白い研究をしているから、博士課程に進んでみないか」と打診され、当時の上司に相談した際に、後押ししてくださり、博士課程にも進学させていただきました。
最終的に3年半、大学にいることになりました。
──論文も書かれて、博士論文も書かれてということですね。
共同研究を開始した当時は、ポリ乳酸の合成技術を確立できていませんでした。宇山先生がポリマーの専門家なので、その技術を学んできて、王子の江戸川分室のチームに還元するというところと、引き続き、海洋生分解性も改善できないかという2本立てで、新たに共同研究がスタートし、論文も執筆しました。
──合成も宇山先生の研究テーマなのですか。
宇山先生が重合方法をご存知でした。会社に化学合成の専門家がいなかったので、ポリ乳酸の重合度を上げるにはどうすればいいかを学びました。
──共同研究の間は、王子HDとはどういう関わり方をしていましたか。
ベンチプラントで開発したポリ乳酸のシート・フィルム化の業務などと並行しながらですが、共同研究内容については週に1回レポートを出したり、チーフと定期的なミーティングをしたり、センター長や本部長に半年から1年に1回研究成果の報告をしたりしていました。今年7月に王子HDに戻りました。
(後編は
こちらから)
(写真・大嶋千尋)
 SDGs(持続可能な開発目標)関連の業務に携わっている若手・中堅社員に直撃インタビューする「SDGsに貢献する仕事」。第28回は製紙業を中核とする王子ホールディングス(HD)が登場します。紙の原料となる木を育て、使い終わった紙を回収して再生する――業態そのものがSDGs、持続可能性というテーマと向き合ってきた王子HD。ペーパーレス時代となり製紙業界が逆風にさらされるなか、注目したのは自社が保有する日本一の森林資源。酵素や微生物などの力で木からプラスチックや燃料をつくる「バイオものづくり」にとりくみ、新たなアプローチで持続可能な社会をつくりだそうとしている研究員にじっくり話を聞きました。(編集長・福井洋平)
SDGs(持続可能な開発目標)関連の業務に携わっている若手・中堅社員に直撃インタビューする「SDGsに貢献する仕事」。第28回は製紙業を中核とする王子ホールディングス(HD)が登場します。紙の原料となる木を育て、使い終わった紙を回収して再生する――業態そのものがSDGs、持続可能性というテーマと向き合ってきた王子HD。ペーパーレス時代となり製紙業界が逆風にさらされるなか、注目したのは自社が保有する日本一の森林資源。酵素や微生物などの力で木からプラスチックや燃料をつくる「バイオものづくり」にとりくみ、新たなアプローチで持続可能な社会をつくりだそうとしている研究員にじっくり話を聞きました。(編集長・福井洋平)


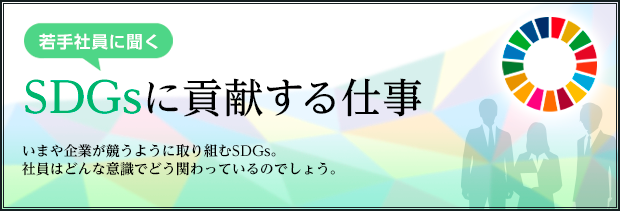
 ■王子ホールディングス(HD)のSDGsへの考え方
■王子ホールディングス(HD)のSDGsへの考え方 (糖液=左とバイオエタノール=右/王子HD提供)
(糖液=左とバイオエタノール=右/王子HD提供) ■バイオケミカル研究
■バイオケミカル研究 ■セルラーゼ
■セルラーゼ ■王子HDの技術力
■王子HDの技術力 (ペレット=左とフィルム=右/王子HD提供)
(ペレット=左とフィルム=右/王子HD提供) ■大阪大学での研究
■大阪大学での研究