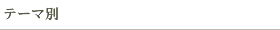(写真は空から見たゼロカーボンベースボールパーク=阪神電鉄提供)
■脱炭素地域
──なぜ、このようなコンセプトが生まれたのでしょうか。
尼崎市は昔に公害問題があったので「公害の町」という環境に対するマイナスイメージを払拭したいという思いがあり、市のイメージアップも含めて環境問題に取り組んできたという経緯があります。また、阪急阪神ホールディングスでは、グループ各社がいろいろな施設を運営する中で、さまざまな脱炭素の取り組みをしています。私はもともと阪神タイガース本拠地の甲子園球場を運営する部署にいましたが、甲子園球場も脱炭素をめざし、リニューアル時に太陽光パネルを設置したり、さきほども触れましたが雨水や井戸水を利用したり、ビールのプラスチックカップをリサイクルして、その素材を外野のフェンスのクッションに使用したりといった「甲子園エコチャレンジ」という取り組みを続けてきました。
――そういった歴史があって、この構想につながったのですね。
そうですね。2022年、環境省が実施する「脱炭素先行地域」の第1回公募に尼崎市と阪神電鉄が選ばれ、2050年にカーボンニュートラル(温室効果ガスの排出量と吸収量を等しくすること)を実現するために先行して脱炭素に取り組む地域として「ゼロカーボンベースボールパーク」の整備計画が動き出しました。国からも補助金など積極的な支援を受け、2030年までにCO₂の排出を実質ゼロにしようとしています。
─―球場名にもなっている日鉄鋼板さんとも、このタイミングで協業が決まったのですか。
脱炭素先行地域に採択され、野球施設としては全国で初めてZEB認証を取得することを目指して、整備計画地の隣にある日鉄鋼板さんの高断熱と耐火性能を高レベルで両立させた金属断熱サンドイッチパネルを使用することになりました。それにあたり、技術、素材の提供にくわえて球場のネーミングライツを採用いただき、タイガースとこの地域での活動を応援していただけることとなりました。
――現在(2025年9月時点)脱炭素先行地域は90提案が選定されていますが、ゼロカーボンベースボールパークの注目度はどうですか。
ここは脱炭素先行地域の中では最初に完成し、まさにファーストランナーとして走っている施設なので、環境省からも注目され、期待されていると感じます。プロ野球チームでは福岡ソフトバンクホークスさんも福岡市と一緒にみずほPayPayドームに太陽光パネルを入れるなど脱炭素先行地域としての取り組みをしていますし、スポーツ界での脱炭素に向けた機運が高まっていることを感じています。
 SDGs(持続可能な開発目標)関連の業務に携わっている若手・中堅社員に直撃インタビューする「SDGsに貢献する仕事」。第29回は、鉄道事業などを展開する阪急阪神ホールディングスのグループ企業である、プロ野球球団・株式会社阪神タイガースが登場します。2025年3月、阪神タイガース2軍の本拠地として開業した日鉄鋼板 SGLスタジアム 尼崎を中核とする「ゼロカーボンベースボールパーク」。名前のとおり、脱炭素推進を全面に押し出した施設です。プロスポーツが持つ発信力をSDGsへの取り組みにいかす先駆的な事例として、全国的にも注目を集めている同施設。地域自治体との連携や広報活動など、さまざまな施策を実現している担当者に話を聞きました。(編集長・福井洋平)
SDGs(持続可能な開発目標)関連の業務に携わっている若手・中堅社員に直撃インタビューする「SDGsに貢献する仕事」。第29回は、鉄道事業などを展開する阪急阪神ホールディングスのグループ企業である、プロ野球球団・株式会社阪神タイガースが登場します。2025年3月、阪神タイガース2軍の本拠地として開業した日鉄鋼板 SGLスタジアム 尼崎を中核とする「ゼロカーボンベースボールパーク」。名前のとおり、脱炭素推進を全面に押し出した施設です。プロスポーツが持つ発信力をSDGsへの取り組みにいかす先駆的な事例として、全国的にも注目を集めている同施設。地域自治体との連携や広報活動など、さまざまな施策を実現している担当者に話を聞きました。(編集長・福井洋平)


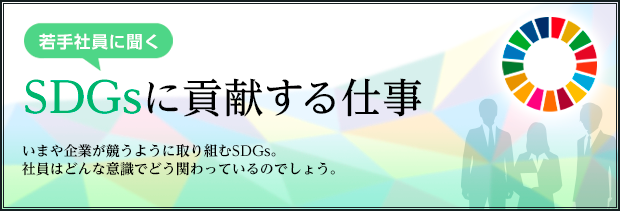
 ■ゼロカーボンベースボールパークの特徴
■ゼロカーボンベースボールパークの特徴 (写真は阪神電鉄提供)
(写真は阪神電鉄提供) ■尼崎市とのつながり
■尼崎市とのつながり (写真は空から見たゼロカーボンベースボールパーク=阪神電鉄提供)
(写真は空から見たゼロカーボンベースボールパーク=阪神電鉄提供) ■スリーエコチェンジ
■スリーエコチェンジ ■スポーツチームが取り組む意義
■スポーツチームが取り組む意義 (写真=コラッキー/阪神電鉄提供)
(写真=コラッキー/阪神電鉄提供) ■球場運営の苦労
■球場運営の苦労 ■イベント
■イベント