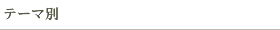──前編でお話されていた、海洋での分解性を高めるというのも強みになりますか。
そうですね。プラスチックのリサイクル技術も進んでいますが、どうしても発展途上国を中心に、海洋に一般ゴミが流出しています。ウミガメの鼻にストローがささっている衝撃的な写真を見た人もいると思いますが、海洋ゴミはなかなか減らず、分解しやすい材料をつくるという視点も大事ですので、海洋分解性に関する技術開発も重要だと思います。まずは、木質由来のポリ乳酸を商業ベースに乗せることが目標です。森林資源を使ってプラスチックをつくる、そういう時代を当たり前にしたいです。
プラスチックは品質とコストともに優れた素材です。今はこれだけ地球温暖化が進み、「石油資源を使うのはどうなのか」「枯渇するのでは」と問題になっていますので、石油に依存せず、木からプラスチックがつくれて、かつ生分解できるとなれば、置き換えていくことが必要だと思います。
──セルロースを分解するセルラーゼは、量産できるものですか。
我々がつくっているものではないのですが、量産されているものです。セルラーゼの原料はいろいろあるのですが、糖を発酵させてつくります。ものによっては、セルロースを原料にしてつくることもあります。製造コストや酵素の能力には、まだ改善の余地があると考えています。
──発酵の力はすごいですね。
日本は食品を中心に古くから“発酵”という手法を使ってきました。微生物の力を借りて、バイオマスをベースにした「バイオものづくり」の技術を確立していく。それは最先端の取り組みと言っても過言ではないと思います。
実は製紙業界は斜陽じゃない、とPRしたいですね。
■髙木さんの就活
──髙木さんはもともと研究者の道に進もうと思っていたのですか。
はい、研究職に就きたいなと思っていました。ただ、大学に残るか、会社に行くかは迷っていまして、モノづくりに興味があったので、メーカーに行きたいと思っていました。
──就活はされたんですか?
はい。10社ぐらい受けました。食品系が多かったですが、王子HDから内定が出ました。大学でやってきた研究のことと、新しい素材開発に関わり、事業化に貢献したいという熱意をアピールしました。
──就活の際に、研究室からの推薦はあったのですか?
研究室の推薦はなかったです。前編でもお話ししましたが、就活する中で、大量のセルロースをもっている製紙メーカーは面白いなと思っていました。ペーパーレスになって行くという転換期にあるので、新規事業というか、研究所の重要性がすごくあるんじゃないかと思いました。
──王子HDに決めた最終的な理由は。
日本最大級の森林資源を持っているということは揺るぎない事実です。そこは強みだと思います。製品をつくるだけでなく、そのもととなる原料も枯渇しない地盤があるメーカーは珍しい。新たな研究の種がたくさんある会社だと思いました。
■王子HDの働きやすさ
──王子HDでは働きやすさを感じますか。
すごく感じています。私は研究職ですので、研究したことを論文や特許にしたり、学会に発表したりするチャンスももらえて、しかも成果として認めてもらえます。
 SDGs(持続可能な開発目標)関連の業務に携わっている若手・中堅社員に直撃インタビューする「SDGsに貢献する仕事」の第28回目。製紙業を中核とする王子ホールディングス(HD)の後編をお届けします。製紙業が逆風のなか、酵素や微生物などの力で木からプラスチックや燃料をつくる「バイオものづくり」に取り組む王子HD。本格的な量産化に向けて試行錯誤を続ける研究員は、世の中にないものをつくりだす「王子精神」の最前線にいられることに大きなやりがいを感じています。就活当時の話や、就活生へのメッセージもうかがいました。(編集長・福井洋平)
SDGs(持続可能な開発目標)関連の業務に携わっている若手・中堅社員に直撃インタビューする「SDGsに貢献する仕事」の第28回目。製紙業を中核とする王子ホールディングス(HD)の後編をお届けします。製紙業が逆風のなか、酵素や微生物などの力で木からプラスチックや燃料をつくる「バイオものづくり」に取り組む王子HD。本格的な量産化に向けて試行錯誤を続ける研究員は、世の中にないものをつくりだす「王子精神」の最前線にいられることに大きなやりがいを感じています。就活当時の話や、就活生へのメッセージもうかがいました。(編集長・福井洋平)


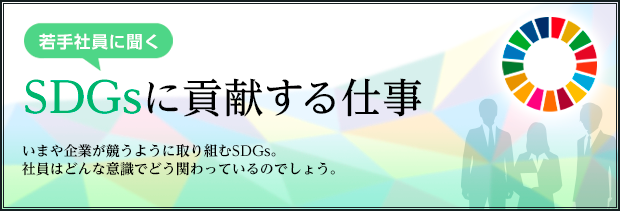
 ■量産化に向けて
■量産化に向けて ■残る課題
■残る課題 (写真=鳥取県米子市のパイロットプラント/王子HD提供)
(写真=鳥取県米子市のパイロットプラント/王子HD提供) ──前編でお話されていた、海洋での分解性を高めるというのも強みになりますか。
──前編でお話されていた、海洋での分解性を高めるというのも強みになりますか。 ■王子HDで働くやりがい
■王子HDで働くやりがい