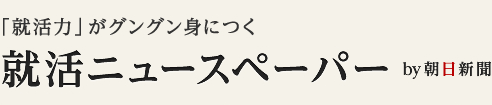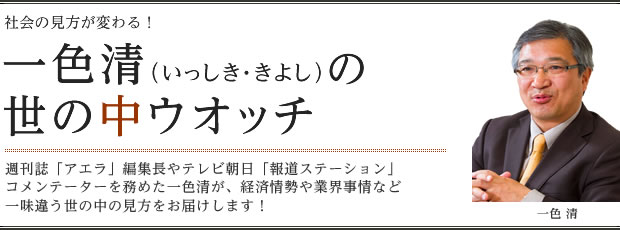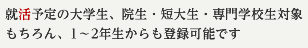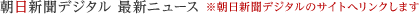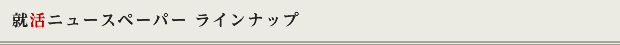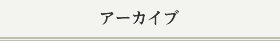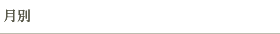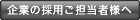「愛される会社」を考えさせる2冊の本
まず、「象の墓場」ですが、世界最大のフィルムメーカーがデジタル社会についていけず衰退していく様を、日本法人に勤める者たちの空しい奮闘ぶりを通じて描いた小説です。作者の楡(にれ)さんは、実際に世界最大のフィルムメーカー、コダック日本法人に15年間勤めていた方です。小説ではありますが、リアリティーにあふれているのは、楡さん自身が体験したり見聞きしたりしたことが下敷きになっているからだろうと思います。
コダックは従業員に優しいエクセレントカンパニーとして有名でしたが、2012年、倒産しました。写真の世界がデジタルカメラになって、フィルムがいらなくなったためです。小説では、「70年代の後半には、そのことを予見する社内レポートが上げられていたんだ。間違いなく、2010年までには、銀塩(フィルム)の時代は終わり、完全にデジタルに取って代わられるとね」と登場人物に言わせています。にもかかわらず、とても儲かるフィルムから離れられず、時代の波に乗り遅れて衰退していくわけです。
「ジェフ・ベゾス 果てなき野望」は、世界最大のネット通販会社アマゾンを創ったジェフ・ベゾスの人物像を描いたノンフィクションです。ベゾスの全面協力のもとに経済誌のジャーナリストが書いたもので、公式伝記とも言える本です。
ベゾスは、デジタル社会の波に乗って大成功を収めた経営者です。コダックがデジタル社会の敗者なら、アマゾンは勝者です。この本の中でも、「他人に食われるくらいなら、自分で自分を食ったほうがずっとマシなわけです。コダックのようにはなりたくありませんからね」と、アマゾンが自社で電子書籍事業を始めることについて、コダックを引き合いに出して説明しています。
ただ、アマゾンの社風はエクセレントカンパニーとはほど遠く、ブラック企業という言葉のほうが近いと感じさせる実態が描かれています。ベゾスは「懸命かつ猛烈に長時間働く」という言葉を口癖のように繰り返したそうです。女性社員がワークライフバランスに配慮するようベゾスに質問すると、ベゾスは「君は職場を選び間違えたのかもしれないね」と答えたと言います。
倹約も徹底されます。会社の駐車場でも駐車料金を取りますし、社員食堂に会社の補助はありません。出張はエコノミー。ベゾスはプライベートジェット機を持っていますが、社員が同乗するときは必ず「君の分は私が自腹を切っているんだよ」と言うそうです。
こうした「猛烈体質」で他者を蹴落としながら大きくなってきたわけですが、最近、ベゾスは「どうすれば恐れられるのではなく、愛される存在でいられるのか」ということを考えているといいます。「アップルやナイキ、ディズニー、グーグル、ホールフーズ、コストコ、そしてUPSでさえも顧客に好感を持たれている大企業だと私には思える」とし、逆に恐れられることの多い企業としては、ウォルマートやマイクロソフト、ゴールドマン・サックス、エクソンモービルなどを挙げています。アマゾンが愛される企業になるためには、「愛想がよくて頼りになるだけでは、あるいは、顧客を中心に考えるだけでは不十分だ。重要なのは、創意工夫をするところだと見られること、征服者ではなく探検者として見られること」というのが、現時点でのベゾスの結論だと書いています。
人々に愛される会社には、いい人材が集まります。愛される会社になりたいとある時点で思うようになることは、会社の発展過程でよくあることです。でも、愛されるためにはどうすればいいのかは難しい問題です。私は、ベゾスの結論にまだ足りないのは、「会社は社会をよくするために存在し、そのためには社会との調和も考えなければならない」ということではないかと思うのですが、いかがでしょうか。