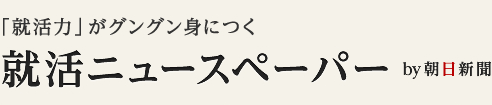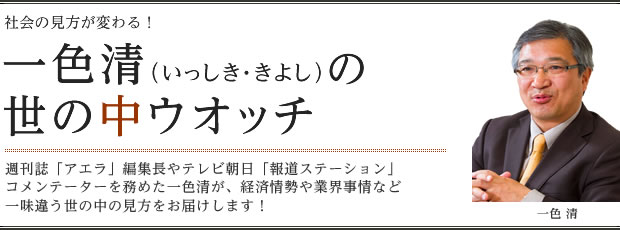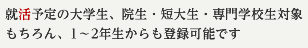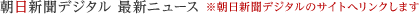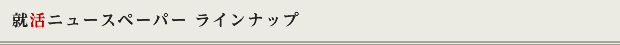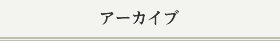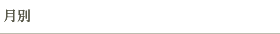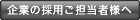同期はライバルというより仲間
堺雅人さん演じる半沢直樹は、東京中央銀行の大阪西支店融資課長です。中小企業経営者だった父親の自殺に関わりのある銀行に入り、「頭取を目指して」銀行内の理不尽、社会の理不尽と闘います。理不尽に立ち向かえず歯がみするばかりの多くのサラリーマンは、思わず「半沢がんばれ」と叫んでしまいます。
セリフもいいんですよね。「やられたらやり返す。倍返しだ」が決めセリフですが、「部下の手柄は上司のもの、上司の失敗は部下の責任」とか「銀行は晴れの日に傘を貸して、雨の日に取り上げる」といったセリフも、上司や銀行に怒りを込めて言うわけですから、スカッとします。いずれも昔から使われてきた言い回しですが、半沢直樹が使うと新しい命が吹き込まれたように言葉が生き返ってきます。
脇役も個性的です。出世欲に取り憑かれている支店長、支店長の腰巾着になりきっている副支店長、合併前の銀行出身者の出世頭である切れ者常務、計画倒産して雲隠れしたふてぶてしい西大阪スチール社長、その愛人、おねぇ言葉の国税局査察部統括官。そして、このドラマで重要な役割を演じるのが同期の仲間たちです。半沢直樹が窮地に陥ったときにアドバイスしたり、行内のシークレットな情報を伝えたりするのは、同期の連中です。中には、ストレスから一時心を病んでその後関連会社に出向していく同期もいます。このドラマの原作は、直木賞作家の池井戸潤さんの小説「オレたちバブル入行組」「オレたち花のバブル組」ですから、同期が描かれるのは当然といえば当然でしょうか。
採用の形が多様になってきた今でも、同期という言葉はまだまだ生きています。新卒の入社が「4月に一斉」ということが続く限り同期意識はなくならないでしょう。
バブル経済の時には景気がよくてどの会社も多くの人を採用しました。バブル入行組のように、同期の人数が多いのは、得でしょうか損でしょうか。「損だ」と思う人が多いでしょう。会社にポストは限られています。課長、部長、役員と上に行くほどポストの数は少なくなっていきます。年功序列の意識がまだまだ残る日本の会社では、こうしたポストを同期が奪い合う形になります。そうであれば、同期の人数が多ければ、ポストに就けない人が多くなるのは道理です。実際、バブル入社組と言われる現在40代前半くらいの人たちは早くから出向や転籍の話が聞かれました。
ただ、私は同期の人数が多いことが一概に損とばかりは言えないとも思います。同期の人数が多いと、競争意識が強くなりパワーのある世代になりがちです。その前後に同期の少ない世代があると、同期の多い世代がポストを奪ってしまうことはよくあります。また、同期の多い世代は会社のリーダーを生む可能性が高く、同期の仲間を引き立てたり、面倒を見たりすることもあります。
人数が多くなくても、強い世代もあります。スターのいる世代です。プロ野球では、松坂大輔世代とか斎藤祐樹・田中マー君世代といった呼び方があります。スター選手がその世代の選手を刺激し世代全体のレベルアップが図られ、世間もスター選手の同期として認知するために、特別な世代として扱われるわけです。会社も似たところがあって、同期に飛び抜けてできる人がいると、知名度の高いその人を通じて同期全体が会社に認知されやすくなります。よく会社で「花の○○年」などと呼ばれる世代は、こうしたスター社員がいる場合が多いように思います。
いずれにしても、同期はライバルですが、助け合う仲間でもあります。いい同期をたくさん持つことは、会社生活の刺激であり、支えとなることと思います。同期を蹴落とすことに力を入れるより、同期と一緒に高めあおうとしたほうがずっといいということは、就活時代から肝に銘じていてもいいのではないでしょうか。