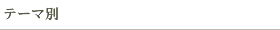■田中さんのお仕事
──田中さんはディレクター職とのことですが、いまの具体的なお仕事内容を教えてください。
田中晴基さん 私はデロイト トーマツ(コンサルティング、以下略)の「Strategy Unit 」という戦略チームに所属しています。業種・業界問わず、幅広いクライアントの経営戦略や事業戦略を扱うチームです。私はそのなかで「CSV/Sustainability」というサービスの全体をリードする立場にいます。2014年の入社後は新規事業などのイノベーション、一般的な中期経営計画、事業戦略や経営戦略を担当してきましたが、その後10年ほどはCSV経営に関わるプロジェクトに取り組んでいます。
――CSVとは?
田中 Creating Shared Valueの略です。SDGsに象徴されるようなサステナビリティや社会課題解決といった取り組みを通じ、「いかに企業を競争優位に変えるか」「ビジネスを通じて社会課題を解決し、成長するか」といった大きな問いを立てて、コンサルテーションしています。
■SDGsとともに10年間
──2015年にSDGsが採択されてからいままでの10年間を、ほぼすべてビジネス現場で体感されてきたということですね。
田中 はい、最近ではそれを自己紹介のキャッチフレーズにしています。
SDGsが採択される2015年以前は、社会課題というとMDGs(Millennium Development Goals)という概念がありました。MDGsは新興国の課題をパブリックセクターやソーシャルセクターが中心となって解決していくためのゴールです。SDGsが採択されてからは先進国も対象になり、企業が当事者として強く参画することになりました。
──SDGsに取り組まれるようになったきっかけは何ですか。
田中 私が転職してかかわった最初のプロジェクトの上司が、新しいアジェンダをビジネスに昇華していくことが好きな人でした。2014年にCSVに関する本を出しており、パリ協定とSDGs(ともに2015年)よりも早くこういう時代が来ると見越して、コンサルファームのビジネスとしてサービス化していこうという時期に私が入社したのです。その動きをみて面白そうだと思い、それ以来、一緒にサービスをつくってきました。
■朴さんの仕事
──朴さんのご出身は。
朴守娟さん 生まれも育ちも韓国です。2013年に大学入学をきっかけに来日して、アメリカにも留学しましたが、日本には10年ぐらい住んでいます。
──朴さんの入社後の仕事を教えてください。
朴 2019年4月入社で、今はないのですが「Pool Unit」という部署に配属されました。新卒や入社して間もない若手のスタッフが配属される部署で、専門領域を決めず、全社のいろいろなプロジェクトにアサインされていました。そこでPublic Unit(現Sustainability Unit)とStrategy Unitを行ったり来たりしながら、SDGsの環境関連プロジェクトを2~3年ぐらい経験しました。2022年に今のシニアコンサルタントという役職になり、正式にStrategy Unitに配属されました。そこからはいわゆるSDGsで環境、社会課題と、それから全く違う部署の事業戦略や経営戦略の両方を経験しています。田中さんのお仕事とも重なっていて、お世話になっています。
──配属は「こういうところに行きたい」と希望するのですか。
朴 そうですね。 基本的に入社前も入社してからも面談があり、希望を出します。希望と部署側の要件がマッチすれば所属できたり、プロジェクトにアサインされたりします。
 SDGs(持続可能な開発目標)関連の業務に携わっている若手・中堅社員に直撃インタビューする「SDGsに貢献する仕事」の第25回は、監査・コンサルティングのデロイト トーマツ グループから、デロイト トーマツ コンサルティングが登場します。就活生にも人気の高いコンサルティング業界。そのなかで時代の先を読み、SDGsが採択される前からサステナビリティと企業の成長をトレードオン(両立)させるという難題に取り組んできました。コンサル業界ならではのインプット力、アウトプット力を駆使し、SDGsの歩みに伴走してきた2人にたっぷりと話をうかがいました。(編集長・福井洋平)
SDGs(持続可能な開発目標)関連の業務に携わっている若手・中堅社員に直撃インタビューする「SDGsに貢献する仕事」の第25回は、監査・コンサルティングのデロイト トーマツ グループから、デロイト トーマツ コンサルティングが登場します。就活生にも人気の高いコンサルティング業界。そのなかで時代の先を読み、SDGsが採択される前からサステナビリティと企業の成長をトレードオン(両立)させるという難題に取り組んできました。コンサル業界ならではのインプット力、アウトプット力を駆使し、SDGsの歩みに伴走してきた2人にたっぷりと話をうかがいました。(編集長・福井洋平)


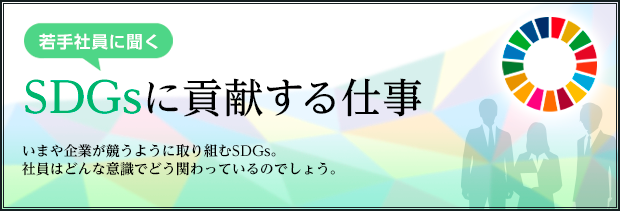
 ■田中さんのお仕事
■田中さんのお仕事 ■WorldClass
■WorldClass  ■インパクトの浸透
■インパクトの浸透 ■SDGsが始まったころ
■SDGsが始まったころ ■新型コロナ以降
■新型コロナ以降 ■コンサルティングの仕事とは
■コンサルティングの仕事とは ■企業の悩みが1周
■企業の悩みが1周