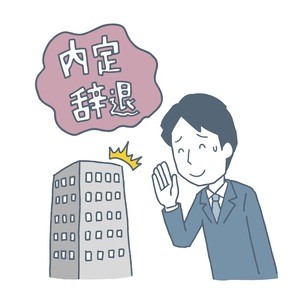
そうなると心配になるのが、内定をとったあと正式な内定(多くは10月に出されます)の前に他社への就活を終わらせるよう強要する、いわゆる「オワハラ」です。2015年に流行語となってからは監視の目も強まり減少傾向ですが、いまもまだオワハラは存在しています。オワハラにあったらどうするか、考えてみましょう。(編集部・福井洋平)
(イラストはPIXTA)
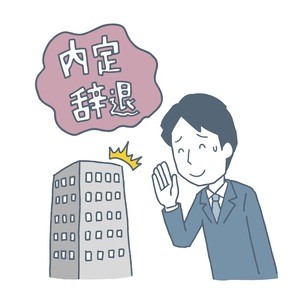
今回は、朝日新聞が提供するメディアサイト「withnews」の連載「#就活しんどかったけど」から、オワハラに関する記事を紹介します。
●「オワハラって本当にあるんだ」とっさのウソ 内々定辞退の苦い経験
記事では九州地方在住、大学4年の女性が経験したオワハラを紹介しています。昨年5月ごろにホテル業界から最初に内々定をもらったのですが、その連絡を受けた電話で「ほかに受けている企業はありませんか?」とも聞かれ、とっさに「ありません」とウソをついてしまいました。担当者からは、内々定者向けの研修会も案内されたそうです。女性はうそをついたことが気がかりで、後日採用担当者と話をした際に別に選考を受けている企業があると伝えたところ、「全て辞退してください」と迫られた、といいます。
政府は2023年4月、経団連などに向けてオワハラ防止を徹底するよう、要請文を出しました。ここではオワハラを「就職をしたいという学生の弱みに付け込んだ、学生の職業選択の自由を妨げる行為」と定義し、具体的には以下のような行為をオワハラとしています。
・正式な内定前に他社への就職活動の終了を迫ったり、誓約書等を要求したりする
・内(々)定期間中に行われた業務性が強い研修について、内(々)定辞退後に研修費用の返還を求めたり、事前にその誓約書を要求したりする
この定義に照らして考えれば、さきほどwithnewsで紹介されていた事例は確実にオワハラとなりそうです。実際この女性は大学の就職課に相談し、辞退してもいいというアドバイスを受けています。
内閣府の「学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査」(2023年度)によると、ほかの企業への就職活動の終了を強要するような「オワハラ」を受けたことがある学生は9.4%でした。2021年度は11.6%、2022年度は10.9%だったので、全体的にはやや減少傾向にあります。
オワハラの内容については、「内々定を出す代わりに他社への就職活動をやめるように強要された」が67.2%で一番多く、ついで「内々定の段階で、内定承諾書の提出を求められた」が38.1%、「辞退を申し出たところ、引き留めるために何度も説明を受けたり、拘束を受けた」が11.1%、「内々定後懇親会等が頻繁に開催され、必ず出席するように求められた」が9.8%、「内々定の条件として、急遽大学の推薦状の提出を求められた」が7.8%となっています。
大学の推薦状については、もともとは理系の学生が大学から推薦を受けて応募する場合に出されることが一般的でしたが、文理を問わず選考が進んでいる段階の学生から大学推薦状を出させることで、辞退しづらくさせるというケースも出てきています。立教大学は推薦状は理系の学校推薦選考の応募者にのみ発行し、それ以外は「学生の『職業選択の自由』を妨げるおそれがあるため、発行いたしません」とウェブサイトに明記しており、他にも同様のアナウンスをしている大学があります。
オワハラがいまだになくならない大きな理由は、人手不足です。ほしい採用数を達成できない企業が増加し、せっかく内々定を出した学生に逃げられたくないという気持ちが強くなることはやむをえないとも言えます。
ただ、企業側はそれでもほかの学生や、あるいは既卒者を採用するなど手の打ちようがあります。一方、学生の人生は一度きり。自分自身で守るよりほかありません。オワハラに屈せず、納得のいく選択をするべきです。そのためには、
・オワハラは政府が防止を徹底するよう呼びかけている
・内々定を出すかわりに他社の就活をやめるよう強要することは、オワハラにあたる
・「後付け推薦」の要求は、オワハラにあたる
・いわゆる「内定承諾書」には、拘束力はない
ことを知ってください。自分のされていることが「オワハラ」だと感じたら、ぜひ大学のキャリアセンターなどに相談し、手を打ちましょう。


2025/12/20 更新
※就活割に申し込むと、月額2000円(通常3800円)で朝日新聞デジタルが読めます。


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10