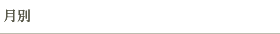企業情報を読ませて強みと弱みを把握
生成AIは自己分析や企業研究、エントリーシート(ES)の作成、面接の練習など就職活動のあらゆる局面で活用可能です。生成AIが得意な分野、不得意な分野を把握することで、よりよい活用が可能になります。
生成AIは言語をあつかうことがうまく、さらにチャットGPTは最新のバージョンになってコミュニケーションの取り方が飛躍的にうまくなっています。そのため、
・質疑応答
・対話
・文章の作成
・要約
といった作業が得意です。情報の要約が得意なので、たとえば上場企業なら有価証券報告書などを読み込ませ、「会社の強みと弱みをおしえてください」とプロンプト(AIに対する指示の文章)を入れると、効果的に会社の情報をチェックしたり、同業の会社同士の比較が効率よく行えたりします。面接練習に特に威力を発揮しますが、詳しくは後編でお話します。
自己分析は自分でやったうえでAIを使おう
一方で、抽象的なイメージを取り込んだり、感情や体験を言語を通さず直接理解したりすることはできません。もとになる情報を言語化してインプットしない限り、何も生み出してくれることはない、ということです。私はよく「100点のものは120点にはできないし、60点のものを100点にすることもできない」と学生に伝えています。自己PRを生成AIをつかって作る際も、これまでの経験やエピソードの棚卸し、自己分析については自分でちゃんと深めておいて、生成AIに渡せる要素をつくっておく必要があります。
また、生成AIはわかりやすい表現で文章をつくってくれる反面、文章に感情や思い入れを込めることが苦手です。出てきた文章をそのまま使うのではなく、感情を込めて自分の言葉に書き直すことを忘れないでください。そうしないと、面接でボロが出てきます。
生成AIに自分の強み、長所などの要素を複数入力して自己分析をつくってもらおうとすると、いくつかの要素を抜いて文章をつくってくることがあります。対策としては、まとめて要素を入力せず、一つ要素を入れて文章を作成し、さらにそこに一つ要素を追加して文章修正、もう一つ要素を追加して文章修正……というように少しずつ要素を加えていき、その都度文章をチェックしていくという方法があります。このほうが、自分が入れたい要素をすべて入れた文章をつくることができます。
見出し作成や文章校正もAIで

また、AIによっては文章から「見出し」をつくってくれたりもします。面接でダラダラ長くしゃべるといい結果につながりませんが、ESに書いた自己PRなどの「見出し」をつくることで文章のポイントをつかむことができ、メリハリをきかせて話せるようになります。「子どもでもわかるように」「小学4年生でも理解できるように」というプロンプトをいれることで、さらにわかりやすい見出しを生み出すこともできます。
書いた文章の校正もAIを活用できます。たとえば、こういったプロンプトを打ち込みます。最初に生成AIに対して「就活アドバイザー」などの役割を与えるのがポイントです。
「あなたは優秀な就活アドバイザーです。以下に貼り付ける文章を修正してください。その際、
#誤字脱字をみつけたら、修正案もつけてください
#表記のゆれは調整してください
#半角、全角が統一されていない場合、半角に統一してください
#文章の末尾は「です、ます」体に統一してください」
(要約の例)
一例として、就活ニュースぺーパの「就活の採用選考『解禁』 4分の3がすでに内々定も 長期化にどう対応する?」の記事を、380字以上400字以内で要約してもらいました。ただ、3回依頼を繰り返しましたが、要約した文字数はいずれも300字程度でした。
「6月1日に企業の採用選考が解禁されたが、実際の就活は早期化しており、4月末時点で74.9%が内々定を獲得。一方で、進路を絞りきれない学生や面接に苦戦する学生も多く、就活は長期化の傾向も見られる。学生の間では早期に動く層と出遅れる層で「二極化」が進んでおり、売り手市場とはいえ対策不足では苦戦も免れない。企業研究や面接経験が不足していると不利になるため、幅広い業界に目を向けて情報収集し、納得のいく進路選択をすることが重要だ。企業とのミスマッチを防ぐためにも、自分の希望や適性を見つめ直し、早期に行動する一方で、焦らず悩む時間も大切にすべきだ。」
また、「小学4年生でもわかるように見出しを5つ考えてください」というプロンプトに対しては、
1 はやく始めた人が うまくいく「しゅうかつ」
2 おわらない「しゅうかつ」で なやむ人もいるよ
3 しゅうかつを がんばる人と まだのんびりしている人がいる
4 めんせつで うまく話せないと たいへん!
5 いろんな会社をしらべて 自分にぴったりを見つけよう!
という結果になりました。
昨年から「AI活用」に舵切る大学も
私はふだん大学での営業活動を行っています。これまでは「学生はなるべく、生成AIは使わないほうがいい」というスタンスの大学がほとんどだったのですが、昨年ごろからAIの進化、浸透にともなって「どうせ生成AIを使うのだから、うまく使って結果を出そう」と考える大学が増えてきました。そのため今年に入って 、学生向けにチャットGPTなどの生成AIを活用する方法を授業や講演で行うようになりました。学情が1年半ほど前に行った調査では、就活やインターンシップで就活を利用した学生は25.3%でした。いまは半数以上になっているのではないか、と思います。マイナビが5月に公表した2026年卒学生向けの調査では、就職活動でAIを利用した学生は66.6%にのぼっています。
生成AIのなかでもチャットGPTが特に優れているというわけではないですが、多くの学生が使っている印象があるのでこれに絞って情報提供しています。大学によっては自校内で使える独自のAIを持っているところもあるので、そういうものは使っていい、という話もしています。
(7月8日公開の後編に続く)
◆朝日新聞デジタルのベーシック会員(月額980円)になれば毎月50本の記事を読むことができ、スマホでも検索できます。スタンダード会員(月1980円)なら記事数無制限、「MYキーワード」登録で関連記事を見逃しません。大事な記事をとっておくスクラップ機能もあります。お申し込みはこちらから。
2026/01/03 更新
- テスラ販売8.6%減 BYDに完敗、首位陥落 マスク氏への反発も(08:02)
- 世界は空前の抹茶ブーム 余波で国内のお茶高騰 お~いお茶も綾鷹も(14:00)
- 百貨店「一拍おいて」初売り そごう横浜店は14年ぶりの2日開催(13:55)
- 中部電力社長、多業種参入の新規事業は「思い切った選択と集中やる」(08:00)
- 中国BYD、25年のEV販売28%増 「テスラ越え」で世界首位へ(21:53)
※就活割に申し込むと、月額2000円(通常3800円)で朝日新聞デジタルが読めます。
就職最新情報を知る
企業と業界を知る
ニュースで就活力を高める
-
1
就活イチ押しニュース高市政権ではじめての「税制大綱」 自動車税制、年収の壁、住宅ローン減税……...
-
2
就活イチ押しニュース金利引き上げも円安進行、経済指標の動きにより敏感に【週間ニュースまとめ12...
-
3
就活イチ押しニュース内々定率すでに3割、内々定獲得後の「中だるみ」どうする? 年末年始に考えて...
-
4
就活イチ押しニュース【27卒学生の就活ルポ】新しい業界に興味出てきた、年明けからがんばる【カレ...
-
5
就活イチ押しニュースネトフリとディズニー、メディア界揺るがす2つのニュースに注目【週間ニュース...
-
6
就活イチ押しニュース【27卒学生の就活ルポ】内定獲得したが、どのタイミングで受諾する?【カメラ...
-
7
就活イチ押しニュースFIFAがトランプ大統領に「平和賞」贈る 1カ月前に新設【週間ニュースまと...
-
8
就活イチ押しニュース【27卒学生の就活ルポ】まだ先と思っていた本命企業の選考がスタート【サッカ...
-
9
就活イチ押しニュース【27卒学生の就活ルポ】内定取って、難しそうな企業にもチャレンジ【ウェスト...
-
10
就活イチ押しニュース【27卒学生の就活ルポ】2社内定も、毎日やることがあって大変【eスポさん7】