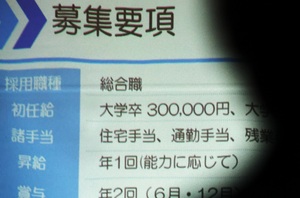
就活生にとっては朗報ともいえる動きですが、ここで考えてほしいことが「初任給をあげるためのお金=『原資』はどこから出てきたのか」ということです。会社の利益があがり、そのぶんを給料アップにまわしていればよいのですが、実はそうではないケースもあります。朝日新聞の記事に寄せられた経済学者のコメントをもとに考えてみましょう。(編集部・福井洋平)
(写真・大卒の初任給30万円をうたう企業も=2025年3月1日、千葉市美浜区の幕張メッセ/写真は朝日新聞社)
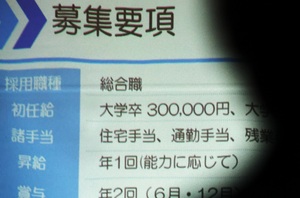
人手不足を背景に、採用力向上のため初任給をアップする企業が相次いでいます。直近のニュースから主なアップ企業をピックアップすると、
・ヤマハ(静岡県浜松市)……大卒、高卒ともに1万3千円上げ、26万3千円、21万3千円に。
・北洋銀行(札幌市)……学歴を問わず一律27万円に引き上げ
・ニトリホールディングス(札幌市)……1万5千~2万円引き上げ、大卒は29万円、大学院卒は30万5千円に
・ファーストリテイリング(山口市)……3万円引き上げて33万円に
・三井住友銀行(東京)……大卒初任給を4万5千円引き上げて30万円に
・九州電力(福岡市)……大卒で2万円増の25万円に
・NTTグループ……大卒の標準ケースで2万5千円程度引き上げ、30万円以上(住宅補助費含め34万円以上)の水準にする
・王将フードサービス(京都市)……大卒は2万1500円引き上げて30万円に
・パナソニックHD(大阪府門真市)……大卒で1万9千円引き上げ、26万9千円に
・日本ガイシ(名古屋市)……大卒初任給を2万2千円引き上げ28万5千円に
・オリエンタルランド(千葉県浦安市)……一律1万7千円引き上げ、大卒・大学院卒は27万2千円に
・大和ハウス工業(大阪市)……10万円増やし、33万2千円(高専・専門学校卒)~36万2千円(大学院卒)に上げる
など、今年も日本を代表するような企業が初任給引き上げを表明していることがわかります。情報会社の帝国データバンクが2月に結果を公表した企業アンケートでも、2025年4月入社の新卒社員に支給する初任給を前年度より引き上げると回答した企業が71.0%に達しています。

もうひとつ考えるべきことは、入社後の賃金上昇カーブです。中高年層の賃金を下げ、カーブを抑えることで若い社員層の賃金を上げている場合、その会社で勤めている間にもらえる賃金は変わらないか、場合によっては減っているケースも考えられます。
近年は若い世代を中心に転職も一般化してきており、人材を引き留めるために若い層を手厚く処遇する流れも生まれています。経団連が会員企業に実施している人事・労務調査の2024年データによると、賃金をベースアップする際にどこに配分するかという問い(複数回答)に対して一番多いのは「一律定額配分」(51.1%)ですが、次いで「若年層(30歳程度まで)へ重点配分」という回答が34.6%となっています。一方で「中堅層(30~45歳程度)へ重点配分」は9.4%、「ベテラン層(45歳程度以上)へ重点配分」は1.1%となっており、若年層になるべく賃金を多く支払っていこうという傾向が見て取れます。また、「職務・資格別の配分」も25.2%あり、年齢に応じて一律に給料をあげるのではなく仕事内容によって給料に差をつける仕組みも広がっていきそうです。日本はながらく若いうちは賃金が安く、社歴が重なるに従って賃金が伸びていく年功序列型の賃金体系が一般的でしたが、その仕組みがどんどん崩れていっているのです。
初任給の高い企業は魅力的に感じますが、その会社が初任給をアップするためにどういった施策をとったかは、わかる範囲で調べておくと会社選びの際に役に立つと思います。また、人手不足が加速すると若手社員に賃金を手厚くして、その後の賃金の伸びはメリハリをつけるという傾向も強まってくるでしょう。入社後に転職を視野に入れるのか、稼げる職種につくことを考えて行動するのか。長い目で見たときに自分はどういうふうにキャリアアップしていくかを考える必要性も、いま増してきていると感じます。就活を機に、自分がもらう賃金について理解を深めていきましょう。
◆朝日新聞デジタルのベーシック会員(月額980円)になれば毎月50本の記事を読むことができ、スマホでも検索できます。スタンダード会員(月1980円)なら記事数無制限、「MYキーワード」登録で関連記事を見逃しません。大事な記事をとっておくスクラップ機能もあります。お申し込みはこちらから。

2025/12/24 更新
※就活割に申し込むと、月額2000円(通常3800円)で朝日新聞デジタルが読めます。


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10