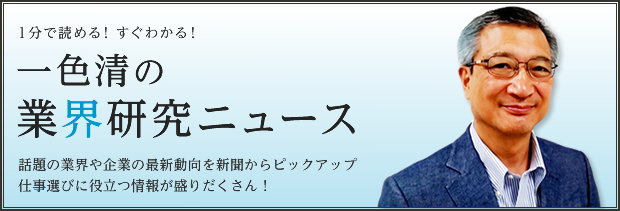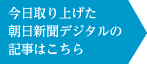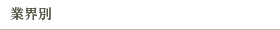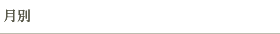1990年代まで世界トップのシェアを誇っていた日本の造船業界ですが、コストの競争になって韓国、中国に抜かれ、今は世界3位に落ちています。長く構造不況業種といわれ、大手造船会社は造船部門を別会社にしたり、撤退したりしてきました。しかし、ここにきて業界への注目度ががぜん高まっています。きっかけの一つは高市政権の誕生です。高市政権の日本成長戦略会議では、成長投資をするべき17の分野のひとつに造船が挙げられ、「(政府が)生産能力拡大のための大規模投資を大胆に支援する」としています。アメリカのトランプ大統領が衰退したアメリカの造船業を復活させるために日米で協力する提案を歓迎していることもあり、造船業に久しぶりの強い追い風が吹いています。日本の造船業界は人手不足が深刻でした。大規模な投資がおこなわれるなら、業界にとっては人材確保が重要になります。大手は新卒の採用数を増やすことが予想され、就職戦線でも注目されます。
(写真・進水式を迎えた捕鯨母船=2023年8月31日、山口県下関市/写真はすべて朝日新聞社)
人件費と国の支援の差で日本は劣勢に
日本の造船業は1956年に建造量で欧州を抜いて世界一になり、1990年代までほぼ世界のトップを維持していました。しかし、1990年代後半に韓国に抜かれ、2000年代半ばには中国にも抜かれ、世界3位に転落しました。今の世界シェアは中国が50%以上、韓国が30%程度、日本が15%程度と3カ国の間に差がついています。造船において画期的な新技術はあまりなく、一定の技術力があれば、製造コストが競争力の差になります。製造コストの中で差が出るのは人件費です。製造工程の自動化は進みにくいため、多くの人手が必要で、人件費はかなりのウェートを持ちます。また、中国や韓国は造船業を主力産業に位置付け、国を挙げて力を注いできました。日本が劣勢になっているのは、人件費と国の支援の差とみられています。
今治造船が日本のトップメーカーに

造船業界の団体には、日本造船工業会と日本中小型造船工業会のふたつがあります。日本造船工業会は大型の船をつくる会社の団体で17社が会員になっています。日本中小型造船工業会はその名の通り中小型の船をつくる会社の団体で、正会員数は49社(2025年10月21日現在)です。造船会社は全国の海沿いにありますが、比較的多いのが瀬戸内海沿岸で、現在の建造量のトップは今治造船(本社・愛媛県今治市)です。かつては三菱重工業、川崎重工業などの大手7社が大型船の建造を主に担っていましたが、大手7社に入っていなかった今治造船が中小造船所を統合するなどしてコスト競争力と技術力を上げ、トップに躍り出ました。2025年6月には2位のジャパンマリンユナイテッド(JMU、本社・横浜市)への出資比率を30%から60%に引き上げ、子会社化しました。JMUはIHI、住友重機械工業、日立造船(現カナデビア)、日本鋼管(現JFEHD)の4社の民間船部門を統合してできた会社ですので、今治造船が大手といわれた会社の多くの造船部門を子会社にした形です。大手といわれた会社の多くは、防衛省におさめる艦艇や潜水艦の建造に特化しています。このほか、常石造船、尾道造船、大島造船所、名村造船所なども有力な造船会社です。
(写真・今治造船のドック=2017年9月、香川県丸亀市)
アメリカとの覚書で日本の仕事が増える

アメリカの造船再生に日本の造船業界が関わるとなると、大きなビジネスチャンスになりそうです。アメリカは第二次世界大戦直後までは「造船大国」と呼ばれていましたが、近年の船舶建造量の世界シェアは0.1%と低迷しています。フィラデルフィアにあるフィリー造船所は200年以上の歴史がある造船所ですが、2024年に韓国のハンファグループが買収しました。トランプ大統領は造船能力で中国に大きな差をつけられていることを安全保障上の問題だとして、日本や韓国の協力を得て造船業の再生に乗り出そうとしています。日本はアメリカとの関税交渉の中で両国の造船能力の拡大などで協力する覚書に署名しました。日本の造船会社の仕事が増えることが予想されます。
(写真・韓国企業のハンファグループが買収したペンシルベニア州フィラデルフィアの造船所=2025年5月16日)
CO2削減と無人運航が研究課題
業界には技術的な研究課題もあります。ひとつは二酸化炭素(CO₂)排出削減のための取り組みです。現在の船の燃料は重油で、燃やすと当然CO₂を排出します。再生可能エネルギーを使って作った水素やアンモニアを燃料にすればCO₂を排出しない船となります。また、植物や木材などから作ったバイオ燃料や廃食用油からつくった燃料を加えることでもCO2を減らすことができます。もうひとつの課題は、人による操舵のいらない無人運航船の開発です。現在、実証実験を進めています。実現すれば、乗組員を大幅に減らすことができるため、運航費用の削減につながります。
一過性の光か長期的な光か
構造不況業種と言われて久しい造船業界に急に光が当たっています。これがトランプ大統領の思いによる一過性の光なのか、世界の構造変化による長期的に続く光なのかは、まだわかりません。海に囲まれた日本で貿易のためにも防衛のためにも船は絶対に必要です。また、船はまだまだハイテク化が進んでおらず、ハイテク化の余地が大きい乗り物でもあります。造船業は本来、もっと光が当たってもいい業界だったのかもしれないという気もしてきます。業界の将来性についての判断はとても難しいのですが、興味のある人は自分で調べて自分で考えてみてください。
◆朝日新聞デジタルのベーシック会員(月額980円)になれば毎月50本の記事を読むことができ、スマホでも検索できます。スタンダード会員(月1980円)なら記事数無制限、「MYキーワード」登録で関連記事を見逃しません。大事な記事をとっておくスクラップ機能もあります。お申し込みはこちらから。