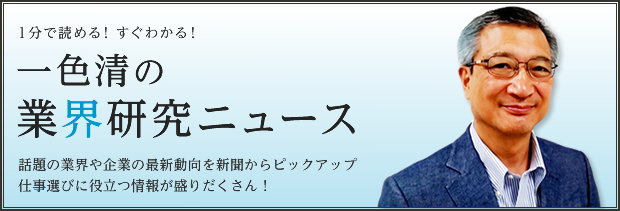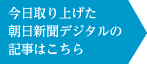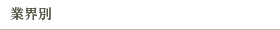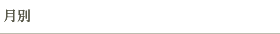高市政権が誕生し、防衛費増額に拍車がかかっています。高市早苗首相は、2027年度に防衛費を国内総生産(GDP)比2%にする現行目標を2025年度中に前倒しで達成する方針を表明しました。また、さらなる防衛費増を視野に入れた安保関連3文書の改定方針も表明しています。背景には、アメリカのトランプ政権が求める防衛費増の圧力があります。日本が防衛費を増やす流れは当分止まりそうにはありません。
こうした流れを受けて、防衛産業といわれる会社の株価は「防衛バブル」という声が聞かれるほど急上昇しています。実際、業績も上向きです。ただ、おおもとの発注者は防衛省、つまり国だけで、発注の増減は世界情勢や国内の政治情勢に左右されます。また、国と特定企業だけで構成される閉ざされた業界でもあります。外部から見えにくい業界だけに、志望する人はしっかりとした業界研究をすることが必要だと思います。
(写真・防衛省=東京都新宿区/写真はすべて朝日新聞社)
三菱重工業、川崎重工業、IHIが大手

防衛産業関連の業界団体としては日本防衛装備工業会があります。正会員は143社(2025年9月時点)です。同会は1988年に日本兵器工業会が解散したあとに新設される形で誕生しました。それ以来会長は19人いますが、その出身会社は三菱重工業3人、川崎重工業3人、IHI3人、三菱電機3人、東芝3人、日本製鋼所2人、日本電気2人となっています。この7社が防衛産業の主要企業といえます。中でも大手3社といわれているのが三菱重工業、川崎重工業、IHIです。下請け会社のすそ野は広く、戦闘機なら約1100社、護衛艦なら約8300社に上るといわれます。
(写真・三菱重工業本社の入り口に掲げられた看板=2019年)
三菱電機などシステム受注も多額に

防衛装備庁が公表している2024年度の防衛装備品の契約額によると、1位は三菱重工業で1兆4567億円です。三菱重工業は艦船や戦闘機の製造に強く、2024年度の実績としてはイージス艦、地対艦誘導弾、高速滑空弾が挙げられています。2位は川崎重工業で6383億円です。川崎重工業は潜水艦やヘリコプターの製造に強く、実績としては輸送ヘリコプターや哨戒機の製造が挙げられています。3位は三菱電機で4956億円です。三菱電機はコンピューターシステムなどに強く、実績としては装備計測評価システムや中距離地対空誘導弾などが挙げられています。4位は日本電気で3117億円、5位は富士通で1736億円。この2社はいずれもコンピューターシステムの仕事を請け負っています。このほか、ジャパンマリンユナイテッドは艦船、IHIは航空機エンジン、日本製鋼所は砲弾と、それぞれ強い分野を持っています。
(写真・IHIのロゴ)
オーストラリアに護衛艦を輸出
日本の防衛産業にとって最近の大きな出来事は、日本が護衛艦をオーストラリアに輸出することが決まったことです。オーストラリア政府は8月、三菱重工業の最新鋭「もがみ」型護衛艦(FFM)をもとに新型護衛艦を共同開発すると発表したのです。日本が護衛艦を輸出するのは初めてで、護衛艦のような殺傷能力の高い大型兵器の輸出は、戦後日本の武器輸出政策の大きな転換点になるといわれています。また、2022年には日本、イギリス、イタリアの3カ国で次期戦闘機の共同開発をするプロジェクトが決まり、2025年7月にはこのプロジェクトの本部の開所式がイギリスでありました。3年以内に試作機の飛行実験を実施する方針です。高市政権は武器輸出の対象を絞っている5類型を撤廃することにしており、これまで以上に日本製の武器輸出が盛んになることが予想されます。
防衛産業にチェック体制が課題に

業績面では追い風が吹く防衛産業ですが、不祥事のニュースもあります。川崎重工業が建造する海上自衛隊の潜水艦で、エンジンの燃費性能に関する検査データが改ざんされていた可能性が高いことが明らかになりました。不正は20年ほど前から続いていた恐れがあるとのことです。川崎重工業をめぐっては、潜水艦の修理に関して防衛予算を使って多額の裏金をねん出していた問題も発覚し、防衛省は特別防衛監察を実施しました。防衛産業と防衛省とのつながりは深く、防衛省の官僚が防衛産業にたくさん天下りしています。持ちつ持たれつの関係の中、外部の目が届きにくい構造になっており、チェック体制が課題になっています。
(写真・川崎重工業神戸本社=2024年7月4日)
民生品とはちがう特別な業界

敗戦国からスタートした日本は平和国家として、防衛装備品の製造や輸出に一定のしばりをかけてきました。それが国際情勢の緊張や国内政治の変化により、しばりをゆるめる流れになっているため、防衛産業が成長産業に変貌しようとしているのです。手放しで喜べる状況ではありませんが、そういう時代になったと受け止めるしかありません。防衛産業に興味のある就活生は、防衛装備品は民生品をつくったり売ったりするのと大きく違うということを理解しておきましょう。防衛装備品は安さや使い勝手よりも性能や耐久性が優先されます。また、多様な一般顧客がいるわけではなく、防衛省というひとつの顧客だけが相手です。まずは、こうした特別な業界であることを知っておくことが必要になります。
(写真・滑走路へ移動する航空自衛隊のF2戦闘機=2024年10月30日、長崎県大村市の長崎空港)
◆朝日新聞デジタルのベーシック会員(月額980円)になれば毎月50本の記事を読むことができ、スマホでも検索できます。スタンダード会員(月1980円)なら記事数無制限、「MYキーワード」登録で関連記事を見逃しません。大事な記事をとっておくスクラップ機能もあります。お申し込みはこちらから。