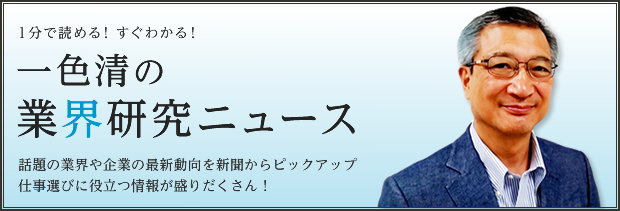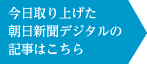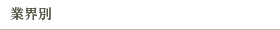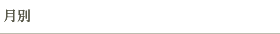日本に誕生して50年余がたったコンビニエンスストアは、すっかりわたしたちの生活になくてはならないものになりました。全国すみずみにいきわたり、国内の店舗数は頭打ちになっているため、コンビニ各社は成長を海外に求めています。しかし、逆に海外のコンビニ大手が日本の企業を買収しようという動きが出てきました。「セブン-イレブン」を展開する国内最大手のセブン&アイ・ホールディングス(HD)が、カナダのコンビニ大手「アリマンタシュオン・クシュタール」から買収の提案を受けているのです。買収が実現すれば、コンビニを経営する会社としては世界最大となり、北米での事業などで圧倒的な強みが発揮できるとみているようです。
セブンの経営陣は買収に賛同していないため買収が実現するかどうかはわかりませんが、成り行き次第ではさらなる業界再編につながる可能性もあります。このほかにも業界では、人手不足への対応や宅配などの新しい事業への取り組みといった課題を抱えています。業界が「成長の曲がり角」を迎えていることは間違いありませんが、暮らしのインフラになった今、まだまだ可能性はあるという見方もあり、依然注目したほうがよい業界といえるでしょう。
(写真・セブン-イレブンのロゴ/写真はすべて朝日新聞社)
売上高は増えるが、店舗数は減少傾向
経済産業省の商業動態統計によると、2023年のコンビニ業界の売上高は前年に比べて3.3%プラスの12兆7321億円となっています。コンビニの業界団体である日本フランチャイズチェーン協会によると、日本国内のコンビニの店舗数は24年12月末で55736店で、こちらはわずかながら前年より減っています。店舗数は2018年ごろをピークに横ばいから減少傾向に転じています。小売りの業態別売上高をみると、スーパーマーケットがトップで約16兆円、コンビニがそれに続き、ドラッグストアが8兆円余、百貨店が6兆円弱となっています。コンビニの売り上げの伸び率は、スーパーよりは多いものの、ドラッグストアや百貨店よりは小さくなっています。
大手3社が売上高の9割を占める

日本のコンビニは、セブンーイレブン、ファミリーマート、ローソンが大手3社で、この3社が業界全体の売上高の約9割を占めています。日本フランチャイズチェーン協会に加盟しているコンビニとしては、ほかにミニストップ、デイリーヤマザキ、セイコーマート、ポプラがあります。店舗数はセブンーイレブンが国内2万1千店余、海外8万店余、ファミリーマートが国内1万6千店余、海外8千店余、ローソンが国内1万4千店余、海外7千店余で、国内外ともこの3社が圧倒的に多くの店舗を展開しています。ミニストップは国内1800店余、海外が180店余です。残り3社は国内だけの展開で、デイリーヤマザキは約1000店、セイコーマートは約1200店、ポプラは約300店となっています。
(写真・ファミリーマートのロゴ)
ファミマは伊藤忠、ローソンは三菱商事とKDDI

コンビニ各社にはそれぞれつながりのある会社があります。セブン‐イレブンを運営しているセブン&アイ・ホールディングスには三井物産が出資しています。ただ、出資比率は1.87パーセント(2024年11月30日現在)と小さく、関係は深くはありません。一方、ファミリーマートは伊藤忠商事が95%近くの株式を持ち、伊藤忠商事の傘下にある会社です。ローソンは三菱商事の子会社の形でしたが、2024年8月にKDDIも出資することになり、今は三菱商事とKDDIが50%ずつ出資する会社になっています。コンビニが総合商社とつながりを持っているのは、商社が消費者と直接結びつく「川下」領域に力を入れるため、コンビニを利用しようとしてきたためです。ローソンに出資することになったKDDIは新しい分野の出資者ですが、コンビニ経営に通信の技術を利用できると考えています。大手3社以外のコンビニは、ミニストップが大手流通グループ・イオンの、デイリーヤマザキが山崎製パンのそれぞれコンビニ事業です。セイコーマートは店舗のほとんどが北海道にあり、北海道の地域コンビニとして親しまれています。ポプラはローソンと業務提携しています。
(写真・ローソン店員の制服を着て写真撮影にのぞむ(左から)三菱商事の中西勝也社長、ローソンの竹増貞信社長、KDDIの高橋誠社長=2024年2月6日)
地方ではスーパーの代わりにもなる

コンビニが抱えている課題はいくつもあります。ひとつめは海外事業の拡大で、大手3社はアジアや北米を中心に店舗数を増やしています。ふたつめは、国内の深刻な人手不足への対応です。アジアの人材を教育して活用しているほか、客が自分で決済をするセルフレジの導入、さらには無人店舗の展開も進めようとしています。また、宅配事業の拡大も課題となっていて、高齢化が進む地方などでは商品を自宅などに届ける事業を進めています。ロボットを使うことも視野に入れ、配達ロボットの実験にも取り組んでいます。さらに、取扱商品を広げる動きもあります。ファミリーマートはコンビニエンスウェアと名づけて衣料品を取り扱ったり、大手コンビニでは若者に人気の韓国コスメなどの化粧品にも力を入れたりしています。地方ではスーパーから仕入れた生鮮食料品を取り扱うコンビニもあり、スーパーの代わりに「買い物難民」の受け皿の役割を果す動きもあります。
(写真・野菜などの生鮮食品も並ぶコンビニ店=2020年5月、山形県)
曲がり角の先にあるコンビニの姿を考えよう
コンビニ業界は国内では成長期から成熟期に入っていますが、海外ではまだまだ成長余力があります。また、カナダのコンビニ大手がセブン‐イレブン事業を買収しようとする動きがあるように、世界を舞台にした業界再編がおこなわれる可能性があります。コンビニの本部で働く人にとっては、国際的な視野や感覚が必要になります。また、地域や時代の変化とともにコンビニに置かれる商品やコンビニが果たす役割にも変化があるはずです。そうした変化に敏感で、アイデアを出したりそれを実行に移したりする力も必要になってきます。志望する人は、曲がり角の先にあるコンビニの将来の姿を考えてみましょう。
◆朝日新聞デジタルのベーシック会員(月額980円)になれば毎月50本の記事を読むことができ、スマホでも検索できます。スタンダード会員(月1980円)なら記事数無制限、「MYキーワード」登録で関連記事を見逃しません。大事な記事をとっておくスクラップ機能もあります。お申し込みはこちらから。