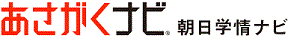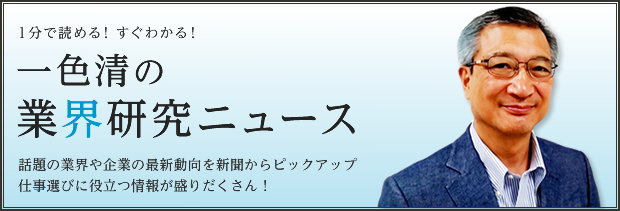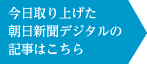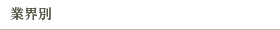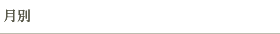旧ビッグモーターの保険金不正請求、企業向け保険料のカルテル、親しい保険代理店を通じての情報漏洩など、2022年から24年にかけて損害保険業界ではいくつもの不祥事が明るみに出ました。2024年末には、金融庁が業界に改革を促す具体案を示しています。たとえば大規模な保険代理店への規制を強化したり、競争環境をゆがめる恐れのある契約先企業への便宜供与の禁止を求めたりする、といった内容です。
業界自体もこれまでの悪しき慣習をなくし、新しいビジネスモデルで出直そうとしています。今後はコンプライアンス を重視し、健全な競争環境の中で商品力や営業力によって各社が切磋琢磨していく方向を目指す、といいます。ただ、主力の自動車保険は若者の「クルマ離れ」や自動運転化により将来性に陰りが見えているなど、不安材料はあります。こうした不安を解消し、これまで以上に発展していくためには、新商品の開発や新規事業への進出がカギになります。
(写真・日本損害保険協会の入る損保会館=東京都千代田区/写真はすべて朝日新聞社)
中世のヨーロッパで仕組みができる
損害保険の歴史は古く、古代ギリシャ時代の海上輸送では嵐や海賊に出会ったときに積み荷を海に捨てることがあり、その損害を荷主と船主で負担するという習慣があったそうです。これが損害保険の始まりとされます。ヨーロッパでは中世に金融業者が介在するようになり、航海が失敗した時には金融業者が積み荷の代金を支払い、成功した時には手数料を受け取るという海上保険の仕組みができました。その後、こうした仕組みは海だけでなく陸にも広がり、火災保険が始まりました。予期のできない損害については、保険をかけてリスクを回避しようという考え方が広がっていったのです。日本でも近代的な保険制度が、幕末から明治維新にかけてヨーロッパから入ってきました。今の東京海上日動火災保険は1879年(明治12年)に誕生しています。
大手は3グループ4社の体制に

金融庁が国内での営業免許を与えている損害保険会社は56社あり、うち日本の会社が35社、外国系の会社が21社です。このうち、大手3グループと呼ばれているのが、東京海上ホールディングス(HD)、 MS&ADインシュアランスグループホールディングス(HD)、SOMPOホールディングス(HD)です。会社としては大手4社という呼び方があり、東京海上日動火災保険、損害保険ジャパン、三井住友海上火災保険、あいおいニッセイ同和損害保険を指します。東京海上HDの傘下が東京海上日動火災保険、SONPOHDの傘下が損害保険ジャパン、MS&ADインシュアランスHDの傘下が三井住友海上火災保険とあいおいニッセイ同和損害保険です。2008年にあった世界的経済危機のリーマン・ショックのあと再編・統合が進み、大手は3グループ4社の体制になりました。
(写真・三井住友海上火災保険の本店=東京都千代田区)
損保ジャパンは介護事業でも大きな地位

4社の中でもっとも売上高が大きいのは東京海上日動火災保険です。日本の損害保険会社の草分けであり、安定した企業風土や営業力の強さが知られています。損害保険ジャパンは介護事業に進出し、介護業界でも大きな地位を占めているのが特徴です。三井住友海上火災は三井と住友というふたつの財閥系が一緒になった会社であり、三井財閥や住友財閥の流れをくむ会社を顧客として持っているのが強みです。あいおいニッセイ同和損害保険はトヨタ自動車グループと親密で、他社に比べて自動車保険の比率が高いのが特徴です。
(写真・損保ジャパン本社=東京都新宿区)
サイバー保険やペット保険が伸びる
損害保険会社が取り扱っている商品の中で柱となっているのが自動車保険です。自動車保険には自動車の保有者に加入が義務付けられている自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とそれでは足りない時の上乗せとなる自動車保険(任意保険)のふたつがあります。この任意保険が、業界の主力商品となっています。次いで大きいのが火災保険で、最近は保険でカバーする範囲が水害や盗難にも広がっています。このほか、傷害保険や海上保険や地震保険も取り扱っています。いま新規分野として伸びているのが、サイバー攻撃などに対処するサイバー保険、犬や猫などのペットを対象としたペット保険などです。
スマホで簡単に契約できる保険も

大手4社のほかにも、オンラインで申し込める自動車保険に特化した会社やペット保険専門の会社など、特徴のある会社があります。最近ではスマホで簡単に契約できる損害保険にスマホと縁の深い会社が参入しています。au損保はKDDIなどが出資している損害保険会社で、自転車保険やペット保険などに力を入れています。ソフトバンクグループが立ち上げたPayPay保険サービスは、PayPayアプリから手軽に加入できる損害保険サービスをおこなっています。こうした保険は少額でその都度入ることもできるのが特徴です。
(写真・au損保の営業開始会見=2011年、東京都港区)
事後的な保険から一歩踏み出したビジネスモデル
業界では柱となっている自動車保険の将来が不透明なのが心配事です。また、代理店に頼る営業が時代遅れになりつつあるという問題もあります。そのため、業界は新しいビジネスモデルを模索中です。東京海上HDは2024年11月に、河川や上下水道など社会インフラの設計を手がける建設コンサルティングのID&Eホールディングスの買収を発表しました。損保会社はこれまで事故が起きた後に保険金を支払うのが仕事でしたが、東京海上HDは事故を予防したり事故や災害が起きた時に早期復旧の提案をしたりするサービスに力を入れることにしています。事後的な保険の仕事から一歩踏み出した、新しいビジネスモデルと位置づけることができそうです。
時代の変化に敏感であることが求められる
損害保険会社は海外展開にも力を入れています。国内市場の大きな伸びが期待できないなら海外市場に期待しようということです。たとえば、2024年3月末の東京海上日動火災の海外拠点は44の国と地域に及んでいます。現地スタッフ数は約3万2千人で、日本からの駐在員は292人います。また、商品開発の分野では、社会の変化に伴った新商品が求められています。サイバー攻撃のような新しいリスクがこれからも登場してくるのは間違いないでしょう。画期的な新商品を開発することができれば、会社の発展につながります。求められる人材としては、国際感覚があることや時代の変化に敏感であることなどが挙げられそうです。
◆朝日新聞デジタルのベーシック会員(月額980円)になれば毎月50本の記事を読むことができ、スマホでも検索できます。スタンダード会員(月1980円)なら記事数無制限、「MYキーワード」登録で関連記事を見逃しません。大事な記事をとっておくスクラップ機能もあります。お申し込みはこちらから。