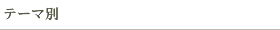■徐さんのやりがい
──徐さんのやりがいは?
徐 私が入社したタイミングで「クラッカーにバイオマスナフサを投入する」という話があり、実際に2021年12月に投入されました。私はフェノール事業部の中で、フェノール系のバイオ商品を市場に普及させるプロジェクトのリーダーを務めています。
──2年目でプロジェクトリーダー!?
徐 私が一番下で、年次の上の方が6人いるプロジェクトですが、バイオへの関心や熱意があるからと抜擢していただきました。チーム内でお客さんにバイオ化の提案をしに行くときは「私、行きます」と率先して手を挙げていて、事業部全体のプロジェクトになったときに任命されました。大学時代からの興味を仕事に取り入れられていて、すごく今は楽しいです。
──やる気に加えて、かなり勉強したのでしょうね。
徐 お客さんに説明する機会が多かったので、知識を蓄える必要がありました。ある程度、場数も踏んで知識を持っていたので、それもあったのかなと思います。
──バイオマスナフサはどの程度普及しているのでしょう。
徐 日本でバイオマスナフサ原料の導入を最初に始めたのは弊社です。2050年までにカーボンニュートラルを達成する目標を掲げているので、その取り組みの一環だと思います。
ただ、私たちのお客さんには川中に位置する化学メーカーが多く、アドマーのようにバイオマスのニーズがまだまだなく弊社が先取りしている形です。去年は海外のお客さんにバイオフェノールを出荷しましたが、お客さんを探している段階で、国内はこれからです。
──大変なことは?
徐 まだお客さんからのニーズが少なく、こちらからさまざまなアプローチを考えなければいけません。お客さんへの説明はもちろん、化学品関係の連盟や協会にプレゼンしたり、マーケティング活動を進めたりしています。自動車メーカーなどのブランドオーナーの方々は、川中のお客さんよりカーボンニュートラルに敏感です。当社の専門部隊であるグリーンケミカル事業推進室とともに、ブランドオーナーに直接ご紹介するなど、連携しながらいろいろな方策を考えるのが大変なところです。
──どんなところにアプローチを?
徐 自動車や化粧品業界、食品包装材のメーカーです。必ずしもフェノールが使われるわけではないメーカーにも行き、川下のニーズの状況や情報の収集をしています。一番川下の消費者に近いところにアプローチして、そこからさかのぼって持っていかないとなかなか進まないと思います。
■大学時代の研究
──大学時代の研究とのつながりは?
山﨑 今は高分子をやっていますが、大学でやっていたのは低分子で全く逆でしたね。有機合成を専門にしていたので入社面談のときには農薬の研究など、有機合成のスキルを活かせるところで働きたいと思い、グループ企業の三井化学アグロを志望していました。面談で「お客さんとも話して、お客さんの課題を解決したい」と伝えたので、その意図と適性を汲み取って、今の部署に配属されたのかなと思います。今となってはこの部署で良かったと思っています。
──なぜお客さんと話したいと?
山﨑 細かい改良や、こうしたらこう良くなるという作業を繰り返すのが好きな性分でした。その成果を世の中に出すには、研究室にこもってフラスコを振っていてもしょうがない。お客さんと話をして、お客さんの課題を解決すれば、それが世に出て社会貢献ができると思ったんです。
──入社当時はSDGsという言葉もなかったころですが、今、環境対応がメインになっていることをどう感じていますか。
山﨑 さまざまな業界各社から多種多様な環境対応製品が発表される激変の時代の中、環境対応の開発を行うことはプレッシャーでもあり、研究者としての腕の見せ所でもあると感じています。
SDGsに関心が強く、バイオマスがほしいし、リサイクルもできないかとお客さんからの問い合わせを受けて開発をスタートしました。お陰で接着樹脂の業界の中でいち早く環境対応に取り組むことができた、そのチャンスには恵まれていたと感じています。それを製品化までこぎつけ、形にできたので達成感もあります。
──徐さんは学生時代からSDGsに関わっていたんですね。
徐 企業の事業活動やSDGsへの取り組みを評価して提言する活動をしていました。たとえば持続可能な森林の利用と保護を図るFSC認証(森林認証制度)とかフェアトレード認証をSDGsとひもづけられないかといった研究もしていました。
──どうしてSDGsに関心を?
徐 中学時代のサマーキャンプや大学でのオーストラリア留学で海外の人と関わり、環境意識の高さに影響を受けました。大学1年次に蟹江先生の授業でSDGsについて知り、こんな画期的な枠組みがあるんだと思いました。当時は全然盛り上がっていなかったので、何か研究ができたら面白いなと。
 「SDGsに貢献する仕事」をしている若手・中堅社員に聞くシリーズの第6回、三井化学の後編です。研究開発職の男性社員は、有名化粧品のチューブのバイオマス(植物など生物由来の再生可能資源)化に取り組み、製品開発に成功しました。基礎化学品「フェノール」の営業担当の女性社員は、バイオへの熱意が評価されて入社2年目でプロジェクトリーダーに抜擢されました。二酸化炭素(CO₂)を多く排出している化学メーカーこそ、カーボンニュートラル(脱炭素)を早急に進めなければならないという信念が、その原動力となっています。(編集長・木之本敬介)
「SDGsに貢献する仕事」をしている若手・中堅社員に聞くシリーズの第6回、三井化学の後編です。研究開発職の男性社員は、有名化粧品のチューブのバイオマス(植物など生物由来の再生可能資源)化に取り組み、製品開発に成功しました。基礎化学品「フェノール」の営業担当の女性社員は、バイオへの熱意が評価されて入社2年目でプロジェクトリーダーに抜擢されました。二酸化炭素(CO₂)を多く排出している化学メーカーこそ、カーボンニュートラル(脱炭素)を早急に進めなければならないという信念が、その原動力となっています。(編集長・木之本敬介)


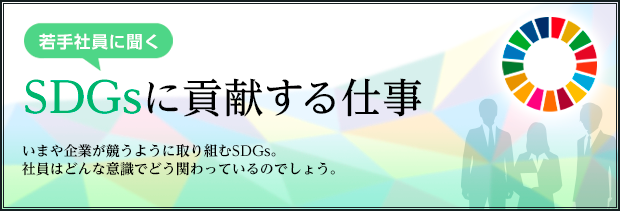
 ■山﨑さんのやりがい
■山﨑さんのやりがい ■徐さんのやりがい
■徐さんのやりがい ■就活振り返り
■就活振り返り