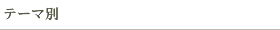■自己紹介
──自己紹介をお願いします。
山﨑孝史さん 入社9年目で、今は「アドマー®」いう製品の研究開発をしています。大学時代は日夜フラスコを回し続けていましたが、今はパンを包装する袋や油のボトルなどに使用される素材を作り、もっと良いものを作ろうと日々研究しています。
徐瑛加さん 入社2年目で、「フェノール」という基礎化学品を担当しています。営業だけでなく生産計画、デリバリー、収益管理もしています。大学はリベラルアーツのような学部だったので、かなり幅広く学び、日本のSDGs界の権威である蟹江憲史先生のゼミで研究していました。
■三井化学にとってのSDGs
──まず、社としてのSDGsへの取り組みを教えてください。
山﨑 そもそも、三井化学は社会課題の解決から始まった歴史があります。約110年前の創業ですが、日本の人口が増え食料不足が社会課題となる中、石炭コークスの副生ガスから農業用の肥料を作ることで社会課題にコミットしました。「課題があれば取り組むのが必然」というDNAがある会社です。
SDGsについては私が入社したころはまだ言葉もありませんでしたし、2015年にSDGsが出てきたときも社内であまり響いていませんでしたが、2018年ごろから環境意識が一気に高まりました。お客さんと会話をしていると「環境に良い、こういう製品はありませんか」というニーズが出るようになりました。それを受けて、我々ができることを考え、今では率先してSDGsに貢献できる製品の開発を進めています。
──「BePLAYER」と「RePLAYER」を掲げていますね。
徐 素材の素材から見直して世界をより再生的に変えていきたいという考えのもと、石油からバイオマス(植物など生物由来の再生可能資源)原料に転換し環境負荷低減に貢献する「BePLAYER」と、廃棄物を資源と捉え、マテリアルリサイクルやケミカルリサイクルをしていく「RePLAYER」の二つの方向性です。BePLAYERでは、2021年に日本で初めて「バイオマスナフサ」を化学品の心臓部である「クラッカー」という設備に原料投入し、そこから生まれるバイオマス製品の生産を始めました。温室効果ガス削減を進め、カーボンニュートラル達成を目指すアクションがBePLAYERで、当社が作ったもののみならず、サプライチェーン全体のリサイクル率向上を進めるのがRePLAYERです。お客さんの目指すべき方向が何で、自分たちはどう貢献できるか、BePLAYERとRePLAYERの概念をベースに社会貢献を全社で進めています。
──「脱プラから改プラへ」も掲げていますが、「改プラ」とは?
山﨑 よく「脱プラ」と言われますが、プラスチックは社会基盤を支える製品です。ありとあらゆるところにプラスチック製品が使われており、「脱プラ」には限界があると思います。一方、当社が実施した一般消費者へのアンケートでは「脱プラ」の浸透により、ものを買うことや使うことに罪悪感を持つという声も聞かれました。ものを買うのは私たちの楽しみのでもあるので、そこに罪悪感を持つのは寂しいですよね。そこで、プラスチックや化学品の素材を原料から根本的に見直し、一人ひとりの消費行動をより再生的なものにする素材を提供し、消費するときの罪悪感を取り除く。それが「改プラ」であり、当社が提供できる価値だと考えています。
──たしかに、プラスチックは「悪いもの」というイメージが広がりましたね。
山﨑 レジ袋有料化が典型的ですね。できるだけ減らそうという社会要請の中で、我々に何ができるのかを考えることが大切です。その取り組みとしてバイオマス原料を使うBePLAYERと、リサイクルを進めるRePLAYERを展開しています。我々の化学に関する専門知識を使ってより良いプラスチックを開発し、社会に提供するのが使命だと思います。
徐 プラスチックは私たちの生活に浸透しています。「プラスチックから紙へ」という動きがありますが、たとえばスーパーの総菜パンの袋を紙にすると保存が効きません。やはりプラスチックの包装材は必要なので、プラスチック自体を変える「改プラ」が大事なんです。
──改プラの代表的な製品は?
山﨑 一例として、バイオマスナフサを原料として製品化したバイオマスPP(ポリプロピレン)「Prasus®」の採用が広がっています。バイオマスナフサは植物由来や動物由来、たとえば天ぷらなどの廃食用油などを原料にプラスチックを作るので、石油由来ではありません。今後も化学メーカーだからこそできる価値を創り、社会に発信していく必要があると感じています。
 SDGs(持続可能な開発目標)関連の業務に携わっている若手・中堅社員に直撃インタビューする「SDGsに貢献する仕事」の第6回は、総合化学メーカーの三井化学です。私たちの生活に欠かせない一方、環境に負荷を与えているプラスチック。同社は、「脱プラ」には限界があるため、石油由来ではなく環境に良い素材を開発する「改プラ」を掲げて業界をリードしています。若手社員の仕事にも、サプライチェーンの上流を担うBtoB(企業間取引)ならではのSDGsへの貢献がありました。(編集長・木之本敬介)
SDGs(持続可能な開発目標)関連の業務に携わっている若手・中堅社員に直撃インタビューする「SDGsに貢献する仕事」の第6回は、総合化学メーカーの三井化学です。私たちの生活に欠かせない一方、環境に負荷を与えているプラスチック。同社は、「脱プラ」には限界があるため、石油由来ではなく環境に良い素材を開発する「改プラ」を掲げて業界をリードしています。若手社員の仕事にも、サプライチェーンの上流を担うBtoB(企業間取引)ならではのSDGsへの貢献がありました。(編集長・木之本敬介)


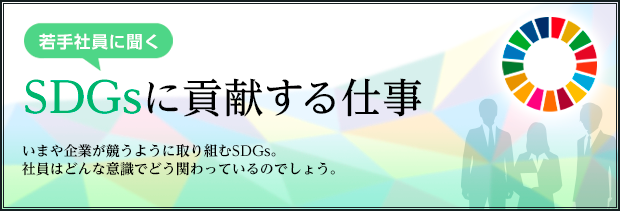
 ■自己紹介
■自己紹介 ■山﨑さんの仕事
■山﨑さんの仕事 ■徐さんの仕事
■徐さんの仕事