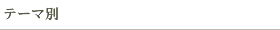■自己紹介
──自己紹介をお願いします。
今年で入社10年目です。ヤンマーのテクノロジー開発拠点の一つである中央研究所でトラクター開発に従事したのち、2014年にヤンマーアグリイノベーションに配属になりました。ヤンマーアグリイノベーションは、持続可能な農業の実現のため、農業機械に限らず農業に関わる全てのことに取り組むために2010年に設立した会社です。私は兵庫県養父(やぶ)市での「にんにく産地化プロジェクト」の担当になりました。耕作放棄地の再生や水田から畑への転作などにより、養父市のような中山間地での農業を活性化し、加工や流通・販売まで手がける六次産業化を支援することで持続可能な農業の実現を目指すプロジェクトです。2016年に国産ブランド「やぶ医者にんにく」として全国で売り出しました。今も関西のスーパーなどで販売している人気商品です。
──その後は?
ヤンマーマルシェの商品部で安全・安心な食の提供を目指して開発した「ライスジュレ(とろみのもと)」の開発・営業に携わりました。お米と水だけを原料とした100%植物由来のヤンマーオリジナル商品です。昨年1月からはフードソリューション部に所属し、農家からお米や野菜を仕入れ、食品メーカー・商社などの流通業者との販路マッチングを行うなど、生産者のビジネス拡大をサポートしています。
■ヤンマーのSDGs
──ヤンマーのSDGsの取り組みを教えてください。
「A SUSTAINABLE FUTURE──テクノロジーで、新しい豊かさへ。」というブランドステートメントを掲げています。人間と自然の豊かさの両立を「新しい豊かさ」と位置づけて、お客様の課題を解決するソリューションを提案しています。事業フィールドは「大地」「海」「都市」。エンジンの生産・開発・販売、農業経営サポートなど幅広い事業を展開しています。私はそのうちの「食・住宅設備機器事業」の担当で、「食の恵みを安心して享受できる社会」を目指す仕事です。ヤンマーは「食料生産」や「エネルギー変換」といった人々の暮らしに不可欠な領域で社会課題の解決に取り組んでおり、ブランドステートメントの体現こそがSDGsへの貢献につながると考えています。
──「YANMAR GREEN CHALLENGE 2050」はどんな内容ですか。
2022年に打ち出しました。一つ目はGHG(グリーンハウスガス=温室効果ガス)排出量実質ゼロの企業活動を実現すること、二つ目は循環する資源を基にした環境負荷フリーの企業活動を実現すること、そして最後にお客様のGHG排出ネガティブ・資源循環化に貢献すること──この三つの課題への挑戦を掲げています。
三つ目のお客様への貢献活動の一つとして、農業や食品加工の際に発生する食品廃棄物を有効活用できるようにするバイオコンポスター「YC100」を提供しています。国内では年間およそ2500万トンもの食品が廃棄され、社会課題になっています。またその処理では多くの二酸化炭素(CO₂)が出るので、廃棄物対策はお客様にとって喫緊の課題になっています。「YC100」は、たとえば和食チェーンの梅の花さんで採用され、運用を始めています。食品廃棄物をほぼ100%再利用して肥料を作り、ヤンマーマルシェの契約農家に提供して野菜などを作り、すべて梅の花さんに納品──という資源循環サイクルを実現しています。
──バイオコンポスター「YC100」はヤンマーマルシェが開発したのですか。
「YC100」の開発はグループ会社のヤンマーeスターですが、ヤンマーマルシェは「YC100」により発酵分解され生成された堆肥を利用した農作物栽培のサポートを行いました。具体的には、契約生産者に堆肥を使ってもらい、栽培から出荷までサポートしました。梅の花さんからは「資源循環の取り組みをしてみたい」というニーズがあり、京都セントラルキッチンで出た食品廃棄物を利用して、京都のヤンマーマルシェの契約生産者で大根を栽培する提案をしたのがスタートでした。資源循環サイクルを、グループ会社が連携して構築しています。
また、廃熱を利用可能な電気に変換するソリューションの提供なども行っています。ヤンマーは創業以来、産業用ディーゼルエンジンを事業の柱にしている会社なので、エネルギー変換技術にも力を入れています。
──エネルギー変換とは?
日本では、発電時に排出される熱の約6割は利用されずに廃熱として捨てられています。発電所から需要地まで電力を供給する代わりに、電気が使用される場所の近くで発電し、送電ロスなどの廃熱を抑えて電力を供給することは、省エネルギーとCO₂排出量の削減につながります。さらに最近では、発電の燃料に畜産や食品系廃棄物から発生するバイオガスや、水素を用いた取り組みも進めています。
 SDGs(持続可能な開発目標)関連の業務に携わっている若手・中堅社員に直撃インタビューする「SDGsに貢献する仕事」の第7回は、農業機械メーカーのヤンマーホールディングスです。農機を作って売る会社ですが、米や野菜を生産する農家との契約栽培事業も行っています。気候変動に対応できる栽培技術を伝え、営農計画から出荷、販売まで、生産者に伴走してトータルソリューションを提供する仕事です。担当者は約60軒の農家を訪ねるため、西日本を年中駆け巡っています。(編集長・木之本敬介)
SDGs(持続可能な開発目標)関連の業務に携わっている若手・中堅社員に直撃インタビューする「SDGsに貢献する仕事」の第7回は、農業機械メーカーのヤンマーホールディングスです。農機を作って売る会社ですが、米や野菜を生産する農家との契約栽培事業も行っています。気候変動に対応できる栽培技術を伝え、営農計画から出荷、販売まで、生産者に伴走してトータルソリューションを提供する仕事です。担当者は約60軒の農家を訪ねるため、西日本を年中駆け巡っています。(編集長・木之本敬介)


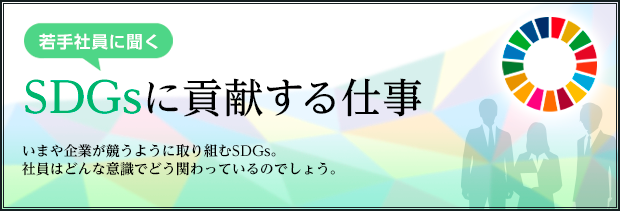
 ■自己紹介
■自己紹介 ■ヤンマーマルシェの事業
■ヤンマーマルシェの事業 ■井口さんの仕事
■井口さんの仕事