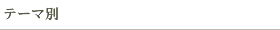■大学と就活
──どうして生産者と仕事をしたいと思ったのですか。
西東京市で生まれ、小中高は大阪、大学と大学院は東京でした。サラリーマン家庭でしたが、管理栄養士の母が食育に熱心で、食べるのが好きでした。いつも「食が人の体を作ってるんだよ」と言い、栄養バランスや薬膳なども身近でした。
高校2年になるとき理系・文系で迷い、「国連で世界の食料課題を解決したい」と思いました。日本の国連事務所に「国連に就職するには英語学科に入るのがいいですか」と問い合わせたら、「国連では英語を使うのは当たり前なので、大学では専門性を身につけてから来てください」と丁寧にメールを返してくれました。「食なら農業かな」と思ったものの、当時はバイオや作物栽培にはさほど興味がなくて。どうしようかなとテレビを見ていたら、柔道の「ヤワラちゃん」の谷亮子さんがCMでトラクターか何かに乗っていて、「面白そう」と思ったんです。物理は好きだったので「これなら自分でもできるかな」と。そこで東京農工大学に入り、農業機械系の精密農業の研究室に入りました。
──どんな研究をしたのですか。
当時、農作業時の事故で毎年300人くらいの方が亡くなっていることに衝撃を受け、農作業安全を研究テーマにしました。担当教授は「研究室に来ないで農家に行きなさい。農家に全ての答えがあるから」という徹底した現場主義で、研究室に所属した3年間、夏休みや田植え、稲刈りの時期にはインターンのように農家さんのところに行っていました。秋田、新潟、埼玉、愛知などの農家さんのところに行くと、みなさんとても誇りを持って農業をしていて、「食を作るのはすごいことなんだよ」と教えてくれました。彼らと一緒に仕事がしたいと強く思い、就活では「絶対に農機メーカーに行きたい」と絞りました。
──農機を作ろうと思ったのですか。
いえ、ヤンマーアグリイノベーションという会社で「新しいソリューションをやりたい」と人事と話していました。ただ、メーカーに入った以上は農機のことを知っておきたかったので、「初期配属は農機の開発をやり、経験を積んでから異動したい」と言いました。順調に自分の行きたい部署に行かせてもらっています。
──ヤンマーの選考で印象的だったことは?
「ヤンマーのためにこれがしたい」ではなく、「ヤンマーという土台が与えられたらあなたは何をしたいですか」と聞かれました。ヤンマーには人の可能性を信じ、挑戦を後押しする「HANASAKA(ハナサカ)」という価値観が根付いており、人材育成にも力を入れています。ヤンマーというフィールドを大いに活用して、受け身ではなくチャレンジしてほしいというメッセージだと思います。
──面接では何と答えたのですか。
「生産者にもっと入り込んだほうがいい」と提案しました。生産者とヤンマー、時には行政も一緒になり、三位一体になって事業を進める風土を作ることで、もっと現場で活躍する技術や商品、サービスを開発できるんじゃないか、という話をした記憶があります。
──ヤンマーの採用はヤンマーホールディングス(HD)一括ですか。
ヤンマーHDと、9社ある事業会社での採用を並行して行っています。HDは事業横断的にキャリアを積んだりグローバルに活躍したりしたい人に、より事業に特化してキャリアを積みたい人は各事業会社に入社しキャリアをスタートさせています。HDから各社への出向もあります。
■目標
──今後の目標は。
生産者がしっかりともうかる仕組みを構築し、事業としても軌道に乗せることが目標です。農業機械メーカーなのでトラクターなどハードの技術開発の土台はありますが、生育情報などを活かした生産者の意思決定を支援するツールをもっと充実できればと考えています。「テクノロジーで、新しい豊かさへ。」というブランドステートメントのもと、DXによる生育予測など農業経営が安定する事業開発にも携わっていきたいです。
 「SDGsに貢献する仕事」をしている若手・中堅社員に聞くシリーズの第7回、ヤンマーホールディングスの後編です。「生産者と仕事がしたい」と入社した女性社員は、田んぼに入って一緒に農作業もする泥臭い面もある仕事に「幸せ」を感じるといいます。農家が減って耕作放棄地も増える中、あの手この手で生産者を支えることが、生物多様性を守り、食料の安定供給にもつながります。持続的な食の未来のための取り組みです。(編集長・木之本敬介)
「SDGsに貢献する仕事」をしている若手・中堅社員に聞くシリーズの第7回、ヤンマーホールディングスの後編です。「生産者と仕事がしたい」と入社した女性社員は、田んぼに入って一緒に農作業もする泥臭い面もある仕事に「幸せ」を感じるといいます。農家が減って耕作放棄地も増える中、あの手この手で生産者を支えることが、生物多様性を守り、食料の安定供給にもつながります。持続的な食の未来のための取り組みです。(編集長・木之本敬介)


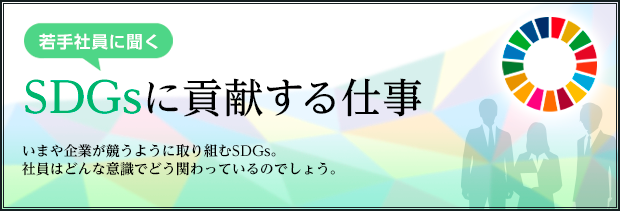
 ■やりがいと苦労
■やりがいと苦労 ■大学と就活
■大学と就活 ■働き方改革と社風
■働き方改革と社風