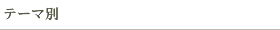SDGs(持続可能な開発目標)関連の業務に携わっている若手・中堅社員に直撃インタビューする「SDGsに貢献する仕事」。第27回はまちづくりを手がける大手デベロッパーの東京建物が登場します。「Brillia(ブリリア)」ブランドで知られるマンション事業や東京の八重洲・日本橋・京橋エリアなどの都市開発を手がける同社は、2023年に開園した都立公園で初めてPark-PFIを活用したプロジェクト「都立明治公園」を手がけています。マンションでも公園でも、大切なことは地域の人々に心から愛され、長続きする関係を築くこと。サステナブルなまちづくりにとりくむ東京建物の社員2人にじっくり話を聞きました。(編集長・福井洋平)
SDGs(持続可能な開発目標)関連の業務に携わっている若手・中堅社員に直撃インタビューする「SDGsに貢献する仕事」。第27回はまちづくりを手がける大手デベロッパーの東京建物が登場します。「Brillia(ブリリア)」ブランドで知られるマンション事業や東京の八重洲・日本橋・京橋エリアなどの都市開発を手がける同社は、2023年に開園した都立公園で初めてPark-PFIを活用したプロジェクト「都立明治公園」を手がけています。マンションでも公園でも、大切なことは地域の人々に心から愛され、長続きする関係を築くこと。サステナブルなまちづくりにとりくむ東京建物の社員2人にじっくり話を聞きました。(編集長・福井洋平)【お話をうかがった方のプロフィル】
新規事業開発部 インフラ・PPP推進グループ 黒田敏(くろだ・さとし)さん(写真右)
2012年同志社大学商学部卒、同年東京建物入社。住宅営業部、住宅事業部、2020年グロービス経営大学院にてMBA(経営学修士)を取得し、同年ソリューション推進部インフラ・PPP推進グループを経て2021年に現部署。
サステナビリティ推進部(市場・政策調査部と兼務) 種田安純(たねだ・あすみ)さん(写真左)
2023年早稲田大学法学部卒、同年東京建物入社。2023年に市場・政策調査部に配属、2025年よりサステナビリティ推進部を兼務。



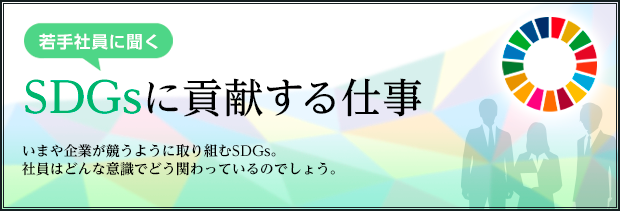
 ■黒田さんと種田さんのお仕事
■黒田さんと種田さんのお仕事 ──種田さんはサステナビリティ推進部と市場・政策調査部を兼務されています。
──種田さんはサステナビリティ推進部と市場・政策調査部を兼務されています。 ■緑化への取り組み
■緑化への取り組み ■明治公園の取り組み
■明治公園の取り組み (写真は都立明治公園内の都市型スパ「TOTOPA」=東京建物提供)
(写真は都立明治公園内の都市型スパ「TOTOPA」=東京建物提供) ■地元との取り組み
■地元との取り組み ■モデルルームの敷居を下げる
■モデルルームの敷居を下げる ■新規事業への挑戦
■新規事業への挑戦 (写真は都立明治公園=東京建物提供)
(写真は都立明治公園=東京建物提供)