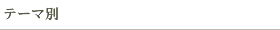■ブルーエコノミープロジェクト
──岡野さんが手がけているブルーエコノミープロジェクトについてお聞きしたいのですが、まず「ブルーエコノミー」とは何ですか。
岡野 漁業や海運業、海洋資源開発といった海洋産業と、海の生態系を含んだ経済圏のことをブルーエコノミーといいます。海の環境を守りながら海洋産業を発展させ、社会をサステナブルに進化させていく考え方も含んでいます。
当社は2022年10月に「ブルーエコノミープロジェクト」を立ち上げました。自然資本の持続可能性の向上、気候変動への対応というブルーエコノミーの考え方が、中期経営計画で掲げた重大課題のひとつである「地球環境との共生」に資するということで全社横断的なプロジェクトとしました。
──損害保険という業態と地球環境は、どういう関係にあるのでしょうか。
岡野 自然災害が起きたときに損害保険で経済的な補填をしますが、近年は「数十年に一度起こる」といわれる災害が毎年のように起きています。そうなると我々としても適切なリスクを取ったり、補償を提供したりすることが難しくなります。「地球環境との共生」というプロジェクトは、保険という本来の役割と親和性があるのです。
山野辺 自然災害の激甚化を最小化するためには気候変動対策が必要で、そのためには温室効果ガス排出量の削減、脱炭素社会を実現しなければいけません。ブルーエコノミープロジェクトでも、温室効果ガスの削減に資する取り組みに1つ大きなテーマを置いています。
■「海」に注目した理由
──「地球環境」のなかでも、なぜ特に海に着目されたのでしょうか。
岡野 サステナビリティを実現するための非常に有意義なプロジェクトであることに加え、大きな事業機会もあるためです。ある試算ではブルーエコノミー市場は、2030年までに3兆米ドルの市場規模が見込まれています。日本は海に囲まれ、世界第6位のEEZを保有していますので、成長に資する事業機会があると考えました。
山野辺 日本の主力電源をみると天然ガスや原油が果たす役割は非常に大きいのですが、日本が輸入しているガスや石油の大半は海底下にあります。私がいる海洋エネルギー室は、そういった天然ガスや原油を採取、生産するプロジェクトの保険引き受けを手がけています。その開発をしている会社が脱炭素の流れのなかで注目しているのが再生可能エネルギーで、たとえば洋上風力発電や、水素、アンモニアといったカーボンニュートラル実現のための取り組みを加速しているのです。そういったお客さまの取り組みにどういったソリューションを提供しようか考えているときに、会社の経営方針として「ブルーエコノミー」というテーマが降りてきた。トップダウンとボトムアップの流れがちょうどこのテーマで合致し、プロジェクトが大きく前進するきっかけとなりました。
──お客さまは日本の企業に限らずということですね。
山野辺 そうですね。我々のチームでは主に日系企業を担当していますが、海外のオイルメジャーや洋上風力発電事業者等、日系企業の事業パートナーとなる非日系企業も担当しています。
──損害保険会社はビジネスのプロジェクトのどの辺から関わるのですか。
山野辺 事業計画の段階からです。洋上風力発電なら、「日本のこの海域で、洋上風力ビジネスを始めようと思っています」という計画の段階から関与し、数年間、伴走支援をしながら取り組みを進めます。
損害保険会社は保険の引き受けだけではなく、リスクマネジメントという大きなくくりで価値を提供することが求められています。これがどこの保険会社も同じかというと、実はそうではなくて、特に我々のチームは海洋エネルギーの領域では国内のマーケットシェア50%を超えています。船舶保険種目ナンバーワンの損保としてお客さまから保険の引き受けだけではなく、リスクマネジメント全体のパートナーとして、うちの会社に声をかけていただくという流れでやってきています。
──ブルーエコノミープロジェクトが、このタイミングでのリリースになったのは、何かステップがあったんでしょうか。
岡野 山野辺が言ったように営業は営業でプロジェクトを進めていたのですが、やはり組織としてプロジェクトを進めていくには営業、本社部門、保険商品の開発は商品部、と全社的に横断した組織のプロジェクト体制が非常に重要になってきます。バラバラだった取り組みをまずは1つにまとめて、全社的に取り組めるような体制をつくり上げようというところでプロジェクトが組成されました。
 SDGs(持続可能な開発目標)関連の業務に携わっている若手・中堅社員に直撃インタビューする「SDGsに貢献する仕事」の第12回は、損害保険大手の三井住友海上火災保険です。「海上」の名にふさわしく、船舶や海上保険に強みを持つ同社。海を中心とする経済圏「ブルーエコノミー」を展開するミッションを掲げています。でも、ブルーエコノミーっていったい何? 損害保険とはどういう関わりが? このインタビューでくわしく説明します。(編集部・福井洋平)
SDGs(持続可能な開発目標)関連の業務に携わっている若手・中堅社員に直撃インタビューする「SDGsに貢献する仕事」の第12回は、損害保険大手の三井住友海上火災保険です。「海上」の名にふさわしく、船舶や海上保険に強みを持つ同社。海を中心とする経済圏「ブルーエコノミー」を展開するミッションを掲げています。でも、ブルーエコノミーっていったい何? 損害保険とはどういう関わりが? このインタビューでくわしく説明します。(編集部・福井洋平)


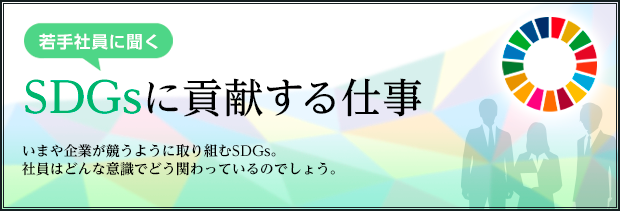
 ■お2人のお仕事
■お2人のお仕事 ■ブルーエコノミープロジェクト
■ブルーエコノミープロジェクト ■「藻場」の再生
■「藻場」の再生 ■ブルーエコノミープロジェクトの進展
■ブルーエコノミープロジェクトの進展