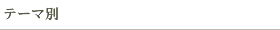■アンダーライティング
──「アンダーライティング」は損保業界の用語ですか。
野中 保険はロンドンのロイズマーケットが起源で、「リスクを引き受けます」と書類の一番下(under)にサインをする(writing)行為をアンダーライティング(underwriting)と呼んでいます。
西山 今は保険を引き受けるために情報を集め、リスクの審査、判断をするという意味でも使っています。
野中 生命保険の場合は個々のリスクより統計がベースですが、損害保険はさまざまなモノが対象なのでリスク審査も個別で全く違います。とくに貨物保険はどんなモノをどう運ぶかでリスクが大きく異なるので、細かくヒアリングします。
──西山さんはどんな貨物を担当しているのですか。
西山 主に養殖中の魚と、輸送中の自動車を担当しています。
──養殖魚と自動車では大違いですね。
西山 どの分野も情報を集め、精査し、リスクを見定めるというアンダーライティングの基礎は同じです。さまざまな分野を見ることでニッチな専門性を身につけつつ、リスクの見極め方をしっかり勉強できると思っています。
■養殖保険
──養殖魚の保険は輸送のリスクを補償するのですね。
野中 養殖をしている間のリスクも含めてお引き受けするパッケージ保険です。実は、養殖は保険の引き受けがすごく難しいビジネスです。養殖の魚が死んだ場合、いろんな原因が考えられます。エサが多すぎたのか、少なすぎたのか、一つのいけすに魚を入れすぎたのか、台風が来たからか、水質が変化したからか……。原因の特定が難しい。さらに温暖化の影響で自然災害が増えたり、今まで起きなかった場所で赤潮が発生したり、リスクが変化しています。未知のリスクを分析・予測して持続可能な保険を設計するのは難しいことなんです。
一方で2018年の漁業法改正で、養殖業への新規参入拡大や、新たな手法・漁場での生産拡大が目指されることになりました。2020年の「養殖業成長産業化総合戦略」では2030年に今の10倍規模の2200億円の輸出を目指す方針が示されるなど、養殖業を成長産業にすることが国の重要な戦略となっています。私が前に担当していた商社でも養殖事業への参画・投資の話が出ていました。お客様や当社にとって追い風の状況です。
──追い風なのに保険がなかったと。
野中 世界的にも同じで、養殖リスクの保険引き受けは一般的ではありません。一説では保険がかけられている割合は15%もないそうです。日本には公的な養殖共済「ぎょさい」がありますが、大規模な養殖や最近増えている陸上養殖を行うお客様が加入できないケースもあります。リスクが低いからお客様側で保険に加入しないのではなく、リスクが高くて保険会社が保険を提供できず、養殖事業者が大きなリスクを背負って事業に挑戦している状態だと分かりました。
今までなら保険の設計が難しい場合はお断りせざるを得なかったのですが、今回は「どうやったら保険をお引き受けできるか?」を考えました。一つの解は、新たな技術開発で組織の枠組みを越えて広く知識・技術を結集する「オープンイノベーション」です。養殖で社会課題解決にチャレンジしているウミトロンというベンチャー企業と話す中で、ウミトロンが持つ海洋データと、当社のアンダーライティングのノウハウにシナジーが見いだせることが分かり業務提携に至りました。提携のねらいは、海洋データを活用して養殖保険を当たり前のものにすることです。
──ウミトロンは何をしている会社ですか。
野中 海の持続可能な開発と魚の安全・安定供給を目指している企業です。IoT機器や衛星データを活用して、給餌の最適化や魚群行動の解析、海洋データ提供などのサービスをしています。養殖業は毎日エサやりがあり、魚の管理も大変で過酷な労働環境でもあります。自動給餌器を使って毎日いけすの場所まで船を出さずに済むようにしたり、カメラを設置して魚の動きや異変、成長スピードを遠隔で見られるようにしたりしています。
──ウミトロンとのコラボで新たな保険ができたのですね。
野中 従来はお客様からの情報だけで行っていたリスク判断を、水位、水温、波の高さ、海中の酸素量、クロロフィル(葉緑素)の値など、ウミトロンが取得する海の状況に関するデータを見て、従来とは別の角度でアンダーライティングができるように検証を進めています。
また、既存の共済制度では対象外の陸上養殖のリスクについても、国内初の専用保険を開発しました。
(写真は、AI・IoT技術を使ったスマート給餌機「ウミトロンセル」を活用した真鯛の養殖場=ウミトロン提供)
 SDGs(持続可能な開発目標)関連の業務に携わっている若手・中堅社員に直撃インタビューする新企画「SDGsに貢献する仕事」の第3回は、損害保険国内No.1の東京海上日動です。損保はSDGsにどう関わるのでしょう。新しい事業にはリスクがつきものですから、再生可能エネルギーをはじめSDGs関連の新たなビジネスには保険が不可欠なのだそうです。「サステナビリティは経営理念そのもの」という同社で新たな保険に日々取り組んでいる社員のお話です。(編集長・木之本敬介)
SDGs(持続可能な開発目標)関連の業務に携わっている若手・中堅社員に直撃インタビューする新企画「SDGsに貢献する仕事」の第3回は、損害保険国内No.1の東京海上日動です。損保はSDGsにどう関わるのでしょう。新しい事業にはリスクがつきものですから、再生可能エネルギーをはじめSDGs関連の新たなビジネスには保険が不可欠なのだそうです。「サステナビリティは経営理念そのもの」という同社で新たな保険に日々取り組んでいる社員のお話です。(編集長・木之本敬介)


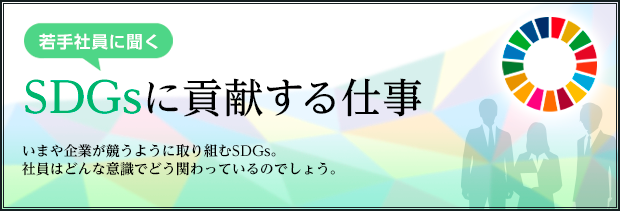
 ■自己紹介
■自己紹介 ■アンダーライティング
■アンダーライティング ■SDGsに貢献
■SDGsに貢献