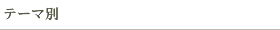■積水ハウスマッチングプログラム
──二つ目の「積水ハウスマッチングプログラム」について教えてください。
「積水ハウスマッチングプログラム」は社員と会社の共同寄付制度で、一口100円から寄付でき、社員と同額を会社が寄付します。寄付先は社会課題の解決に取り組む、SDGsに沿った活動をしている団体で、中でも「子ども」と「環境」に関する活動をしている団体が対象です。2006年に始めて、加入社員は8000人弱、全体の約30%で、これまでNPOを中心に累計496団体に5億円を超える寄付をしてきました。
私が担当しているのは、オンラインの社内セミナー「つながりカフェ」です。企画とMCをしています。毎月1回40分ほど、ゲストを招いて講演してもらいます。「積水ハウスマッチングプログラム」という社会貢献活動を、社員により身近に感じてもらうために始めました。ゲストは、プログラムで助成している団体です。全社員に「今月はこのテーマに関連する団体をお呼びしています。ご希望の方は是非」とお知らせして参加を呼びかけています。
──なぜ社員と会社の共同寄付なんですか。
社員の主体性を大事にするためです。会社が寄付するのは簡単ですが、それだと社員が認知しません。毎月100円でも自分の給料から寄付することで社会貢献に関わっている意識を持つことが大事だと思います。
各地域の団体という点もポイントです。社員に、自分が仕事をしている地域に根ざした活動をしている団体を知ってもらい、地元の地域に目を向けてほしい。地域課題に取り組んでいる団体と連携を深めれば、積水ハウスが地域に貢献できますし、気づくことで社員や会社の成長にもつながります。社会貢献活動と経済活動の両輪が回ることになります。
支援している団体は喜んでくれますし、社員も社会貢献ができ、地元とつながりができてよかったと言ってくれます。投資家からはこうした取り組みを開示するように言われます。社会貢献活動に対する会社の取り組みは関心が高いようです。
──「子ども」と「環境」ということですが、具体的にはどんな活動ですか。
たとえばここ数年、コロナ禍で子どもたちが外で遊べなかったので、自然の中で遊べる環境を整備する活動に寄付しました。あるいはDV(家庭内暴力)や学校でいじめを受けて自分の居場所がないと感じる子どもたちの居場所づくりをしている団体や、シェルター、子ども食堂も支援しました。「環境」では、震災災害のレスキュー、小学生向けのビオトープ(小さな生態系のある場所)づくり、カンボジアや東ティモールで自然保護の活動をしている団体にも支援しています。
──団体はどうやって選ぶのですか。
参加している社員(会員)による投票と、会員から代表して選任されたメンバーで構成された「積水ハウスマッチングプログラムの会」で決議されます。また、団体がエントリーするためには、社員の推薦を必須としています。地域に根ざした活動をし、その地域の事業所やグループ会社が連携しているほどポイントが高くなります。
──「つながりカフェ」にはどんなゲストを?
アトピーのお子さんを支援している団体に、被災地への支援物資にアレルギー除去食がなく、食べて発作を起こすことがあるという話をしてもらいました。環境の関係では、阪神淡路大震災27年目の当日にレスキューの団体を、東日本大震災の3月11日には別の団体を招き、当時の被災地の様子を聞きました。改めて生の声を聞き、自分たちに何ができるか考えるのも重要です。
地域の社会課題ってこんなにあるんだと驚きます。目に見えない課題に取り組んでいる方、報酬に関係なく信念に基づいて活動されている方が大勢います。
──反響はどうですか。
「この時間を楽しみにしています」という固定ファンもいれば、「このテーマだから聞きに来ました」という社員もいます。1年で12回開催し、計1200人が参加してくれました。ただ、まだ存在を知らない社員が大多数です。まずは認知度を上げるのが課題ですが、最終的にはマッチングプログラムの会員数を増やしていきたいです。
(
後編に続く)
(写真・MIKIKO)
 SDGs(持続可能な開発目標)関連の業務に携わっている若手・中堅社員に直撃インタビューする新企画「SDGsに貢献する仕事」。第2回は、太陽光発電と高断熱を組み合わせてエネルギー消費を実質ゼロにする「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH=ゼッチ)」で業界をリードする積水ハウスです。SDGsとも深く関わるのが、環境や社会問題に配慮するESG(環境・社会・企業統治)。現場の営業を経験した後、若くしてESG経営推進の部門で働いている社員にお話をうかがってきました。(編集長・木之本敬介)
SDGs(持続可能な開発目標)関連の業務に携わっている若手・中堅社員に直撃インタビューする新企画「SDGsに貢献する仕事」。第2回は、太陽光発電と高断熱を組み合わせてエネルギー消費を実質ゼロにする「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH=ゼッチ)」で業界をリードする積水ハウスです。SDGsとも深く関わるのが、環境や社会問題に配慮するESG(環境・社会・企業統治)。現場の営業を経験した後、若くしてESG経営推進の部門で働いている社員にお話をうかがってきました。(編集長・木之本敬介)


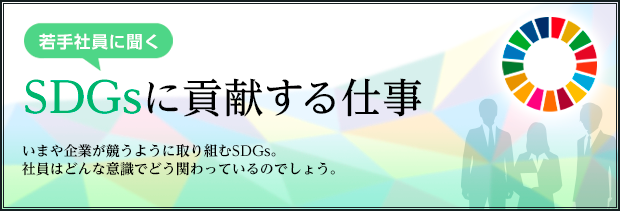
 ■自己紹介
■自己紹介 ■ESGを自分事にする表彰制度
■ESGを自分事にする表彰制度 ■積水ハウスマッチングプログラム
■積水ハウスマッチングプログラム