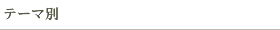■継続的な取り組み
──「1チョコ for 1スマイル」の取り組みは、同種の取り組みと比べてどういった特色があると思いますか。
先ほどお話ししたように、2008年というSDGsが提唱される前からはじまり、そこから16年継続しているということが特徴だと思います。この16年間で約3億2000万円を寄付して6カ国182村・集落、90の学校、約2万人の子どもたちを支援し、児童労働から解放された子どもは622人と、実際に数字として活動の成果があらわれています。
私が昨年の11月に訪問したカカオ産地の一つであるガーナのカカオ農家は構造的に、3階層に分かれています。まずは土地持ちの農家、そしてシェアクロッパーといって売り上げの半分は土地持ちの農家に取られて残り半分しか自分の取り分のない農家、最後はケアテイカーといって売り上げの3分の1しか取り分がない農家です。シェアクロッパーやケアテイカーといった階層の低い人たちは収入が低く、児童労働のリスクも高くなります。そこに直接的に支援をしているのが、我々の強みです。
また、もう1つ特徴的なことは我々が実際に使っているカカオ豆の産地だけではなく、将来的に調達する可能性のある産地も支援していることです。いま取引している産地だけに限定せず、カカオ産地全体の未来を見据えて支援しています。
──継続的な支援ができる理由は何ですか。
森永製菓はパーパスに「森永製菓グループは世代を超えて愛されるすこやかな食を創造し続け、世界の人々の笑顔を未来につなぎます」と掲げています。「笑顔を未来につなぐ」は、チョコレートを食べる人とカカオ産地の子どもたちの笑顔を未来につなぐということにもつながります。ほかにも森永製菓は企業理念の中で「持続可能な社会に貢献」「利他の精神」を挙げており、人との繋がりを大切にする、企業と社会の課題を一致させることなどを大事にしています。だからこそ、今もなお支援が続いているのだと思います。
──「利他の精神」は、創業以来の精神と聞いています。
はい、森永製菓創業者の森永太一郎が掲げたのが「利他の精神」です。太一郎は「日本の人々においしく、栄養価の高いお菓子を食べてもらいたい」という想いを持って創業し、西洋菓子を日本で広めました。関東大震災のときに被災者にお菓子を配ったり、従業員のために日本で初めて8時間労働制を導入したりしました。
ちなみに、森永製菓はパイオニアスピリットも創業以来の精神として受け継いでいます。国産初のペニシリンを開発したのも森永製菓です。1998年には、日本の菓子業界で初めてISO14001(環境マネジメントシステム国際規格)を取得しました。「inゼリー」のようなパウチゼリー飲料も森永製菓が市場をつくりました。ほかにも女性活躍の指標となる「プラチナくるみん」を取得したり、ダイバーシティ担当も2012年から設置したりしています。チョコレートといえば原料であるカカオ豆からのチョコレートの一貫製造をしたのも国内では当社が初めてです。先駆的な取り組みを許容する風土が、森永製菓には息づいているのです。
 SDGs(持続可能な開発目標)関連の業務に携わっている若手・中堅社員に直撃インタビューする「SDGsに貢献する仕事」。第21回は、お菓子をはじめとする食品メーカーで、さらにウェルネスカンパニーへの生まれ変わりをめざす森永製菓が登場します。森永製菓は2008年から、年間を通して⾏う寄付に加えて、特別期間では森永チョコレートなどの対象商品1個につき1円を寄付する「1チョコ for 1スマイル」という取り組みを16年にわたり続けています。情報発信を担う広報担当者として、2023年に主要産地のガーナを訪問した渡辺啓太さんにお話を聞きました。(編集長・福井洋平)
SDGs(持続可能な開発目標)関連の業務に携わっている若手・中堅社員に直撃インタビューする「SDGsに貢献する仕事」。第21回は、お菓子をはじめとする食品メーカーで、さらにウェルネスカンパニーへの生まれ変わりをめざす森永製菓が登場します。森永製菓は2008年から、年間を通して⾏う寄付に加えて、特別期間では森永チョコレートなどの対象商品1個につき1円を寄付する「1チョコ for 1スマイル」という取り組みを16年にわたり続けています。情報発信を担う広報担当者として、2023年に主要産地のガーナを訪問した渡辺啓太さんにお話を聞きました。(編集長・福井洋平)


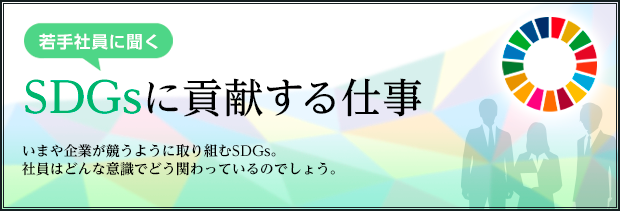
 ■「1チョコ for 1スマイル」について
■「1チョコ for 1スマイル」について ──活動支援パートナーが現地とつないでくれるのですか。
──活動支援パートナーが現地とつないでくれるのですか。 ■継続的な取り組み
■継続的な取り組み ■取り組みが社内に浸透するまで
■取り組みが社内に浸透するまで (写真は国内でのイベントの様子)
(写真は国内でのイベントの様子) ──ガーナに行かれて、一番印象深かったことは何ですか。
──ガーナに行かれて、一番印象深かったことは何ですか。 ■ガーナの児童労働
■ガーナの児童労働