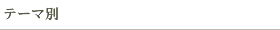──2020年から取り組まれている「トレイマットデザインコンテスト」について教えてください。
あるテーマに沿って大学で講義を行い、それをマクドナルドに来店するお客様にも理解していただけるよう、店で使うトレイにしいているトレイマットを大学生にデザインしてもらうという取り組みです。今まで、生物多様性、食の循環、気候変動への取り組みについてのテーマを取り上げてきました。2020年にスタートし、地方自治体、大学、マクドナルドでコラボレーションして、今年は横浜市と京都市の2カ所で展開しています。
──コンテスト開始のきっかけは。
日本マクドナルドは食を提供する企業としていつまでもおいしいお食事を提供したいと願い、可能な限りサステナブルな食材、資材を調達しています。
SDGsの推進には「学んで、知って、伝える」という流れが理想的です。そこで学生を巻き込んで、SDGsにちなんだテーマで「学んで、知って、伝える」という流れを1つのプロジェクトとして体現できないかと考えました。さらに趣旨に賛同いただける自治体ともつながり、産官学連携で社会全体を巻き込んでいこう、と発展していきました。
──学生をパートナーとして選んだのはなぜですか。
学生はこれからの日本を背負っていく世代ですし、SNSの普及によって発信力も持っています。彼らは「学んで、知って、伝える」という流れを一番体現してくれます。学生からも夏期休暇などになると、SDGsに関する問い合わせが増えるのです。SDGsについて積極的に学びたがっている学生に対して、場を提供したいという思いもありました。
──自治体を巻き込むというのは、どういう意図ですか。
デザインコンテストは「きれいなデザインを描いて終わり」というわけではありません。SDGsにおいては、その重要性について学び、伝えて、伝えた先の人々に実際の行動を起こしてもらうことが重要なポイントです。その行動を起こすのは、一般市民の人々です。自治体も巻き込むことで、市民の行動変容にまで影響を出せると思いました。
──トレイマットに注目されたのは、なぜですか。
トレイマットは店内で食事をされる全員に配られ、多くの方の目に触れます。学生にとっても自分がデザインしたものが皆様の目に触れる場所で使われるのは、モチベーションに繋がると考えました。
──実現にはどういったハードルがありましたか。
日本マクドナルドのクリエイティブには非常に厳しいガイドラインがあるため、普通の学生が絵を描いてもなかなかOKは出ません。デザインを日本マクドナルドが求めるレベルにまで上げる、それを学生に学んでもらうのも大切なポイントでした。自治体に関しても、「学んで、伝えて、行動する」までつなげていただける発信力のある自治体さんと組みたいと考えています。三者がWin-Winでやらないと意味がないのです。
──日本マクドナルド側から「こういうレギュレーションで」「こういう発想で」と学生に説明するのですか。
そうですね。大学の授業のコマを使い、プロジェクトの冒頭でテーマに沿った日本マクドナルドの取り組みを伝え、広告代理店からデザインの進め方や作成する上でのTipsを授業形式で学生に講義しました。地方自治体と、サステナブルラベルの認証団体にも授業をしてもらいます。
(写真・トレイマットコンテストの最優秀作品=日本マクドナルド提供)
 SDGs(持続可能な開発目標)関連の業務に携わっている若手・中堅社員に直撃インタビューする「SDGsに貢献する仕事」の第13回は、ハンバーガー・レストラン・チェーン大手の日本マクドナルドです。アメリカでの創業時から、「社会に貢献する(Giving back to the communities)」という思いでビジネスに取り組んでいるという同社。食品ロスを減らしたりプラスチック削減に取り組んだりしているなかで、より人々の行動を変える目的ではじめたのが「トレイマットコンテスト」。大学や地方自治体とも協力し、参加者が年々増えてきています。中核で活躍する若手社員に話を聞きました(肩書は取材当時)。(編集長・福井洋平)
SDGs(持続可能な開発目標)関連の業務に携わっている若手・中堅社員に直撃インタビューする「SDGsに貢献する仕事」の第13回は、ハンバーガー・レストラン・チェーン大手の日本マクドナルドです。アメリカでの創業時から、「社会に貢献する(Giving back to the communities)」という思いでビジネスに取り組んでいるという同社。食品ロスを減らしたりプラスチック削減に取り組んだりしているなかで、より人々の行動を変える目的ではじめたのが「トレイマットコンテスト」。大学や地方自治体とも協力し、参加者が年々増えてきています。中核で活躍する若手社員に話を聞きました(肩書は取材当時)。(編集長・福井洋平)


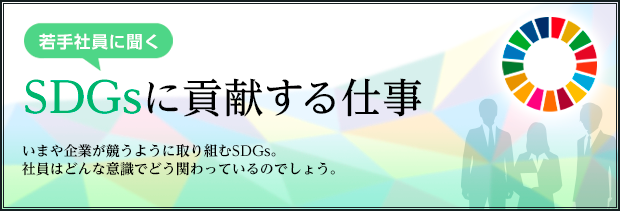
 ■マクドナルドとSDGs
■マクドナルドとSDGs ──2020年から取り組まれている「トレイマットデザインコンテスト」について教えてください。
──2020年から取り組まれている「トレイマットデザインコンテスト」について教えてください。 ■企業、自治体、大学の調整
■企業、自治体、大学の調整 ■赤松さんの経歴
■赤松さんの経歴 ■現在の仕事
■現在の仕事