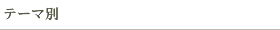■自己紹介
──自己紹介をお願いします。
田上さん 入社14年目で、2022年10月に管理職に就きました。高岸さんら営業メンバーと現場の工事やエネルギー診断をする技術担当メンバー、計約20人が在籍するソリューション営業グループの課長をしています。もう一つ、営業の進捗管理や事業拡大に向けて市場の情報収集・発信をする事業推進グループの仕事も兼任しています。
高岸さん 入社3年目で、法人のお客様に空調機のメンテナンスを提案する仕事をしています。
■SDGsへの取り組み
──ダイキン工業がSDGsに取り組む姿勢を教えてください。
田上 主力事業の空調は、電気・水道といったインフラと同じぐらい生活に浸透し、なくてはならないものになっています。熱中症の予防や空気の質の改善を通してみなさんの健康に役立っていると思います。赤道直下など気温が高くて人が住めなかったところや、快適には暮らせなかったところに空調機が普及することで経済発展にも貢献できています。
ただ、世界的に空調の需要が2050年には今の3倍に膨れ上がると予想されています。電力需要がその分増えるという課題にも取り組まなければいけません。コロナ対策で空気の質が注目され、安心で安全な空気の需要が増えています。今は安心、快適に過ごせる空気と環境を提供できていますが、今後も長く提供し続けられるよう事業を継続することが大切です。温暖化への影響を限りなく減らしていくのがダイキンの社会的な使命だと思っています。
──「環境ビジョン2050」を掲げていますね。
田上 2050年に温室効果ガス排出実質ゼロを目指す目標です。空調の世界トップメーカーなので、リーダーとしての使命感、責任感も非常に感じています。全世界の総消費電力のうち1割がエアコンといわれていて、省エネ性の高いものを世の中に送り出すことが、電力不足、カーボンニュートラルという意味でも大事です。環境貢献を事業のかたわらでするのではなく、事業そのものに直結している点が他のビジネスとは違うところで、やりがいも大きいですね。
──具体的な取り組みを教えてください。
田上 当社は、独自の環境技術を多く持っていて、それらをグローバルに普及させることで、世界の二酸化炭素(CO₂)排出量の削減に貢献したいと考えています。
最近ヨーロッパでは、日本の一般的なエアコンにも用いられているヒートポンプ技術を使った暖房機の需要が高まっています。これまではガスやオイルを使う燃焼式暖房が主流でしたが、環境意識の高まりや近年の情勢不安による資源価格の高騰などにより、少ない電力で暖めることができるヒートポンプが注目されています。
温暖化への影響が少ない冷媒(フロンガス)の普及も重要です。現在のエアコンに使われる冷媒には、CO₂の数百倍から数千倍の温室効果があります。当社は、温暖化に与える影響が従来の3分の1以下の冷媒R32を採用した空調機を普及させることでCO₂排出量の削減に貢献しています。R32の関連特許を全世界に無償で開放するようなこともしています。
──特許を開放したらもうからないのでは?
田上 特許を開放するなんて普通は考えられないと思いますが、無償で誰でも使えるようにすると、R32を採用した製品が市場に多く出回り、その結果、当社の製品も受け入れてもらいやすい市場を作れるという考えです。技術を自社だけで囲い込むのではなく、他の空調メーカーにも広く使ってもらえるように活動し、空調業界全体の脱炭素化に取り組んでいます。
冷媒は大気放出されると温暖化が進んでしまいますので、まず漏れないようにしたり、空調機を廃棄するときはきちんと回収したりすることも大切です。世の中で循環している冷媒をしっかり把握して漏れないようにし、回収・再生率を高めていくためのプラットフォームの実証実験を進めているところです。
──「空気を“はぐくむ森”プロジェクト」もあるそうですね。
田上 「森は地球のエアコン」をキャッチフレーズに取り組んでいる森林保全プロジェクトです。日本、インドネシア、ブラジルなど世界7カ所で国際NGOと協力しながら進めている活動です。世界自然遺産に登録されている知床では、植樹だけでなく、その価値を次の世代に伝えるために子どもや学生の環境教育のサポートもしています。
社員もボランティアとして参加しています。参加した人からは「環境問題をより自分事として考えるきっかけになった」「ダイキンとして取り組んでいることが実感できた」と聞きました。
 SDGs(持続可能な開発目標)関連の業務に携わっている若手・中堅社員に直撃インタビューする「SDGsに貢献する仕事」の第5回は、世界ナンバーワンの空調メーカー・ダイキン工業です。地球温暖化で空調は世界中でなくてはならないインフラとなりましたが、電力の消費量も増える一方。カギを握るのは省エネです。業界のリーダーにとって、安心・安全な空気の提供と環境への貢献は「事業そのもの」であり社会的使命だと言います。若手社員もSDGsへの貢献を日々実感していました。(編集長・木之本敬介)
SDGs(持続可能な開発目標)関連の業務に携わっている若手・中堅社員に直撃インタビューする「SDGsに貢献する仕事」の第5回は、世界ナンバーワンの空調メーカー・ダイキン工業です。地球温暖化で空調は世界中でなくてはならないインフラとなりましたが、電力の消費量も増える一方。カギを握るのは省エネです。業界のリーダーにとって、安心・安全な空気の提供と環境への貢献は「事業そのもの」であり社会的使命だと言います。若手社員もSDGsへの貢献を日々実感していました。(編集長・木之本敬介)


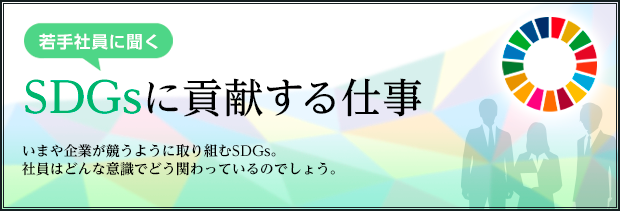
 ■自己紹介
■自己紹介 ■高岸さんの仕事
■高岸さんの仕事 ■営業の仕事
■営業の仕事