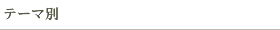■加藤さんの仕事
──これまでの仕事でのSDGsとの関わりについて教えてください。
1年目は「製品の勉強しなければ」と目の前のことに必死で、正直「SDGsって?」くらいの気持ちでしたが、いま振り返ってみるとSDGsに携る仕事ができていたのだと思います。
大手の食品メーカーはSDGsにとても強い関心を持っています。1年目に担当した菓子メーカーには「健康」に関わる研究部署があり、先輩社員のフォローを受けながら私はその部署だけを担当しました。先方としてもチャレンジングなテーマだったので「新入社員でもぜひ意見を」と言ってくれました。
──しっかり勉強しないと営業できませんね。
私の場合、最初の半年くらいは先輩の商談について行き、先輩の説明を聞いて「へえー、そうなんだ」と。帰ってから自分で調べて、「あっ、本当だ!」「そういう意味だったんだ!」というのを繰り返していました。半年後にようやく「ひとりで行ってみようか」と言われ、半年間詰め込んだことをお客様に一生懸命説明したら、思わぬ質問を受けて「もう1回勉強してきます!」ということもありました。
当時所属していた課では飛び込み営業はあまりなく、ほとんどはもとから取引があるお客様が相手でした。アポで苦労することはありませんが、新しい提案を持っていく必要があるので準備期間がいります。開発や生産部門の先輩は勉強会も開いてくれました。開発の人に電話すると何でもすぐ教えてくれるので、1年目は嫌がられるくらい電話しましたね(笑)。勉強する時間は会社から与えられていました。
──営業にとってSDGsは売り込みの武器ですか、それとも説明を求められるから勉強するのですか。
どちらもあります。SDGsは日々の業務では見えにくいこともあり、お客様の立場によって反応が違うことがあります。たとえば、お客様の社長との面談では、「(SDGsに関わる)こういう問題があると聞きましたが、御社はどんな取り組みをされていますか?」と聞かれ、説明をすることがあります。現場担当者間では日々の業務や課題のやり取りが多いのですが、「上層部から(SDGs関連の/プラントベースフードの)話をきいたけど」と相談され、「弊社ではこういう取り組みしていますので、御社のこの製品とマッチすると思います」と提案したこともあります。
──健康担当の後は?
2~3年目は大阪営業部の外食・カフェチェーンとパンメーカーを担当しました。製菓・製パンは約20社を持ちました。しかもチョコも大豆もパーム油も、すべての製品をひとりで売らなければなりません。種類が多いので大変でした。同じ油でもパンに使う場合と揚げ油に使う場合では説明の仕方が変わります。
──菓子メーカーとの違いはありましたか。
当時はSDGsや大豆ミートという言葉が一般消費者に広まっていなかったため、丁寧な提案が必要でした。弊社はBtoB(企業間取引)の会社ですが、2019年から2年間限定で大阪の百貨店に「UPGRADE Plant based kitchen」というお店を出店し、一般消費者とのコミュニケーション、認知を上げる取り組みをしたことがあります。そこで得た情報を外食に持っていって「こういう形にすると売れました」「このPRで女性客がたくさん買ってくれました」とフィードバックしたのです。そのようなやりとりを続けながら、コロナ前ごろに大豆ミートに興味を持ってもらえるようになりました。
──業種によって取り組み姿勢が違うんですね。
たとえば外食産業では店舗で使いやすく、そのまますぐに使える製品が求められます。メーカーのように自社設備をもっていて加工できるとは限らず、店舗内でできる作業も限られているからです。そのため、同じ営業でも、メーカーと外食産業では加工度が違う製品を販売することになります。SDGsに関しても説明の仕方を変えます。営業も一人ひとりが「どうしたらお客様に提案が響くのだろう」「どうしたら弊社の想いが伝わるのだろう」と考えなくてはいけません。
ちなみに業界によってスピード感も全然違って、外食は圧倒的に採用までが速いです。たとえば、メーカーは1~2年後の製品の話をしますが、外食は3カ月後の話です。メーカーでは製品開発に1年かかることも珍しくないですが、外食産業ではたった1カ月で採用を決めてしまう会社もありました。
(写真は、加藤さんが販売している主な製品)
 SDGs(持続可能な開発目標)関連の業務に携わっている若手・中堅社員に直撃インタビューする新企画「SDGsに貢献する仕事」の第4回は、食品素材メーカー・不二製油です。パーム油やカカオなど人権や環境問題に直結する素材を大量に扱っているため、サステナブルな対応をしないと事業が続けられないとか。事業そのものがSDGsなんですね。ブームの「大豆ミート」の開発にも60年以上前から取り組んでいます。(編集長・木之本敬介)
SDGs(持続可能な開発目標)関連の業務に携わっている若手・中堅社員に直撃インタビューする新企画「SDGsに貢献する仕事」の第4回は、食品素材メーカー・不二製油です。パーム油やカカオなど人権や環境問題に直結する素材を大量に扱っているため、サステナブルな対応をしないと事業が続けられないとか。事業そのものがSDGsなんですね。ブームの「大豆ミート」の開発にも60年以上前から取り組んでいます。(編集長・木之本敬介)


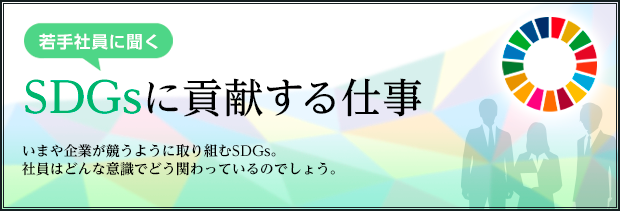
 ■不二製油のSDGs
■不二製油のSDGs ■加藤さんの仕事
■加藤さんの仕事 ■東京へ
■東京へ