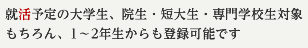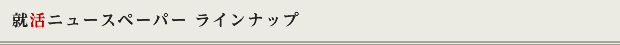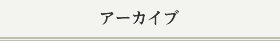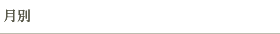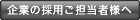WBCもネットフリックスが独占配信
 いまや、ヒットコンテンツの発信源となっている動画配信サービス「Netflix」(ネットフリックス、ネトフリ)。「サンクチュアリ」や「地面師たち」など、ネトフリだけで見られるドラマが次々ヒットしたことは記憶に新しいと思います。前回は大谷翔平らの活躍で劇的な優勝を果たしたWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)も、来年開催についてはネトフリが独占配信をすることになり、話題を呼びました。傘下に様々なメディアをかかえるワーナー・ブラザース・ディスカバリー(WBD)の一部事業の買収に乗り出すなどメディア再編の中心に出てきたネトフリは、どのようにしていまの地位を築いたのか。今後、日本の動画配信ビジネスはどうなっていくのか。メディア関連に興味のある就活生もそうでない人も、朝日新聞の記事をもとにして知識を深めてみましょう。(編集部・福井洋平)
いまや、ヒットコンテンツの発信源となっている動画配信サービス「Netflix」(ネットフリックス、ネトフリ)。「サンクチュアリ」や「地面師たち」など、ネトフリだけで見られるドラマが次々ヒットしたことは記憶に新しいと思います。前回は大谷翔平らの活躍で劇的な優勝を果たしたWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)も、来年開催についてはネトフリが独占配信をすることになり、話題を呼びました。傘下に様々なメディアをかかえるワーナー・ブラザース・ディスカバリー(WBD)の一部事業の買収に乗り出すなどメディア再編の中心に出てきたネトフリは、どのようにしていまの地位を築いたのか。今後、日本の動画配信ビジネスはどうなっていくのか。メディア関連に興味のある就活生もそうでない人も、朝日新聞の記事をもとにして知識を深めてみましょう。(編集部・福井洋平)
(写真・ネットフリックスの日本上陸から2025年で10年。10周年を記念したセブン―イレブン、イトーヨーカドーとコラボ商品も出した=2025年10月27日/写真は朝日新聞社)
もとはDVDの郵送レンタル業者から発展
 ネットフリックスとはそもそも何なのか、歴史を振り返ってみます。もともとは1997年、創業者のリード・ヘイスティングス氏とマーク・ランドルフ氏が、DVDレンタルを郵送で行うビジネスを思いついたことからネトフリはスタートしました。翌年に世界初のDVDレンタル・販売サイトとしてNetflix.comが創設され、1999年には好きな作品を好きなだけレンタルできる定額制サービス、いわゆるサブスクリプション(サブスク)を導入しました。2007年には、映画やテレビ番組を即時視聴できるストリーミング配信サービスを開始。インターネットが急激に拡大する時代に誕生し、ネットの成長とともにサービス内容を進化させてきたわけです。
ネットフリックスとはそもそも何なのか、歴史を振り返ってみます。もともとは1997年、創業者のリード・ヘイスティングス氏とマーク・ランドルフ氏が、DVDレンタルを郵送で行うビジネスを思いついたことからネトフリはスタートしました。翌年に世界初のDVDレンタル・販売サイトとしてNetflix.comが創設され、1999年には好きな作品を好きなだけレンタルできる定額制サービス、いわゆるサブスクリプション(サブスク)を導入しました。2007年には、映画やテレビ番組を即時視聴できるストリーミング配信サービスを開始。インターネットが急激に拡大する時代に誕生し、ネットの成長とともにサービス内容を進化させてきたわけです。
ネットフリックスはいまや日本でもコンテンツ発信の中心となっていますが、その鍵になったのが、テレビのリモコンにつけた「NetFlix」ボタンです。いまではテレビのリモコンに動画配信サービスのボタンが並んでいるのはあたりまえの風景になりましたが、このボタンはネトフリの試みが初めてとされています。朝日新聞デジタル版の連載記事「NetFlix『黒船』の10年」をもとに、経緯をまとめます。
(写真・ネットフリックス社のロゴ=アメリカ・ロサンゼルス/朝日新聞社)
テレビのリモコンに「Netflix」ボタンを入れる
 「NetFlix」ボタンを実現したのは、日本人初のネトフリ社員とされる下井昌人氏です。2008年、日本でまだネトフリがサービスをはじめるかどうかもわからないころ、下井氏は日本のメーカーがアメリカで販売するテレビにネトフリのソフトウェアを入れてもらおうと売り込みを始めます。ネトフリは配信サービスをはじめたばかりで、テレビですぐネトフリが見られるようになれば、飛躍的に会員を増やせると考えたわけです。当時はまだスマートフォンが本格的に普及するまえで、動画の視聴の中心はテレビでした。ソフトウェアの導入に成功すると、次にねらったのが「NetFlix」ボタンです。狭いリモコンの中に、「NetFlix」ボタンを入れてもらうには苦労したそうですが、このボタンはネトフリ会員の増加に大きく寄与しました。
「NetFlix」ボタンを実現したのは、日本人初のネトフリ社員とされる下井昌人氏です。2008年、日本でまだネトフリがサービスをはじめるかどうかもわからないころ、下井氏は日本のメーカーがアメリカで販売するテレビにネトフリのソフトウェアを入れてもらおうと売り込みを始めます。ネトフリは配信サービスをはじめたばかりで、テレビですぐネトフリが見られるようになれば、飛躍的に会員を増やせると考えたわけです。当時はまだスマートフォンが本格的に普及するまえで、動画の視聴の中心はテレビでした。ソフトウェアの導入に成功すると、次にねらったのが「NetFlix」ボタンです。狭いリモコンの中に、「NetFlix」ボタンを入れてもらうには苦労したそうですが、このボタンはネトフリ会員の増加に大きく寄与しました。
ネトフリは2015年に日本でのサービスを開始します。その前年、下井氏はさらに大きな仕掛けを試みます。ネトフリのサービスが始まる前の段階で、「NetFlix」ボタンを日本のテレビのリモコンに搭載するよう画策したのです。
サービス開始前にボタンを載せるのはリスクが高く、メーカー側からは当然、不安視する声があがります。しかし、下井氏には秘策がありました。国も協力に推進していた高画質の「4K」対応テレビです。鳴り物入りでスタートしたもののなかなか普及しなかった4Kですが、ネトフリは4K対応のコンテンツをたくさんもっていたそうです。メーカー側にネトフリのコンテンツを宣伝素材で貸し出すなどして、日本のテレビのリモコンにも「NetFlix」ボタンを導入することに成功。のちの大躍進の土壌をつくりました。
4K放送についてはいま、民放各局が撤退を検討していると報じられ、行き詰まりが顕著になっています。需要が伸びなかった背景には、当時「黒船」とも言われたネトフリの「上陸」などによる動画サービスの急成長があります。スマートフォンなどの小型画面で動画をみることが当たり前になった結果、高画質が求められなくなったのです。当初は4Kを軸に拡大していったネトフリが、4Kを行き詰まりに導いたことには、皮肉めいたものを感じます。
(写真=「Netflix」にワンタッチでつながるテレビリモコンのボタン。当初は同社のボタンだけのリモコンも多かった)
企画から撮影開始まで3年かける
ネットフリックスは、コロナ禍で巣ごもり需要が伸びた2020年ごろからさらに存在感を増していきます。このころ日本のネットフリックスの主力コンテンツは韓国ドラマでした。南北分断を背景にしたラブロマンス「愛の不時着」や、敗れれば死ぬデスゲームに主人公たちが巻き込まれていく「イカゲーム」などは、ご覧になった方も多いのではないでしょうか。
しかし2023年ごろから、日本発のドラマが急激に台頭してきます。たとえば2023年に公開された、相撲未経験の主人公が横綱をめざす「サンクチュアリ―聖域―」は大きな話題となり、相撲人気の向上にも一役かったと言われています。そして2024年には大手住宅メーカーが巻き込まれた実際の事件をもとにした「地面師たち」が大ヒットし、登場人物のセリフ「もう、ええでしょう」はその年の新語・流行語大賞にノミネートされるほどになりました。
コンテンツの魅力を支えているのは豊富な資金力と丁寧な準備です。朝日新聞デジタル版で、「地面師たち」の脚本・監督を担った大根仁氏は「従来の国内メディアとは、全然発想が違うんだなと感じましたね」と語っています。自ら映像化の権利を獲得して脚本を執筆。まずはテレビ局に持ち込むことを考えましたが、大手住宅メーカーがスポンサーにつくテレビ局は無理だろうと判断。不動産事業も行う映画会社からは断られました。そんななか、ネトフリでは即座にGOサインが出たといいます。また、企画を持ち込んでから撮影開始まで約3年かけ、撮影後の仕上げ作業(ポスプロ)にも納得のいく十分な時間をかけられたそうです。テレビドラマは半年程度で企画から撮影まで終わらせるといいますから、準備にかけられる時間が大きく違うことがわかります。これは、豊富な資金力なくしては実現しません。記事では「民放連ドラの10倍はお金をかけている」という業界関係者の声も紹介されています。世界市場を相手に巨大なプラットフォームをつくりあげているネトフリだからこそ、十分な資金をコンテンツづくりに投入することができているわけです。今週の週間ニュースまとめでも紹介したとおり、ネトフリは「ハリー・ポッター」などを持つアメリカのワーナー・ブラザース・ディスカバリー(WBD)の一部事業の買収に乗り出すなど、メディア業界再編の中心的存在にもなりつつあります。
国内の動画配信サービスは共倒れしないか?
 民間調査会社GEMパートナーズの調べでは、国内の定額制配信事業は急成長を続けています。コロナ禍の2020年は3222億円で、前年比で約35%増と躍進。以降も毎年10%を超える伸びが続きます。2024年は前年比4.1%増と伸びが鈍化しますが、いまやコンテンツの視聴方法として、大きな位置を占めています。ネトフリはトップシェア(21.5%)ですが、前年からシェアを少し落としており、Paraviを統合したU—NEXTがシェア17.9%でネトフリを追う展開となっています。以降アマゾンプライムビデオ、DAZN、ディズニープラスと続きます。U-NEXTをのぞいては海外発のプラットフォームがずらっと並んでいる状況です。連載記事「Netflix『黒船』の10年」3回目記事のコメントプラスで、ジャーナリストの松谷創一郎さんは「U-NEXTやABEMA、TVerは存在感がありますが、そこにちゃんと集まっていけるかどうか」として、国内の配信動画サービスの大同団結が必要なのにもかかわらずテレビ局がうまく手を組めていない、と指摘。「このままいけば、プラットフォームはNetflixとAmazonにやられて共倒れは必至です」と語っています。
民間調査会社GEMパートナーズの調べでは、国内の定額制配信事業は急成長を続けています。コロナ禍の2020年は3222億円で、前年比で約35%増と躍進。以降も毎年10%を超える伸びが続きます。2024年は前年比4.1%増と伸びが鈍化しますが、いまやコンテンツの視聴方法として、大きな位置を占めています。ネトフリはトップシェア(21.5%)ですが、前年からシェアを少し落としており、Paraviを統合したU—NEXTがシェア17.9%でネトフリを追う展開となっています。以降アマゾンプライムビデオ、DAZN、ディズニープラスと続きます。U-NEXTをのぞいては海外発のプラットフォームがずらっと並んでいる状況です。連載記事「Netflix『黒船』の10年」3回目記事のコメントプラスで、ジャーナリストの松谷創一郎さんは「U-NEXTやABEMA、TVerは存在感がありますが、そこにちゃんと集まっていけるかどうか」として、国内の配信動画サービスの大同団結が必要なのにもかかわらずテレビ局がうまく手を組めていない、と指摘。「このままいけば、プラットフォームはNetflixとAmazonにやられて共倒れは必至です」と語っています。
また、松谷さんは連載第2回のコメントプラスでは、世界的に見て日本のドラマはほとんどヒットしておらず、「日本ドラマにはまだ韓国ドラマほどのブランド力(信頼)がなく、地上波の記憶から脱却していかなければダメでしょう」ともコメントしています。ネットフリックスの成長は、日本のコンテンツ産業の課題も浮き彫りにしています。今後どのようにビジネスが発展していくのか、新たなプレイヤーは現れるのか、ぜひいろいろニュースをチェックして感度を高めてください。
(写真・動画配信サービスにワンタッチでつながるテレビリモコンのボタン。Netflixが先駆者とされる)
◆朝日新聞デジタル版のベーシック会員(月額980円)になれば毎月50本の記事を読むことができ、スマホでも検索できます。スタンダード会員(月1980円)なら記事数無制限、「MYキーワード」登録で関連記事を見逃しません。大事な記事をとっておくスクラップ機能もあります。お申し込みはこちらから。
 いまや、ヒットコンテンツの発信源となっている動画配信サービス「Netflix」(ネットフリックス、ネトフリ)。「サンクチュアリ」や「地面師たち」など、ネトフリだけで見られるドラマが次々ヒットしたことは記憶に新しいと思います。前回は大谷翔平らの活躍で劇的な優勝を果たしたWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)も、来年開催についてはネトフリが独占配信をすることになり、話題を呼びました。傘下に様々なメディアをかかえるワーナー・ブラザース・ディスカバリー(WBD)の一部事業の買収に乗り出すなどメディア再編の中心に出てきたネトフリは、どのようにしていまの地位を築いたのか。今後、日本の動画配信ビジネスはどうなっていくのか。メディア関連に興味のある就活生もそうでない人も、朝日新聞の記事をもとにして知識を深めてみましょう。(編集部・福井洋平)
いまや、ヒットコンテンツの発信源となっている動画配信サービス「Netflix」(ネットフリックス、ネトフリ)。「サンクチュアリ」や「地面師たち」など、ネトフリだけで見られるドラマが次々ヒットしたことは記憶に新しいと思います。前回は大谷翔平らの活躍で劇的な優勝を果たしたWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)も、来年開催についてはネトフリが独占配信をすることになり、話題を呼びました。傘下に様々なメディアをかかえるワーナー・ブラザース・ディスカバリー(WBD)の一部事業の買収に乗り出すなどメディア再編の中心に出てきたネトフリは、どのようにしていまの地位を築いたのか。今後、日本の動画配信ビジネスはどうなっていくのか。メディア関連に興味のある就活生もそうでない人も、朝日新聞の記事をもとにして知識を深めてみましょう。(編集部・福井洋平)
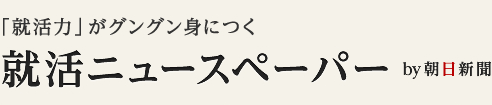

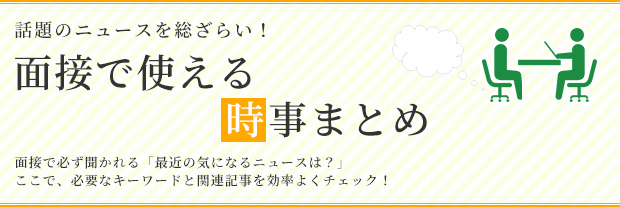
 ネットフリックスとはそもそも何なのか、歴史を振り返ってみます。もともとは1997年、創業者のリード・ヘイスティングス氏とマーク・ランドルフ氏が、DVDレンタルを郵送で行うビジネスを思いついたことからネトフリはスタートしました。翌年に世界初のDVDレンタル・販売サイトとしてNetflix.comが創設され、1999年には好きな作品を好きなだけレンタルできる定額制サービス、いわゆるサブスクリプション(サブスク)を導入しました。2007年には、映画やテレビ番組を即時視聴できるストリーミング配信サービスを開始。インターネットが急激に拡大する時代に誕生し、ネットの成長とともにサービス内容を進化させてきたわけです。
ネットフリックスとはそもそも何なのか、歴史を振り返ってみます。もともとは1997年、創業者のリード・ヘイスティングス氏とマーク・ランドルフ氏が、DVDレンタルを郵送で行うビジネスを思いついたことからネトフリはスタートしました。翌年に世界初のDVDレンタル・販売サイトとしてNetflix.comが創設され、1999年には好きな作品を好きなだけレンタルできる定額制サービス、いわゆるサブスクリプション(サブスク)を導入しました。2007年には、映画やテレビ番組を即時視聴できるストリーミング配信サービスを開始。インターネットが急激に拡大する時代に誕生し、ネットの成長とともにサービス内容を進化させてきたわけです。 「NetFlix」ボタンを実現したのは、日本人初のネトフリ社員とされる下井昌人氏です。2008年、日本でまだネトフリがサービスをはじめるかどうかもわからないころ、下井氏は日本のメーカーがアメリカで販売するテレビにネトフリのソフトウェアを入れてもらおうと売り込みを始めます。ネトフリは配信サービスをはじめたばかりで、テレビですぐネトフリが見られるようになれば、飛躍的に会員を増やせると考えたわけです。当時はまだスマートフォンが本格的に普及するまえで、動画の視聴の中心はテレビでした。ソフトウェアの導入に成功すると、次にねらったのが「NetFlix」ボタンです。狭いリモコンの中に、「NetFlix」ボタンを入れてもらうには苦労したそうですが、このボタンはネトフリ会員の増加に大きく寄与しました。
「NetFlix」ボタンを実現したのは、日本人初のネトフリ社員とされる下井昌人氏です。2008年、日本でまだネトフリがサービスをはじめるかどうかもわからないころ、下井氏は日本のメーカーがアメリカで販売するテレビにネトフリのソフトウェアを入れてもらおうと売り込みを始めます。ネトフリは配信サービスをはじめたばかりで、テレビですぐネトフリが見られるようになれば、飛躍的に会員を増やせると考えたわけです。当時はまだスマートフォンが本格的に普及するまえで、動画の視聴の中心はテレビでした。ソフトウェアの導入に成功すると、次にねらったのが「NetFlix」ボタンです。狭いリモコンの中に、「NetFlix」ボタンを入れてもらうには苦労したそうですが、このボタンはネトフリ会員の増加に大きく寄与しました。 民間調査会社GEMパートナーズの調べでは、国内の定額制配信事業は急成長を続けています。コロナ禍の2020年は3222億円で、前年比で約35%増と躍進。以降も毎年10%を超える伸びが続きます。2024年は前年比4.1%増と伸びが鈍化しますが、いまやコンテンツの視聴方法として、大きな位置を占めています。ネトフリはトップシェア(21.5%)ですが、前年からシェアを少し落としており、Paraviを統合したU—NEXTがシェア17.9%でネトフリを追う展開となっています。以降アマゾンプライムビデオ、DAZN、ディズニープラスと続きます。U-NEXTをのぞいては海外発のプラットフォームがずらっと並んでいる状況です。連載記事「Netflix『黒船』の10年」3回目記事のコメントプラスで、ジャーナリストの松谷創一郎さんは「U-NEXTやABEMA、TVerは存在感がありますが、そこにちゃんと集まっていけるかどうか」として、国内の配信動画サービスの大同団結が必要なのにもかかわらずテレビ局がうまく手を組めていない、と指摘。「このままいけば、プラットフォームはNetflixとAmazonにやられて共倒れは必至です」と語っています。
民間調査会社GEMパートナーズの調べでは、国内の定額制配信事業は急成長を続けています。コロナ禍の2020年は3222億円で、前年比で約35%増と躍進。以降も毎年10%を超える伸びが続きます。2024年は前年比4.1%増と伸びが鈍化しますが、いまやコンテンツの視聴方法として、大きな位置を占めています。ネトフリはトップシェア(21.5%)ですが、前年からシェアを少し落としており、Paraviを統合したU—NEXTがシェア17.9%でネトフリを追う展開となっています。以降アマゾンプライムビデオ、DAZN、ディズニープラスと続きます。U-NEXTをのぞいては海外発のプラットフォームがずらっと並んでいる状況です。連載記事「Netflix『黒船』の10年」3回目記事のコメントプラスで、ジャーナリストの松谷創一郎さんは「U-NEXTやABEMA、TVerは存在感がありますが、そこにちゃんと集まっていけるかどうか」として、国内の配信動画サービスの大同団結が必要なのにもかかわらずテレビ局がうまく手を組めていない、と指摘。「このままいけば、プラットフォームはNetflixとAmazonにやられて共倒れは必至です」と語っています。