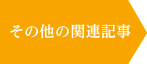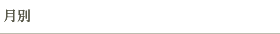反社=「反社会的勢力」
 反社会的勢力=「反社」、という言葉を聞いたことはありますか。たまにニュースでも取り上げられるキーワードですが、いわゆる暴力団(ヤクザ)など、暴力や詐欺などで経済的利益を得ようとする人たちのことを指します。ふつうに生活していればまず接点を持つことはない集団ですが、企業がこういった反社と接点を持ってしまい、大きな経済的、社会的ダメージを受ける事件は絶えず起きています。最近でも、地方信組が反社とつながっていたことで大きな問題が起こっています。最新の動きからこれまでのニュースを振り返り、企業と反社との関係について知識を深めておきましょう。業界選択や研究の際に知っておいて損はないテーマです。(編集部・福井洋平)
反社会的勢力=「反社」、という言葉を聞いたことはありますか。たまにニュースでも取り上げられるキーワードですが、いわゆる暴力団(ヤクザ)など、暴力や詐欺などで経済的利益を得ようとする人たちのことを指します。ふつうに生活していればまず接点を持つことはない集団ですが、企業がこういった反社と接点を持ってしまい、大きな経済的、社会的ダメージを受ける事件は絶えず起きています。最近でも、地方信組が反社とつながっていたことで大きな問題が起こっています。最新の動きからこれまでのニュースを振り返り、企業と反社との関係について知識を深めておきましょう。業界選択や研究の際に知っておいて損はないテーマです。(編集部・福井洋平)
(写真・不正融資や反社会的勢力との関係について謝罪するいわき信用組合の金成茂理事長=2025年10月31日/写真はすべて朝日新聞社)
反社=暴力団だけではない
 政府は2007年に公表した政府方針で、反社を「暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人」と定義しています。一般的には暴力団をイメージされることが多いですが、そのほかにも「総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団」などさまざまな反社集団があります。その種類だけではなく実際の行動に注目して判断することが重要と政府方針にはあります。
政府は2007年に公表した政府方針で、反社を「暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人」と定義しています。一般的には暴力団をイメージされることが多いですが、そのほかにも「総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団」などさまざまな反社集団があります。その種類だけではなく実際の行動に注目して判断することが重要と政府方針にはあります。
「暴力団」はもともとヤクザ、極道といった呼ばれ方をされていました。代表者を頂点にしてピラミッド型の組織を構成し、絶対的な上下関係があるといった特徴があります。かつては山口組や住吉会、稲川会といった巨大な暴力団が勢力を誇っていましたが、1992年に暴力団対策法が施行されてから活動が強く規制されるようになりました。かなり勢力は衰えているものの、いまでも活動が続いていることには注意が必要です。近年では、暴力団の組織に入らないが暴力を背景に犯罪を繰り返すグループ、いわゆる「半グレ」といった存在も広がっています。また、警察庁は近年活動が活発になっている、暴力団の組織に入らずSNSなどを利用しながら詐欺や強盗をはじめ様々な犯罪に関わる集団を「匿名・流動型犯罪グループ(匿流〈トクリュウ〉)」と称して警戒を強めています。トクリュウは今回のテーマからはやや離れる話ですが、こちらはSNSの「闇バイト」募集などで一般の人にもかかわってくる存在ですので、改めてみなさんもしっかり警戒をしてください。
(写真・北海道警に設けられた「匿名・流動型犯罪グループ対策本部」=2024年4月8日)
10億円前後を反社に支払っていた
ふつうの生活をしていれば縁がない存在と思われる「反社」ですが、企業が反社と深い接点を持ってしまい、社会的に大きな非難を浴びるというケースが後をたちません。今年の10月31日には、福島県の「いわき信用組合」(いわき信組)が反社に資金を提供していたとして、金融庁が銀行法に基づく行政処分を出しています。いわき信組は1994年ごろから反社から不当な要求を繰り返され、資金提供に応じていたとみられ、信組の経営陣は、反社との関係がばれないよう金融庁に虚偽の報告を行っていたそうです。
いわき信組は今年5月、約247億円の不正融資が発覚して金融庁から業務改善命令を受けていました。これをめぐり設置された特別調査委員会は10月31日に報告書を公表し、いわき信組が20年以上も反社会的勢力などに資金を支払っていたと指摘。不正融資で捻出して反社に提供したお金は2004年以降だけでも10億円前後にのぼる可能性があるとしています。なぜ、これだけ巨額の資金を、不正をしてまで反社に提供していたのでしょう。
右翼団体との「仲介役」が反社だった
 報告書によると、いわき信組と反社とのかかわりは1994年にスタートします。当時、信組では暴力団関係者と交友がある理事がいたため、その事実をつかんだ右翼団体が信組本部や理事長宅周辺で、信組幹部の素行や暴力団関係者らとのつながりを糾弾する「街宣活動」を繰り返していました。街宣活動とは拡声機を積んだ車(街宣車)などをつかって街中で訴えを展開する活動のことですが、それをこの団体はいわき信組への脅しにつかっていたわけです。
報告書によると、いわき信組と反社とのかかわりは1994年にスタートします。当時、信組では暴力団関係者と交友がある理事がいたため、その事実をつかんだ右翼団体が信組本部や理事長宅周辺で、信組幹部の素行や暴力団関係者らとのつながりを糾弾する「街宣活動」を繰り返していました。街宣活動とは拡声機を積んだ車(街宣車)などをつかって街中で訴えを展開する活動のことですが、それをこの団体はいわき信組への脅しにつかっていたわけです。
ここで、信組の大口融資先だった「仲介役」という人物が登場します。右翼団体との仲介を信組にもちかけ、解決金名目で現金3億円超を要求したそうです。信組は、納税充当金として積み立てられていた資金を取り崩して「仲介役」に要求された金額を支払っています。当時はこういった不正行為をチェックするための監査も行われておらず、不正は見過ごされました。
当時から信組はこの人物について、暴力団関係者と親交があると認識していました。本人も背後に首都圏の暴力団幹部がいることを示唆していたそうです。信組側は、街宣活動の再開を示唆されるたびに数回にわたり数億円を渡していました。調査委員会は2004~2016年の間に、9億4900万円が支払われたと推定しています。
(写真・いわき信用組合の本店=2025年5月29日)
無断で口座つくり融資する手口で資金調達
 この人物に渡す資金は当初、納税充当金を崩して調達していましたが、そのうち知り合いの融資先に必要額より多い融資を行って水増し分を現金で戻してもらうなどして調達するようになりました。さらにいわき信組は、預金している人の了解を得ないままその人の口座を勝手につくり、勝手に融資を行ったことにして、そのお金をこういった反社勢力に渡す「無断借名融資」も繰り返し行うようになります。
この人物に渡す資金は当初、納税充当金を崩して調達していましたが、そのうち知り合いの融資先に必要額より多い融資を行って水増し分を現金で戻してもらうなどして調達するようになりました。さらにいわき信組は、預金している人の了解を得ないままその人の口座を勝手につくり、勝手に融資を行ったことにして、そのお金をこういった反社勢力に渡す「無断借名融資」も繰り返し行うようになります。
朝日新聞では、この「無断借名融資」にかかわったいわき信組元職員に取材をしています。支店長から呼び出されて不正融資を指示された元職員は取材に対し、「上層部に何かもの申すという勇気がなかった」「反発できる組織ではなかった。自分は何か発言してもつぶされるだけ。それならば、黙って従っていくしかないと思った」と語っています。
反社への融資を決めていたのは信組の幹部ですが、こういった形で職員も不正にかかわらされていたわけです。結果、2011年から2014年まで不正融資にかかわってきた元職員が2024年9月にX(旧ツイッター)上で不正の詳細を告発し、1カ月後にいわき信組が「投稿内容はおおむね事実」と発表するに至りました。
(写真・いわき信用組合の不正融資問題に関する調査結果を報告する第三者委員会の弁護士ら=2025年5月30日)
かつては4大証券で30人以上起訴されたことも
いわき信組が反社と関係をもつようになった1990年代、いまから30~40年前は、株主総会で大騒ぎして企業に金銭を要求する反社勢力である「総会屋」がはびこっている時代でした。1997年には、野村証券や日興証券、大和証券など当時の4大証券が同じ総会屋に対して損失補填(ほてん)や融資をしていた事件が発覚し、企業側の30人以上が起訴されています。その後、金融機関では反社勢力との関係が疑われる企業や団体の情報のデータベース化が進み、契約時の書類に反社勢力との取引を拒絶する「暴力団排除条項」の導入も広がりました。それでも、金融機関が暴力団関係者に融資する事件はなくなっていません。報告書では「反社からの脅しに屈して資金提供を行った場合、そのことも弱みとなり、その後も繰り返し、反社による不当要求の餌食となることは容易に想像できるところである」と指摘しています。今回の例でもわかるように、反社は最初は「トラブルを解決してあげる」など味方のふりをして近づいてくるようです。しかしいちど反社と関係を持ってしまうと、そこから関係を切ることは非常に難しくなる、ということです。
全盛期からは勢力が大きく後退しているとはいえ、いまでも反社が企業活動に影響を与えることは珍しくありません。いまでは仕事をすすめるうえで、相手が反社ではないか確認する「反社チェック」はごく一般化しています。なぜ反社とつきあってはいけないのか、どういう過程でコンプライアンス意識が高まっていったのか、これまでの歴史や今回のいわき信組の事件から、改めて教訓を学びたいところです。
◆朝日新聞デジタル版のベーシック会員(月額980円)になれば毎月50本の記事を読むことができ、スマホでも検索できます。スタンダード会員(月1980円)なら記事数無制限、「MYキーワード」登録で関連記事を見逃しません。大事な記事をとっておくスクラップ機能もあります。お申し込みはこちらから。
 反社会的勢力=「反社」、という言葉を聞いたことはありますか。たまにニュースでも取り上げられるキーワードですが、いわゆる暴力団(ヤクザ)など、暴力や詐欺などで経済的利益を得ようとする人たちのことを指します。ふつうに生活していればまず接点を持つことはない集団ですが、企業がこういった反社と接点を持ってしまい、大きな経済的、社会的ダメージを受ける事件は絶えず起きています。最近でも、地方信組が反社とつながっていたことで大きな問題が起こっています。最新の動きからこれまでのニュースを振り返り、企業と反社との関係について知識を深めておきましょう。業界選択や研究の際に知っておいて損はないテーマです。(編集部・福井洋平)
反社会的勢力=「反社」、という言葉を聞いたことはありますか。たまにニュースでも取り上げられるキーワードですが、いわゆる暴力団(ヤクザ)など、暴力や詐欺などで経済的利益を得ようとする人たちのことを指します。ふつうに生活していればまず接点を持つことはない集団ですが、企業がこういった反社と接点を持ってしまい、大きな経済的、社会的ダメージを受ける事件は絶えず起きています。最近でも、地方信組が反社とつながっていたことで大きな問題が起こっています。最新の動きからこれまでのニュースを振り返り、企業と反社との関係について知識を深めておきましょう。業界選択や研究の際に知っておいて損はないテーマです。(編集部・福井洋平)


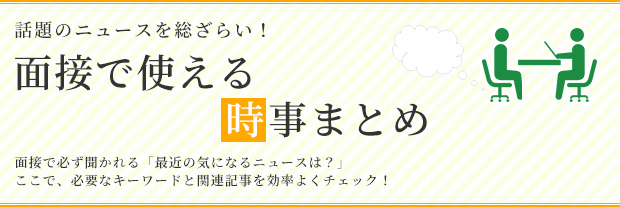
 政府は2007年に公表した政府方針で、反社を「暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人」と定義しています。一般的には暴力団をイメージされることが多いですが、そのほかにも「
政府は2007年に公表した政府方針で、反社を「暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人」と定義しています。一般的には暴力団をイメージされることが多いですが、そのほかにも「 報告書によると、いわき信組と反社とのかかわりは1994年にスタートします。当時、信組では暴力団関係者と交友がある理事がいたため、その事実をつかんだ右翼団体が信組本部や理事長宅周辺で、信組幹部の素行や暴力団関係者らとのつながりを糾弾する「街宣活動」を繰り返していました。街宣活動とは拡声機を積んだ車(
報告書によると、いわき信組と反社とのかかわりは1994年にスタートします。当時、信組では暴力団関係者と交友がある理事がいたため、その事実をつかんだ右翼団体が信組本部や理事長宅周辺で、信組幹部の素行や暴力団関係者らとのつながりを糾弾する「街宣活動」を繰り返していました。街宣活動とは拡声機を積んだ車( この人物に渡す資金は当初、納税充当金を崩して調達していましたが、そのうち知り合いの融資先に必要額より多い融資を行って水増し分を現金で戻してもらうなどして調達するようになりました。さらにいわき信組は、預金している人の了解を得ないままその人の口座を勝手につくり、勝手に融資を行ったことにして、そのお金をこういった反社勢力に渡す「無断借名融資」も繰り返し行うようになります。
この人物に渡す資金は当初、納税充当金を崩して調達していましたが、そのうち知り合いの融資先に必要額より多い融資を行って水増し分を現金で戻してもらうなどして調達するようになりました。さらにいわき信組は、預金している人の了解を得ないままその人の口座を勝手につくり、勝手に融資を行ったことにして、そのお金をこういった反社勢力に渡す「無断借名融資」も繰り返し行うようになります。