 人気企業の採用担当者インタビュー「人事のホンネ」2021シーズン第6弾、JA全農(全国農業協同組合連合会)の後編です。メインの仕事は、農家の生産した農畜産物の販売(販売事業)と農家への資材の供給(購買事業)。農業分野の商社のような役割ですが、公的な側面もあります。お役所とも民間企業とも異なる独特な団体です。(編集長・木之本敬介)
人気企業の採用担当者インタビュー「人事のホンネ」2021シーズン第6弾、JA全農(全国農業協同組合連合会)の後編です。メインの仕事は、農家の生産した農畜産物の販売(販売事業)と農家への資材の供給(購買事業)。農業分野の商社のような役割ですが、公的な側面もあります。お役所とも民間企業とも異なる独特な団体です。(編集長・木之本敬介)(前編はこちら)
■求める人物像
──求める人物像は? 農協関連の団体というと、「堅い」「真面目」など公務員に重なるイメージがあります。
服部(写真左) 組織上さまざまな人と関わりながら仕事をしていくので、対人能力が必要です。組織や農業の課題を解決する問題解決能力も必要ですね。事業を提案して若手の力を発揮する場面もあるし、責任ある仕事を任される職場なので、「チャレンジ精神」も掲げています。
──受けに来る学生は?
服部 安定志向の学生もいれば、「何でもやります、どこでも働きます!」という学生もいますね。
小野(写真中) 安定志向の人は、裏を返せば手堅く仕事をするので悪いわけではありませんが、「安定」が全ての優先順位になっているように感じられる人は難しいですね。現実のJA全農に、安定的に仕事を進める人間が多いからこそ、若手にブレークスルーの機会を与えたい、多少のことには目をつぶってもチャレンジ精神のある学生を採用したいと思っています。とくに事業環境が変わる中、自己改革に取り組んでいる今はなおさらそうした企業風土が必要だし、「減点主義」ではなく「加点主義」で採用したいと考えているので、採用担当者には「加点主義でお願いします」と言っています。面接官によっては判断基準や目線が違うこともありますが、そういう場合には、自分の印象で良いので「一緒に仕事をしたいか」「同僚と一緒に働かせて大丈夫か」で考えてと言っています。
──農業は、TPP(環太平洋経済連携協定)、日米交渉など世界情勢が大きく影響します。ニュースについて面接で聞きますか。
小野 「農業で気になることはありますか?」などと「農業」をキーワードに聞くことはあります。ただ、「今日のニュースを見て適当に言っているな」と感じる上滑りの返答もあるので、必要以上に背伸びしなくても大丈夫です。
■社風
──JA全農はどんな団体ですか。
小野 組織内外の関係者と協調しながら、チームで仕事を進める団体です。JAグループの一つなので、組織連絡やチーム力を大切にした仕事の仕方をしています。といっても組織でガチガチに縛るわけではなく、みんなとのコミュニケーションやネットワークを大切にしながら仕事を進めています。一人ひとりのサムライが自由に仕事をしているわけでも、組織力を前面に押し出しているわけでもありません。
──JAグループで連携する仕事が多い?
服部 常に連携しているわけではありません。機能分担がしっかり分かれていて、JA全農は経済事業を担っており、商社やメーカーのような仕事です。農林中金は銀行、共済連は保険、全中は指導と役割が分かれています。常に連携しているのは地域の市町村にあるJA、経済連ですね。
──グループ内の最大組織ですよね。
服部 JA全農は「全国を統括している」と考えている人もいますが、そうではなく、全国規模で経済事業を行っているということになります。統括している、指導しているという立場ではなく、あくまで役割分担です。
小野 たとえば、トマトを生産して市場に出荷するにしても一農家・一農協では販売先であるスーパーなどに年間を通して安定供給することが難しいかもしれない。そうしたときにJA全農が全国で各産地の出荷時期を調整しながら供給を維持して良い販売条件を得る。そしてそのメリットはJA、農家に還元する。あるいは飼料用のトウモロコシは数万トン単位の大型船で輸入しますが、一農家・一農協ではそれだけのボリュームを消化できない、かといって数十トン単位のコンテナで輸入すると輸送コストが上がる。そうしたときにJA全農が大型船でトウモロコシを輸入して配合飼料を製造し各畜産農家にお手ごろな価格でお届けする、そういった農家・JA単独では実行が難しい、あるいは効率が低い機能を補完するのがJA全農のミッションであると考えています。



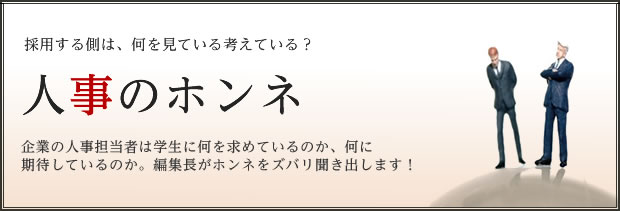
 ■やりがいと厳しさ
■やりがいと厳しさ








