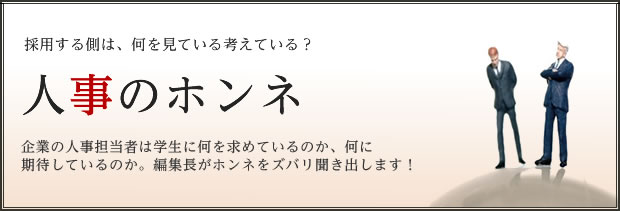人気企業の採用担当者インタビュー「人事のホンネ」2023シーズン第4弾、京セラの後編です。「京セラドーム」で知られる世界最先端の電子機器メーカーは、「大家族主義」でも有名です。いったいどんな会社なのでしょう。(編集長・木之本敬介)
人気企業の採用担当者インタビュー「人事のホンネ」2023シーズン第4弾、京セラの後編です。「京セラドーム」で知られる世界最先端の電子機器メーカーは、「大家族主義」でも有名です。いったいどんな会社なのでしょう。(編集長・木之本敬介)(前編はこちら)
■面接
──面接について教えてください。
技術系、営業管理系共に、例年面接は複数回行っています。とくに技術ではプロダクト別採用を行っているので、学生が希望した部門の責任者と面接してもらい、技術的なマッチングを図っています。
──それぞれの段階で確認するポイントは?
たとえば3回行うとしたら、1次は人事の目を通して次に進んでもらう人を見極め、2次は営業なら営業の責任者が仕事への適性を中心に見ます。会社への理解がより深まるように、学生からの質問の時間も大切にしています。最終の3次は幹部の立場から見ての総合評価となります。
■適性検査
──コロナ禍で適性検査が自宅でのWEB検査になりました。誰が受けているか分からないという面もあります。
原則はテストセンター受検です。「テストセンターで受けられる状態であれば、テストセンターで受けてください」という姿勢で、緊急事態宣言が出ている地域は自宅でのWEBテストにしました。中には外出して受けたくないという人もいるので相談に応じて対応しました。
──適性検査の使い方は?
能力面は一定の点数で線引きをしますが、そこから先は営業向きか管理向きかなど職務適性を見るので、合否判定には使いません。
■ニュースへの関心
──世の中の出来事やニュースへの関心度合いは重視しますか。
市場感覚というか、世の中の動向に興味を持っているかどうかは非常に大切です。営業の社員はもちろんですし、職種に限らず技術系も自分のやっている仕事がどういう世の中の流れで注文をもらっているのか、次にどんな戦略で会社が伸びていこうとしているのかなど、経営的な感覚は持っている必要があると思います。
──面接で聞きますか。
人によりますが、時事ネタを聞く面接官はけっこういます。事業に関連する内容について興味があるかどうかを聞くケースが多いと思います。
■学校推薦
──技術系の採用には学校推薦制度もあると思いますが、内定者の何割くらいを占めるのですか。
2022年卒では、最終的に9割ほどの学生が学校推薦での採用になりました。
――技術系の大半が推薦なんですね。
今は大学ごとにやり方が違って、「学校推薦の選考期間中もいろんな企業を受けに行っていいぞ。マッチングした会社に最終的に推薦状を出すよ」としている大学もあるようです。
──選考が進むうちにマッチングが成立して、その時点で推薦状を持ってくる「後付け推薦」といわれるものですね。
そういう大学もあれば、推薦状を出せない大学もあるのでケースバイケースです。企業としては、来てもらいたい学生が来るか来ないかわからないのはネックですし、推薦状をもらってきてもらえると正直安心です。でも、学生の側からすると、これだけ企業がある中で合格が出たらそこしか行けないと道を狭めるようなやり方は理想ではないと思います。京セラとしては、自由に受けてもらって最終的にうちに決まったら確実に来てね、という感じです。
──ガチガチの学校推薦より、お互いに良いのかもしれないですね。
学生や大学の先生と話すと、最近は学校推薦を使う学生が減って自由応募で受ける学生が増えてきていると聞きます。専攻によって違って、電気・電子系は今でも学校推薦を選ぶ学生が比較的多いようですが、情報系などでは推薦を使わず自由に行くところを決めたいと考える人が多いそうです。
──京セラが推薦の対象にしている学校はどのくらいあるのですか。
全国で100校ほどです。京セラの事業領域は多岐にわたるため求人対象学科が多く、電気電子、機械、情報、材料、物理などを中心に、学科ごとに求人票を送付しています。…続きを読む