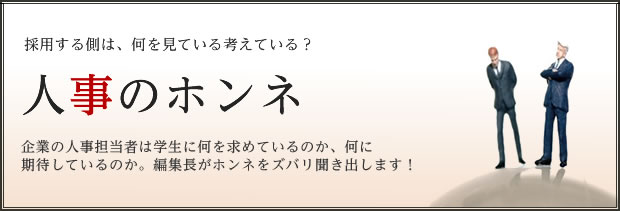人気企業の採用担当者インタビュー「人事のホンネ」2022シーズン第1弾、三菱商事の後編です。総合商社をいまだに貿易の会社と思っている人はいませんか。事業投資を経て、今や事業を経営する会社に大変身をとげています。こうした時代に合わせた変化こそが、就活生の人気ランキングでトップクラスにあり続ける秘訣です。でも、「経営人材」になれるのって、どんな人?(編集長・木之本敬介)
人気企業の採用担当者インタビュー「人事のホンネ」2022シーズン第1弾、三菱商事の後編です。総合商社をいまだに貿易の会社と思っている人はいませんか。事業投資を経て、今や事業を経営する会社に大変身をとげています。こうした時代に合わせた変化こそが、就活生の人気ランキングでトップクラスにあり続ける秘訣です。でも、「経営人材」になれるのって、どんな人?(編集長・木之本敬介)(前編はこちら)
■求める人材
──求める人材について、採用ホームページには「構想力」「実行力」「倫理観」とありますね。
三菱商事は「経営人材」が育つ会社を目指しているので、これに必要な資質を持った人ということになります。経営人材というと、「全員社長になるの?」というイメージを持たれますが、そうではありません。1700社のグループ企業も含め、それぞれが携わる事業の価値を上げていくのが経営人材です。
──もともと貿易会社だった総合商社は、投資がメインになり、今は経営という流れですね。
トレーディング主体で始まり、1980年代までは100円で買ったミネラルウォーターを105円で売って5円が利益になるという仲介モデルが中心の「トレーディング期」でした。市場の変化や顧客のニーズに対応するために、国境を越えて売り手と買い手を結ぶ仲介役として幅広い産業を支えてきました。
1980年代半ばの円高不況、それに続くバブル経済とその崩壊を経て、事業環境は厳しくなりました。仲介役から一歩踏み出し、川上・川下へのマイノリティ出資によって取引を広げ、中間流通業者として付加価値を生み出す事業に取り組みました。これを「トレーディング発展期」と呼んでいます。
原材料を調達し、製品を作り、顧客にサービスが届くまでの一連の連鎖をバリューチェーンと呼びますが、2000年代に入ると、産業界全体のバリューチェーンの力学が変化し、仲介という事業モデルの変換が求められるようになりました。事業投資を加速させて事業そのものの運営に乗り出す「業態転換期」を迎えました。
2010年代半ばには、資源市況の環境が変わり、資源と非資源のリバランスやキャッシュ・フロー重視の経営を進めるようになりました。投資で成長する発想から、自ら事業に深く入り込み、三菱商事の「経営力」で主体的に価値を生み出し成長していく「事業経営」へのシフトを図っています。
このように、三菱商事は環境変化に応じてビジネスモデルを柔軟に変化させ、価値創造に取り組んできましたが、どの時代も変わらないのは、社員が会社を切り盛りし、会社の行く末を社員自ら切り開いてきたということです。社員が財産であり、社員の成長が会社の発展と一体化している会社なので、会社は社員に対し、チャレンジングな仕事=場の提供をします。それに応え、成長してくれる人材を求めています。
──事業経営のためには「構想力」「実行力」「倫理観」が必要だと?
はい。「構想力」は、本質を見抜く洞察力、変化を見通す先見性、創意工夫して戦略を練る力です。For the teamの精神で、困難を乗り越える強い心と周囲を動かすリーダーシップを持って、難しい大きいビジネスをするのが「実行力」です。「倫理観」は三菱商事の特徴の一つです。瞬間的にもうかるビジネスはありますが、社会に役立つ事業でなければ続きません。社内外の関係者と誠実さを持って信頼関係を築き、中長期的なビジネスを構築することが必要だと考えています。
──その人材をどう見極めますか。
これまでの人生で、何を考え、何をやってきて、そこから何を学んだかという点は重要だと思っています。同じことを社会に出てもやってくれると期待ができるからです。
──ビジネスでいう「PDCAサイクル」ですね。
PDCAサイクルほどきれいにまとまっていなくていいし、やってきたことの大小や成否も関係ありません。よく、三菱商事は「100人規模で全国で優勝するような部活の主将をやっていないとダメなのか」といった質問を受けますが、全くそんなことはありません。面接で話すエピソードも「このカテゴリーじゃないと」「インパクトがないといけない」ということもありません。学業でもアルバイトでも留学でも、本当に何でもよくて、話してほしいのは「何を考えて、何をしたのか」です。仮に失敗してしまったとしても「失敗から何を学び、次にどういかしたか」があると、思考と行動のプロセスが分かります。…続きを読む