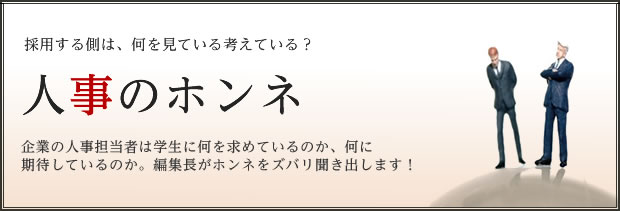人気企業の採用担当者インタビュー「人事のホンネ」2020シーズンの最終回、神奈川県庁の後編です。秋季チャレンジは難しい「専門試験」なしですから、民間志望者にもチャンスがありそう。一方で「公務員になりたい」だけの人はNGだとか。志望動機のポイントを聞いてみました。(編集長・木之本敬介)
人気企業の採用担当者インタビュー「人事のホンネ」2020シーズンの最終回、神奈川県庁の後編です。秋季チャレンジは難しい「専門試験」なしですから、民間志望者にもチャンスがありそう。一方で「公務員になりたい」だけの人はNGだとか。志望動機のポイントを聞いてみました。(編集長・木之本敬介)(前編はこちら)
■1次試験
──選考について教えてください。
夏の1次試験は「教養試験」「専門試験」からなる筆記試験、2次では論文試験、グループワーク、面接を行います。
──筆記試験はかなり勉強しないと受かりませんよね。
地方公務員法第20条で「採用試験は、筆記試験その他の人事委員会等が定める方法により行うものとする」と書かれていますから筆記試験は行っていますが、学校の勉強だけではなく、専門学校にも通う「ダブルスクール」の人が多いようですね。
ただし、秋季チャレンジでは専門試験をなくしました。確かに専門試験は難しいですが、教養試験だけなら独学でも勉強できると思います。
──秋季チャレンジで専門試験をなくしたのは、いろんな人が公務員を目指せるように?
はい。代わりに自己PRシートを出し、面接では最初の5分程度で「意欲・向上心・行動力」をプレゼンテーションしてもらいます。この点は普通の公務員試験とは違います。
■GDと論文
──2次試験のグループワークは、いわゆるグループディスカッション(GD)ですね。
8人ほどで約1時間、グループワーク形式で実施しています。事前にテーマを与えて考えてきてもらい、その場で議論してグループとしての意見をまとめ、発表してもらいます。
面接だけでなく多面的に人物を見ます。どういう人で、どういう役割か、人物特性を見ています。組織での立ち居振る舞いも見ます。
――2019年卒の夏試験のテーマは「18 歳までに身につけておいた方がよいことは何か、グループで3点挙げ、優先順位をつけた上で、その理由について説明しなさい」でした。事前にテーマを示すのはどうしてですか。
事前にテーマを伝えることで準備をしてもらい、当日は活発な議論をしてもらうためです。
──最近はGDの訓練をしてくる学生が多いと思います。
かなり慣れていますね。役割分担を含めて、すべて自由に進めてもらいます。
発言内容にもよりますが、極端に発言が少ない人は評価が難しいですね……。
──過去の論文のテーマは「人工知能(AI)」「SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)」など比較的オーソドックスですね。
論文試験では思考力、創造力、論理力、柔軟性を問うことにしています。県職員はたくさん文書を書かなくてはいけないので、基本的な文章の作成能力があるかどうかが大切ですね。分かりやすい文章が書けないと話にならないので。…続きを読む