
■エントリー数と自社説明会
――エントリー数を教えてください。
プレエントリーが4万人弱。本エントリーが1万人弱ぐらいです。プレエントリーは前年と比べるとやや減りました。本エントリーは例年並みです。
──2017年卒は就活スケジュールの短期化で志望企業を絞り込んだ学生が多く、多くの企業でエントリー数が減ったようです。
採用広報に力を入れたこともあり、人数は維持できました。6月の選考解禁より前に他社に決まっている学生も結構いました。それを考えると、本エントリーがもっと減ってもおかしくないところでしたが、維持できたと思います。
──何か工夫した点は?
博報堂と博報堂DYMPは2014年に「未来を発明する会社へ。Inventing the future with sei-katsu-sha」というビジョンを発表しました。そのビジョンを採用広報の中にも徐々に入れています。
ポイントは、ITやデジタルの進化で生活者や企業を取り巻く環境が変わる中、今までのビジネスからもう一歩広げたり、まったく新しい領域に踏み出したりする発想が必要だと打ち出していることです。もともと私たちは、「新しいことをどんどんやろう」と言い続けている会社ですが、ここ2年ぐらいは特に、新しい発想やビジネスができる素養のある人材に対してメッセージを強めに出しています。
他には「自社説明会」に力を入れています。学生を弊社に招き、いろいろなプレゼンテーションをして共有しました。一昨年、昨年と少しずつ回数を増やしています。
──以前は自社説明会をしていなかったのでしょうか?
合同説明会では話していましたが、自社説明会を増やしたのは最近です。うちの会社に来てもらって、どんな社員がいるのか見て、生の声を聞いてもらうのが目的です。内定者からも好評で、今後も力を入れていきます。やはり、実際に来てもらえばじっくり話ができますから。
かつてOB・OG訪問が就職活動の主流だった時代は、会社に来て社員と話して、どんな仕事か直接聞いてもらっていました。その後、WEBエントリーが普通になると、OB訪問しなくても就活はできるし、情報もネットで見られるようになりました。便利にはなりましたが、「生の仕事感」「生の会社の雰囲気」を学生に伝えにくくなったのではないか、という反省がありました。実際にいきいきと働いている社員を見て、話してもらう機会を再び増やしていこうとしています。
──自社説明会はどんな内容ですか。
まず、若手社員が「どんな仕事をしているか」「就職活動のときはどうだったか」という話をします。それから社員数人のパネルディスカッションをします。Q&Aも含め計2時間弱ぐらいですね。
参加者は昨年が2500人くらい。今年は約3000人に増やしましたが、応募が1万1000人ほどあり、参加できない人も多かったので、さらに増やす予定です。
■インターンシップ
──夏に実施したインターンシップについて教えてください。
2種類あって、一つは職種を限定しない普通のインターンシップ。博報堂が考える「生活者発想」という概念を仕事に落とし込む体験をしてもらう「生活者発想合宿」です。長野県の軽井沢で2泊3日、30人×2回開きました。形式を変化させて、これまで14~15年間やっています。
もう一つは、クリエイティブ職向けの「クリエイティブ・サマーキャンプ」です。デザイン、コピーライターなど職種ごとに10人ほど募集し、通い形式で1週間くらい。こちらは始めてから3~4年です。
冬インターンの予定は今のところありません。
──インターンに参加した学生には、その後も接触していますか。
クリエイティブの講義や相談会をしています。「博報堂に来てほしい」というよりは「大学生のキャリアを一緒に考えよう」という取り組みですね。もちろん、高い倍率のインターン選考を通過した学生で、かつインターンで様子も見ていますから、「このまま来てくれればいいな」と思う学生はいますが。
──インターン参加者から内定はいますか。
年によって違いますが、10人~20人くらいです。
■面接
──2018年卒の選考スケジュールは?
2017卒と同じで、3月WEBエントリー開始、6月から選考の予定です。
──WEB適性検査や書類選考でかなり落とす?
SPI試験をテストセンターで行いますが、できるだけ実際に会います。1次面接は4500人ぐらいの方とします。
──2人に1人は面接に進める……意外に多いですね。1次面接はどんな形式ですか。
2017卒では、1対1の面接を2回しました。1回あたり5分から10分。職種が多彩なので、社員によって「この学生は営業に向いていそう」「クリエイティブの面から見ると、すごく良い」など、違う見方があります。そこで、複数の職種の社員が見たうえで次のステップに上がってもらうようにしています。
──2次選考は?
2017卒では、7~8人のグループディスカッションを2時間半から3時間ほどしました。ディベートをしたり、チームで一つ提案をつくってもらったり。さらに社員との座談会の時間も設けているので、半日がかりです。社員との座談会は選考ではなくOB訪問の一環のような形です。
──どんなワークをするんですか。
抽象的なテーマで話し合ってもらい、「正しい答え」がない課題にどう取り組むのかを見ます。テーマは毎年変えて基本的に公表していませんが、たとえば過去には「紙の本と電子書籍はこれからどうなっていくか」「これからの出版業界や本を読む人の生活シーンはどうなっていくか」というようなテーマを出したことがあります。
──どこを見るんですか。
各グループに社員が2人ほどついて、どんなことを話しているかや、チーム運営の様子を見ています。「この人はリーダーのタイプだな」「この人はアイデアを出す人だな」といったところも見ますね。
ただ、ビジネスの特性上、一定のコミュニケーション能力は必要です。クライアントや媒体社と一緒にパートナーシップを築いていくときに、「いや、私は全部一人でやります」というスタイルだと厳しい。基本的なことですが、チームでうまくやっていけるか、人の意見をきちんと聞けるかは重視します。
──最終面接の形式は?
2017卒では、学生1人に対し、役員や部門長、局長クラスの3~4人で面接しました。時間は30分ほどです。
──それぞれの面接ごとに見るポイントはありますか。
一貫して「特になし」ですね(笑)。学生からは「そこが難しい」とよく言われますが、「こういう人材がほしい」という決まった方針はないんですよ。よく言われることですが、博報堂の人材は「『粒ぞろい』より『粒違い』」。つまり、「いろんな人がいて良い」という考え方なので、それぞれの芸風がしっかりあるかどうかが重要ですね。
──「芸風」とは広告会社らしい表現ですね。「個性が強い人」ですか。
うーん、「あまり個性が強くないのが個性」という人もいますしね。派手で、よくしゃべって、イケイケで、という人ばかりではないですよ。
──それがまさに広告業界のイメージですが(笑)。
そうですね。でも、おとなしい学者肌のような人でも、話すとすごく面白いことがあります。とつとつとしゃべる人もいれば、早口でペラペラしゃべる人もいますから。
いずれにしても、面接やグループワークのなかで、「一緒に働きたいかどうか」は見ています。私も面接をしますが、「自分の部下に入ってきたらどうか」「自分の上司にこの人がいたらどうか」という観点で見ます。「ちゃんと下が育つかどうか」「リーダーになれそうか」は考えますね。
──印象に残っている学生は?
「大学時代、○○をしていました」という話のバリエーションが多いタイプですね。「水産学科でイルカの研究をしています」とか、一見「それ全然、広告に関係ないでしょ」という学生もいました。うちの部署にも宇宙工学を専攻していた社員がいます。
よくいるタイプはイベント系のサークルで活動していた学生ですね。そういう学生はとても多いので、よほど面白くないと、それだけでは目立ちませんが。
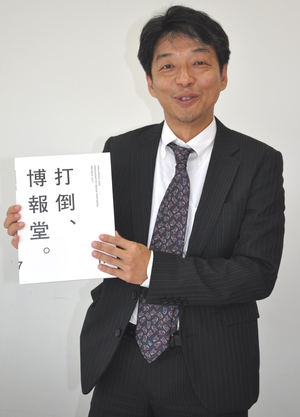 企業の採用担当者に直撃インタビューする人気企画「人事のホンネ」。2018シーズンの第4回は、広告大手の博報堂です。
企業の採用担当者に直撃インタビューする人気企画「人事のホンネ」。2018シーズンの第4回は、広告大手の博報堂です。


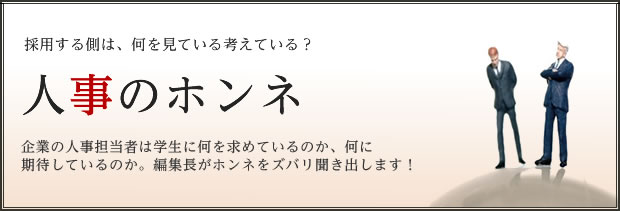
 ──両社の仕事の違いを教えてください。
──両社の仕事の違いを教えてください。 ■エントリー数と自社説明会
■エントリー数と自社説明会 ■エントリーシート
■エントリーシート ■社風
■社風









