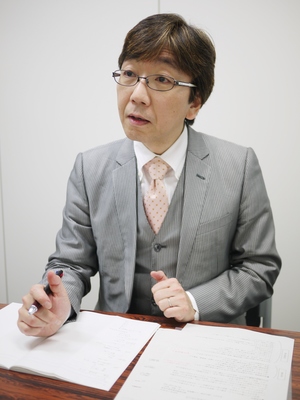
■面接
――その後の面接は何回ですか。
例年は1次面接を含めて3~4回です。GD以降は30分から1時間弱の1対1の面接を予定しています。
――面接で特に着目するポイントは?
学生時代の経験談を深掘りすることが多いですね。一つひとつの物事にどれだけ失敗をして、原因は何だったのかをちゃんと振り返り、新たに挑戦していく……というサイクルができているかどうかを知りたい。どういう目的意識で行動してきたかもしっかり聞きます。
――中田さんが重視する質問は?
学生は、自分がやりたいと思ってやってきたことはいきいきと話をします。でも社会に出ると、自分のやりたい仕事ができることは非常に少ないと思います。「やりたい」仕事をやるために「やらなければいけない」ことが出てきて、そこが大きな壁になったりする。「やらなければいけないこと」に対してどう自分の中で納得して行動に移してきたか。そこを聞きたいと思っています。
――学生時代に「やらなければいけないこと」とは。
勉強でも部活でも、得たい成果がありますね。そのために何をやらなければいけないのかと日々考え、目標を定めたうえでどんな努力をしてきたか、というプロセスが知りたいですね。
――印象に残っている学生は?
やはり部活の話が多いですね。たとえば野球をしていた学生で、ケガで野球を続けられなくなり一度は挫折したものの、プレイヤーでない自分が組織の中で何ができるか考え、チームのモチベーションを上げるために、もがきながら提案したり行動したりしてきたという話をしてくれた人がいます。非常によかったですね。
――「失敗をいかに語れるか」が大事?
就活では「うまくいったこと」だけを話してしまう傾向があります。ただ、うまくいった過程で大変だったのはどこか、そのポイントで何を考えどう行動したかを深掘りすることで本人の価値観が見えてくる。アルバイトで頑張って感謝されたという成功体験の部分ではなく、そこに行き着くまでの具体的なプロセスを聞くようにしています。ESにはそこまで深いことは書かれていないことが多いので、ESですべてを判断しようとは考えていません。ESはよく書こうと思えばいくらでも書けてしまうので、あくまで面接のきっかけ。そこから掘り起こす、引き出すように聞いていきます。
――引き出し方は社員間で共有されているのですか。
当然共有をしていきますが、我々はOFCのころからオーナーさんの抱えている課題を日々引き出すことを意識していました。ただ「この商品が売れているから入れましょう」と言うだけではオーナーさんの行動は変わらない。そういう仕事を積み重ねているので、対応できると考えています。
■ES
――ESの項目を教えてください。
基本的には履歴書と同じ形でシンプルです。個人情報や大学時代に力を入れたことなどの基本的な情報。アルバイト、ゼミや研究内容、半年以上の留学経験、あとは志望動機と自己PRだけですね。
それから、セブン-イレブン・ジャパンのどの部分が魅力と感じたのかが400字以内。ここからは本人の価値観が出てくると思います。なぜOFCの仕事に興味を持ったのかも400字以内。インターンに参加した学生も多いので、どこに成長を感じたのかも聞いています。
――セブン-イレブンの魅力の欄では、自分の身近なセブン-イレブン体験を書く人が多いのですか。
そうですね。「商品力が魅力」という人も「新しいことに挑戦しているところが魅力」だという人もいますが、会社説明会では私たちの信念を伝えているので、そこに共感しているかどうかを確認したいです。
――採用HPにある「日本の、世界No.1ブランド」「安定こそリスク」といった理念への共感が必要?
そうですが、ESだけで判断するのは学生にも失礼だと思います。あくまでESは面接の一つの資料です。一つの項目に2行程度しか書いてこないようなESは、意思や意欲があるのかと疑いますが、これはセブンーイレブン・ジャパンに限らず、就職活動で企業と向き合うにあたり基本的な事項ですよね。
――同業他社との違いを認識していることは大事ですか。
そこは「理解していただいてありがとうございます」としか言えない部分ですね。我々は他社のことはわからないし、当社には他社と比べて考える文化がありません。それよりも、当社の理念にどう共感しているかが大切です。
――セブン-イレブンの価値観の中で一番重視しているのは?
我々はフランチャイズビジネスです。オーナーさんが「加盟してよかった」「夢が実現できてよかった」と思ってくださらない限り、私たちのビジネスは成り立たない。加盟店の満足度が向上していけば、オーナーさんも自然とお客様としっかり向き合えるようになる。我々が向き合っているのはオーナーさんであり、お客様と最前線で向き合っているのはオーナーさんである、という部分を理解しているかはすごく見ますね。
■求める人材
――フランチャイズビジネスを展開するうえで、求める人材とは?
本当にオーナーさんと向き合えるかどうかですね。よく「人と向き合う仕事が好き」と言う学生がいます。人と向き合う仕事は世の中にたくさんありますが、我々が向き合うのは、自分の家族の人生もかけて経営されている方です。そういう相手に、どれだけ自分の思いをぶつけていけるか。
「成長していきたい」という学生もよくいます。良いことですが、単に「自分が成長したいからこうしたい」だけだとベクトルが自分に向いている。自分のことしか考えられないOFCにあなたなら自分の店を担当してほしいと思うだろうか、という話を学生にはします。ベクトルをオーナーさんに向け、オーナーさんに対して何ができるかを考え、やり続けて、うまくいかないことも経験し、結果として成長してほしい。
当社の鈴木敏文会長はよく「脱チェーンストア」という言葉を使います。発注の権限をすべて持っているオーナーさんと個別に向き合ってアドバイスしない限り店の売り上げは伸びない。今後、この部分に対する要求がさらに求められると思います。
――フランチャイズビジネスに対する学生の理解度は?
なかなかわかってもらえないのですが、我々の信念はそこにあるので、繰り返し伝えていくことはすごく大事だと思います。ここの理解がないと厳しいし、お店の数値も自分自身も変えられない。未知の新たな商圏を開拓して売り上げをどんどん上げていきたいというタイプや、何とかしようと自分だけで一人で頑張ろうというタイプの人は苦労すると思います。なぜなら、OFCは自分だけが動くのではなく、オーナーさんの意識、行動を変えないといけないからです。
OFCが一つの店を担当するのは平均3年くらいですが、担当から外れた後に店舗の体制や数値が元に戻ってしまったら、OFCとして失格だと学生に言います。自分がいなくなっても、オーナーさんと一緒につくってきた組織の考え方や仕組みが残ることで恒久的に売り上げが上がるようにするのが良いOFC。私は、OFCがいなくなった時がOFCの存在意義を示す指標になると考えています。
――採用HPからは、新しいことにチャレンジできる人材を求めている印象を受けましたが。
その要素ももちろんあります。新しいことに挑戦するというのは、仕事の「仕方」に関してのことで、人間関係を構築することとは別です。同じことを繰り返すだけではオーナーさんの意識は変わらないし店も変わらない。だから、新しいことに臆せず挑戦したり提案したりする必要がある。オーナーさんはその土地で20年も30年も商売をやってきて実績も自信もあるから簡単には変わらない。でも、変わらなければ店舗は衰退してしまう。そんなときに新しい仕事のやり方や挑戦を提案できるのは、OFCだけなんです。
「挑戦」というと奇抜なことをするイメージがありますが、セブン-イレブンで毎年発表するスローガンの中に必ずあるのは「変化への対応と基本の徹底」という言葉です。変化に対応し新しいことに挑戦するのは大切ですが、基本も忘れてはいけない。そこを間違うと、奇抜なもの、新しいもの、その場限りのものになってしまいます。
――ありがちな志望動機ってありますか。
「地域貢献ができる」というものが多いですね。これも貢献をするのはセブン-イレブン・ジャパンではなくオーナーさん。オーナーさんが地元に根ざした商売をするから地域貢献できるわけで、OFCとしてオーナーさんの意識、行動を変えていくことの重要性はここにもあります。
――内定が競合するのは?
昨年だと銀行、商社、メーカーが多かったですね。
 ■採用数とスケジュール
■採用数とスケジュール


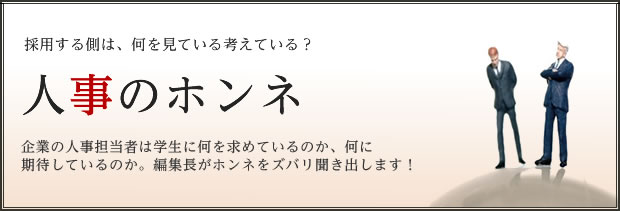
 ■職種
■職種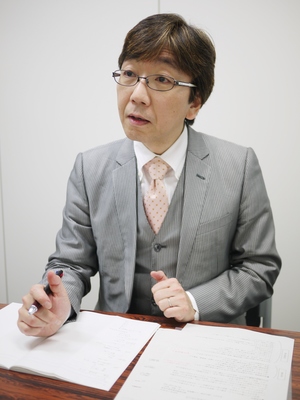 ■面接
■面接 ■社風
■社風 ■中田さんの就活
■中田さんの就活









