
■選考の流れ
――2015年度新卒採用の大まかな流れを教えてください。
12月1日にWEBエントリーの受け付けを始め、自宅のPCでWEB適性検査を受けてもらいます。並行してセミナーなどを開きます。その後、エントリーシート(ES)を受け付け、4月1日以降に2~3回面接があります。募集職種によって選考フローは異なります。
――もともと紙が主体の印刷会社ですから、ESはWEB上ではなく、紙に手書きですか。
紙に書いて郵送してもらっています。内容は、志望理由は何ですか、どんなことにチャレンジしたいですか、など一般的な質問が多いですよ。数年前、書く量を増やしてA4サイズ3~4枚にしたら内定者から「あれはきつかった」と大変な不評だったので、従来の2枚程度に戻しました。
――面接はどんな形式ですか。
これも職種によって異なるのですが、営業職では、2014年新卒採用の1次選考は6~8人でのグループディスカッション(GD)でした。面接官はディスカッションをする様子を見て、最後に少し質疑をします。
――どんなテーマで行うのですか。
ソフトなものが多いですね。学生ならではの議論が盛り上がりそうなものから、社会人になったらこういう場面に直面しそうというものまで。どんな風に考えられる人なのかを見ます。一つの班に社員が2名付いて、質疑も含めて1時間から1時間半くらいかけます。
2次は1対2の個人面接。学生1名に対し、面接官は人事総務系の社員と、営業部門や配属予定職場の社員の組み合わせ。課長クラスで時間は30分くらいです。
3次が最終面接で、面接官3対学生3の集団面接です。面接官は、役員と人事部長の私と、採用の課長です。時間は45~50分くらい。最終面接を3対3にしているのは時間的な制約が理由です。学生同士を比べるためではありません。
――それぞれの面接では、主にどんなところを見ているんですか。
グループディスカッションでは、コミュニケーション能力や論理的に考えられる人か、討論を観察しながら見ます。2次面接は本人にクローズアップして、仕事をやり抜く力があるかを見ていきます。
――最初にグループディスカッションをする理由は?
出来るだけ多くの人に会いたいので、大勢を受け入れるためにやっています。学生同士で話をさせることで、結構いろいろなものが見えてきます。結論を導き出すためにどういうパートを担って、どう対応するか。最後は必ずインタビュー形式で個別に質問します。そこでの受け答えも瞬発力ですよね。ある一定のことは分かります。
学生から「どんな役割をするといいですか?」とか聞かれますが、関係ありません。さすがにひと言も話さないのは評価のしようがないので、少なくとも自分の何かしらをPRしてほしい。司会は上手くいけばプラスですが、逆に空回りしてしまう学生もいます。やると言ったからには責任を持ってやってほしい。
――最終面接でも落ちますか。最終のポイントは?
最終でも落ちます。最終面接で見るのは人物の全体像。どんな能力を持っているか、どういう経験をしてきて、何を感じたのか、私はそこを重要視しています。今の学生はいろんな経験はしていますが、そこから何を感じ取ったのかが大事です。
学生の本業である勉強をどれくらいやってきたのかも見たいが、学業をPRする学生は少ないですね。では、学業以外で得たもの感じたものは何ですか、ということになりますよね。アルバイトの目的はお金のためでもいいが、その経験からあなたは何を身に付けましたか、というところに関心があります。
――学生の体験に「就活目当てじゃないの?」と感じることがありますか。
ありますし、実際に会って話をすれば分かります。「語学目的」の留学を挙げる人は多いですが、就活目的でESに書くためだけであれば、非常にもったいない。せっかく時間と労力とお金をかけて、別の土地へ行ってきたのだから、「留学」と書くだけではなく、そこから何を感じ、何をつかんできたのか書いてほしい。留学で何かを見てきれいだった、面白かっただけでは足りないんです。活動への主体性など、何かつかんできた子は面白いですね。
――凸版印刷を受ける学生のタイプってありますか。
一概には言えません。凸版印刷は事業分野が非常に多岐にわたり、広告に近い仕事、出版印刷、パッケージ包装材関連、エレクトロニクス部材、半導体関連部材をやっている部門などがあり、会社自体にいろんな人がいる。受けに来る人もいろんな人がいますね。
――では、ほしい学生像は?
「コミュニケーション能力」と「感性」「感じる力」がある人。我々の仕事は、決まったものをつくってお客様に届ける仕事ではありません。お客様と一緒にお客様が求めるものをつくっていくのが仕事ですから、「感じる力」をすごく大事にしたい。お客様がほしがっているものは、お客様自身もイメージのレベルで伝えることが多い。それをどう形にしていくか、それが「感じる力」であるのかなと。
メディア関連やプロモーションの事業も行っている会社なので、好奇心も大切です。お客様の課題解決のためには、トレンドを先取りして提案していかなければならず、それに精通していなければ納得してもらえない。「多くを感じる力」を持つには、多くのことにアンテナを張っていなければいけないんです。どうやって感じ取るか、どれだけのことを感じ取れるのかもありますが、まずは感じることが大事です。だから、外に出て行くのが自然な人。そういう学生が合っているかなと思います。
あと、どんどん仕事の業態が変わっているので、自分たちでビジネスをつくれるような主体性、バイタリティー、柔軟なものの考え方を備えた人が必要です。凸版印刷というフィールドを使って、自分のアイデアで何かを始めてみたい人を採りたい。社内でいろんな仕事を勝手につくっていく会社なので、ベンチャーっぽくチャレンジしてくれる人に来てほしいですね。うちにはベンチャーよりはいろんな基盤があって、歴史も、取引先もある。そういった土台を使って新しいことができます。
…続きを読む※続きを読むためにはあさがくナビへの会員登録が必要です。
 ■昨年の採用実績、職種
■昨年の採用実績、職種


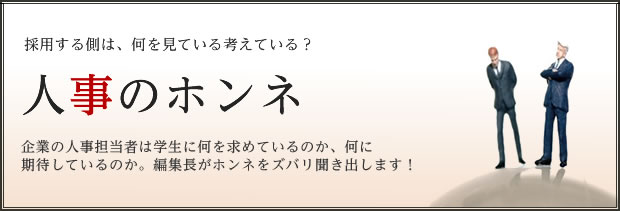
 ■選考の流れ
■選考の流れ








