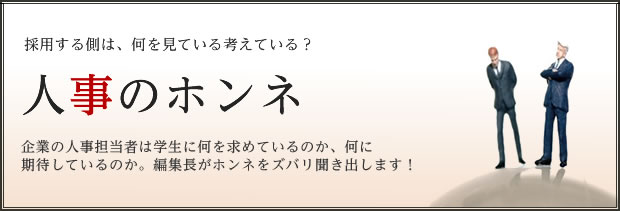人気企業の採用担当者に直撃インタビューする「人事のホンネ」の2023シーズン第5弾は、NTT東日本です。通信業界最大手NTTグループの中核企業は、コロナ禍でこれまで以上に注目度、存在感を増しています。採用選考も通信がなければ成り立たなくなりました。グループディスカッション(GD)もWEBで実施。WEB選考ならではの見極めポイントがあったそうですよ。(編集長・木之本敬介)
人気企業の採用担当者に直撃インタビューする「人事のホンネ」の2023シーズン第5弾は、NTT東日本です。通信業界最大手NTTグループの中核企業は、コロナ禍でこれまで以上に注目度、存在感を増しています。採用選考も通信がなければ成り立たなくなりました。グループディスカッション(GD)もWEBで実施。WEB選考ならではの見極めポイントがあったそうですよ。(編集長・木之本敬介)■コロナ禍での2022年卒採用
──コロナ禍2年目の2022年卒採用はいかがでしたか。
河内さん(事務系採用担当=写真右) 「フルWEB元年」で、学生との接触、対話はすべてWEBでした。内定者にもいまだに一度も会っていません。学生も我々もお互いの本音や生の声が届きにくい部分があるだろうと思い、様々な工夫を凝らしてきました。一方で通信の重要性の高まりは学生にも感じとってもらえたと思います。
五十嵐さん(技術系採用担当=写真左) WEB選考で「学生をしっかり見極めて採用する」というミッションを達成できるのか不安でしたが、実際にやってみると、学生の発言内容や考え方、思考力、気配りは対面よりむしろ明確に分かりました。ただ、WEBで優秀だと思って採用した学生がリアルに活躍できる人材かどうかは、長期的な視点では何とも言い難いですね。
──WEBのほうが思考力が分かるのはなぜでしょう。
五十嵐 WEBのグループワークでは小さなブレークアウトルームに分かれます。周囲のグループの声が入らないので個々の学生の発言がよく聞こえます。個々の学生がワークの中でどういう資料を作成して、どんな出来栄えだったかもはっきり見えます。グループディスカッション(GD)の議論内容も聞きやすく発表内容もWEBだと分かりやすいので、能力差が見やすいのだと思います。以前なら評価が発言量に引っ張られてしまうことが多かったかもしれませんが、WEBでは学生の考えをしっかり把握することができ、評価しやすくなりました。
河内 GDでは1グループ6~7人でやりとりするので、人の発言を自分の言葉でまとめたり、自分の意見をアウトプットしたりする言語化能力は対面でなくてもよく分かりました。WEBだと空気がギスギスしやすいので、状況を見て発言していない人に話を振ったり、意見集約のタイミングに気を配ったりといったヒューマンスキルの面も見られました。優秀な学生を見極めることはWEBでも可能だと思います。
──コロナ禍で多くの人が「通信の重要性」を実感しましたが、学生の反応に変化は?
河内 NTT東日本という名前は多くの学生が知っていますが、具体的にどんなことをして、どこに貢献しているのかは目に見えないので知らないんです。今は企業説明で「コロナ禍をどう過ごしていましたか。思い起こすと全部通信につながっていませんか。通信はみなさんの生活の基盤です」と話せば、学生が「自分ごと」として捉えてくれるようになりました。
――かつては電話の会社でしたが、今は何の会社ですか。
河内 ひと昔前の説明会では「電話じゃなくてインターネットの会社だよ」と説明していましたが、今は「インターネットの会社じゃなくて、通信を基盤に世の中に新しい価値を生み出す会社だよ」と説明します。
■WEB説明会
──WEB説明会で工夫したことは?
五十嵐 自社のWEBイベントを2021新卒採用から始めました。2022新卒では、WEBならではの自由度の高いイベントを目指しました。リアルだと「何時から何時」「あなたの回は何時ですよ」となるところを、「好きな時間帯に来てください」と時間の制約をなくしました。さらに、SE(システムエンジニア)やネットワークプランニングなど職種が多いので、聞きたい職種の先輩社員の部屋に自由に出入りできるようにしました。女性社員のパネルディスカッション、若手マネジャーとの対話会、地方の働き方紹介など、さまざまな部屋を用意しました。リアルだと地方の社員の参加は難しいのですが、北海道や宮城の社員とWEBでつないで現地の特色などを伝えてもらいました。1ターム30分で社員が10分ほど話した後は学生と質疑応答のやりとりをしました。リアルな説明会では「ここだけ聞きたいのに30分拘束された」ということもありましたが、聞きたいポイントだけを聞けるようにしました。WEB説明会は3月上旬に2日間実施しました。
――ほかにも?
五十嵐 以前からアンケートでWEBだと「社風や社員の雰囲気が分かりづらい」という声があったので、YouTubeライブ配信を実施しました。例えば、サイコロを振って、そのマスのお題について社員が話す「NTT東日本すごろく」をして「社員食堂で好きな食べ物は?」をテーマに社員4人がディスカッションしたり、エントリーシート(ES)のリアルタイム添削をしたりしました。
──ええっ!? これから受ける学生のES添削を?
五十嵐 はい。我々人事部ではなく、説明会に出ている協力社員が「こう書いたほうがいいんじゃないか」とアドバイスしました。すごろく、ES 添削、「すべらない話」といろいろやりました。学生にとって、「役に立つ、かつ面白い」ことを大事にしています。学生からは「YouTubeライブが最高に面白かった」というコメントがたくさん来ました。WEBだからこそできたと思っています。…続きを読む