
■英語力とライバル他社
――選考で英語力はどの程度重視しますか。
テストセンターの筆記試験で英語力を見ます。それをクリアする最低限の英語力は必要です。それ以外にTOEICなどの基準は設けていないので、内定者の中にはTOEIC400点台という人もいます。ただ、入社5年目の昇格の際にはTOEIC730点以上というバーがあり、海外駐在の条件にもなっているので、それまでにその基準はクリアする必要があります。
語学ができるに越したことはないですが、語学力は一つのツールであり、それだけではビジネスはできません。留学経験はその中身が重要です。当社を受験する人に占める留学経験者は年々増えている印象があり、1カ月とかの短期留学も含めたら半分以上の学生が経験しているのではないでしょうか。面接では留学の動機や留学中に何を考えながらどのような経験をしてきたのか、中身やプロセスを聞いています。海外に住んでいた人が語学が得意なのは当たり前です。その背景も含めて人を見るようにしています。
――内定者が競合する企業は?
他の商社が一番多いですね。どこに行ってもできることはそれほど変わらないからと悩む人が多いようですが、最終的には自分に合う社風であったり、一緒に働きたいと思える人がいたり、ということで決める人が多い印象があります。その他の業界だと、その学生が大事にしている就活の軸によって競合は違います。グローバルに働きたい人は海運や海外展開に積極的なメーカーなど、自分で何かをつくっていくことに興味を持っている人は広告やマスコミ業界、事業や経営に興味がある人はベンチャーやコンサルといった感じです。
――起業したいという人はいずれ独立するかもしれませんが、それでも採用しますか。
入ってしばらくすると(もしくは辞めてから気付いて戻ってくる人もいますが)、ベンチャー企業を立ち上げて自分でやるより、丸紅のネームバリューや信用力、資金力、社内に蓄積されている様々なノウハウや管理部門の機能といったリソースを使ってベンチャー的なビジネスを丸紅の中でやる方が簡単で、もっと大きなことができるとわかる。また、商社は連結経営の時代で、当社も440社を超えるグループ会社を全世界に保有しその経営を牽引する役割があるため、経営という視点についても社内で経験を積んでいくことができます。そう考えると、起業や独立したいと思っている人も「いずれ辞めるかもしれない」というより「いずれ丸紅の仕事にはまるかもしれない」という気持ちで見ています。
■丸紅カラー
――「人の三井、組織の三菱」と言われますが、丸紅のカラーは?
学生や内定者からは「丸紅には個性豊かな社員がいる」「皆さん熱さはあるが、それを前面に押し出すよりも内に秘めている感じの人が多い」「温かい雰囲気で親しみやすい人が多い」などと言われます。よく商社は体育会系だと言う人もいますが、当社は「がつがつした体育会系という感じがしない」とよく言われます。取引先からは「丸紅さんは他社より若い人が出てくるね」とも言われるので、若手に任せる社風もあるのだと思っています。あと私自身が感じているのは、同期はもちろんのこと、先輩後輩や他部署の人も含め、社員同士仲が良いという点です。組織力よりは個性を大切にしている会社ですが、そういった人と人との連携やコミュニケーションはよく取れているのが丸紅の特徴だと思います。他商社から転職してきた者がいますが、彼曰く、上司との距離の近さ、意見の言いやすさが違うと。それも丸紅の自由闊達さが表れているところではないかと思います。
――弱みはありますか。
他の商社と比べて人数が決して多くない中、業績を伸ばして差を縮め、業容を拡大してきているので、人が足りていない状況があります。現状の陣容を強化していく人材育成で補ったり、若手や中堅の頑張りでカバーしたりしていますが、新卒採用、キャリア採用の強化も図っています。
あとはブランドマネジメントも課題の一つです。「丸紅」と聞いて、どういう会社なのかがパッとイメージできるような、企業のイメージ作りを採用活動の中でも行っていければと考えています。
――他の総合商社との違いをどうアピールしますか。
各商社ともそれぞれ強い事業分野と弱い事業分野があります。例えばうちでいえば穀物や電力が強いという特徴はありますが、会社全体で見たビジネスの領域や規模、取扱商品などに大きな違いはなく、どこへ行ってもやれる仕事はほぼ同じかと思います。大切なのは、丸紅の良さ、特徴をきちんと理解してもらい、それに共感してくれる学生に入社してもらうことだと考えています。我々が求めている「己の強さで世界に挑んでいきたい」という大きな志やチャレンジスピリットを持っている人、「丸紅のような若いうちから任され、チャレンジさせてくれる会社がいい」と考えている人、「自由闊達な雰囲気の中、個性を生かして伸び伸びとやっていきたい」と考えている人を増やしていきたい。そのためには、我々もありのままを伝えることが大事だと考え、採用活動をしています。
――採用についての課題は?
先ほどのブランドマネジメントの部分になりますが、わかりにくい総合商社というものをいかにわかりやすく伝えていくか、差別化が難しい総合商社の中での特徴、違いをどう伝えていくかを常に考えています。丸紅の社風などの特徴をわかってもらうためには、社員に会ってもらうのが一番わかりやすいので、セミナーや説明会を活発に行うとともにOB・OG訪問を促進しているんです。
――研修制度について教えてください。
商社の仕事は、まさに人がビジネスをつくり出していく源泉であり、最大の資産は過去も未来も「人材」にあります。人を強くしていくことが会社の成長につながっていくため、人材育成には非常に力を入れています。2013年度から始まった3カ年の中期経営計画でも「人材戦略の更なる推進」を経営課題の一つに掲げ、研修制度の充実を図るとともに多様な経験施策を導入し、「若手を早く、大きく育てる」ことに注力しています。特に全ての総合職に対して、入社7年以内に少なくとも半年以上の海外勤務を経験させることを必須化しており、若いうちに海外経験、現場経験をさせることで成長を促そうとしています。
■やりがいと厳しさ
――総合商社の仕事は、大変忙しいんですよね。休みは取れますか。
プライベートな時間が全く持てないほどではありませんが、どちらかと言えば忙しい業界に入るでしょうね。たとえば案件が立て込んでいたり、大きなプロジェクトの入札前だったり、急なトラブルがあったりした時には、土日に出社したり、毎日終電間際まで働いたり、時には終電を逃してもやらなければいけないこともあります。でもそれが1年間ずっと続くわけではない。入社1年目は周りが見えない中で、上司に言われるがままにやるしかないこともあるかもしれませんが、2年、3年と経験を積んでいくうちに全体が見えるようになり、自分の裁量も増え、自らある程度仕事を組み立てられるようになってきます。学生時代に比べると圧倒的にプライベートな時間は少なくなりますが、みなオンとオフをうまく切り分け、時間を大切に使っています。仕事をばりばりやるためにも、オフの充実は重要です!
――商社の仕事の厳しさとやりがいについて。
商社の仕事は「グローバル」「投資」など華やかなイメージがあるかもしれませんが、結構地道な仕事、泥臭い仕事もあります。数字の取りまとめなどの細かい実務、社内で承認を得たり、報告したりするための文書作成、様々なアレンジの業務、様々な現場に出て行ってのプロジェクト管理や問題対応など、数え上げたら切りがありませんが、すべてが必要な仕事です。また我々のビジネスは、信用や付加価値がないと存在意義がありません。顧客、取引先、消費者に対する責任を果たすことで信用を得、付加価値を提供することで信用を高めていきます。信用を維持することは簡単ではなく、失うようなことは絶対にしてはいけない。そういった厳しさもあります。
やりがいは、自分が担当しているビジネスが社会につながり、その貢献が感じられることであったり、自分自身の成長が感じられることであったり、人から感謝されることであったり、人によって様々です。食料でもライフスタイルでも化学品でも、自分の扱っている商材が最終的に何かしらの製品等になって、人々の生活を豊かにすることにつながっている。金属やエネルギーなら自らのビジネスが日本への資源の安定供給に寄与している。電力、プラントやインフラ関係の仕事なら、自分の仕事がその国や地域の発展に寄与したり、現地の雇用を生み出すことになったり……。みな社会的意義のある仕事をし、現地や取引先の人々に感謝されている。そういった経験を通して自分も成長し大きくなる。そんなやりがいがあるのだと思います。
■毛利さんの仕事
――毛利さんはどんな就活をしたのですか。
入社した1996年当時はネットを使った採用は一般的ではなく、セミナーや説明会も今ほど盛んには行われていませんでした。採用ホームページを開設している会社もほぼなく情報も限られていたので、OB・OG訪問が一番の情報収集の手段という時代でした。私は体育会だったので、クラブのOBがいる興味のある会社をとりあえず回って、幅広く話を聞きにいきました。仕事内容を聞くと、どの会社も非常に面白そうで、これでは志望先が固まらないなと危機感を感じ、自らの学生時代を振り返って一番やりがいを感じた「自らの成長」に軸を置いて会社を見て行きました。どの業界のどの会社ならやりがいのある仕事ができ、仕事を通して視野が広がり、自分自身が成長していけるか。そうした視点で一番魅力的に映ったのがグローバルなフィールドでビジネスができる商社でした。また、自らがたどり着きたいイメージの40代、50代の人たちが一番多かったのも商社です。40~50代になっても元気にばりばりとやりがいを持って仕事をしている人が多い。なぜ商社がそういう業界なのか。自分なりに出した答えは、商社の仕事はいつまでたっても考え続けることが求められる仕事だということです。常に世界の政治、経済、社会、そして自らの属する業界や商材の動向、取引先や世の中の状況やニーズを見ながら、将来を見据え、自らの仕事を常に変えて行く。新しいビジネスを作り出して行く。そんな仕事に思えました。そんな厳しい仕事である分、やりがいもあり、常に張りがある。だからこそ成長もしていける。そう感じたので商社の道を選びました。
――総合商社の中で、なぜ丸紅に?
当時は非常に商社の人気が高く、人気企業ランキングの上位10社以内に商社が5~6社入っている時代で、どの商社にも魅力を感じていました。商社各社の差別化は非常に難しく悩んでいましたが、何となく各社の空気感の違いというか、社風の違いを感じていた中で選考が進み、一番早く内定が出た丸紅に決めました。そこで丸紅の雰囲気が合うと感じていなかったら、おそらくそこで迷ったのではないかと思いますが、迷いなくすっと決めることができました。何名かのOBにあった印象や選考を通して、温かくかつ自然体な雰囲気、のびのびと楽しそうに社員の皆さんがやっている感じが直感的に合うと感じていたのだと思います。
――入社後の仕事の経歴を教えてください。
食料やライフスタイルをやりたくて営業を志望していましたが、人事部に配属されました。正直驚きましたが、人事部の仕事も面白く、やりがいはあったので、入社して10年目ぐらいまでは営業と人事、どちらでもやりがいは感じられると言っていたところ、その後もずっと人事畑で今に至ります。人事部には、採用以外にも給与や福利厚生関連、人事評価や異動の仕事、そして人事制度の企画・立案や従業員組合対応など本当に幅広く、それらを一通り経験した後、2008年から4年間はロンドンにある丸紅欧州会社で人事総務のマネジャーを担い、2012年に戻ってきて現在のポジションです。
 ■採用実績、エントリー数
■採用実績、エントリー数


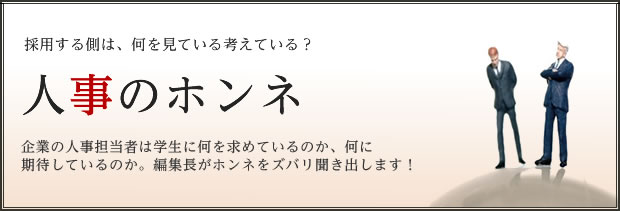
 ■総合職と一般職
■総合職と一般職
 ■英語力とライバル他社
■英語力とライバル他社









