
■寺澤さんの就活
──寺澤さんの就活について教えてください。
私は2014年入社で現在12年目 です。2013年に就活をして、見ていた業界は通信、金融、鉄道とマスコミとバラバラでした。学生時代は陸上の短距離走をやっていましたね。
──なぜ、通信業界を選んだのですか?
すごくシンプルに言うと、自分が一番身近でお世話になっていると感じたからです。中学生のときから携帯電話を持っていて、ずっと手元にあるなあと。金融や鉄道も身近な存在で、なおかつどれも世の中の支えになり、影響力も大きいので、通信、金融、鉄道を見ていました。マスコミはアナウンサーを受けていましたが、選考とKDDIの最終面接がかぶって、KDDIを選択しました。
──KDDIの他に内定は取られたんですか?
いただいていましたが、これから新しいこととか、ワクワクすることがKDDIだったらできるだろうな、世の中に出していくだろうな、と思ったのが決め手でした。あとは社員と会う中で、この人たちと働きたいなと感じたのも大きかったですね。
──どういう社員、社風と感じていましたか。
当時はまだKDDI版ジョブ型制度は導入前でしたが、若いうちから活躍できる会社だと感じました。シンプルに言うと、社員のみなさんがすごくかっこよく映ったんですよね。その当時、入社3年目の男性社員がいたのですが、いい意味ですごく自信を持って仕事を語っているし、「3年目でこんなになれるんだ」「こんなかっこいい人がいるんだな」と衝撃を受けました。
それから、KDDIは新しいサービスをどんどん世に出していくだろうな、と思いました。私が中学校1年生のときにauが携帯の「着うた」を始めたんですよ。それでauの携帯がほしくなって、カタログを各社調べたところ、auはダブル定額という、パケットをいくら使っても料金が変わらないというサービスも初めて出していました。「新しいことをやる会社なんだな」と、すごく印象に残っていました。
──実際入ってみて、社風はいかがでしたか?
私個人は、若いときからいろいろとやらせてもらっています。初期配属で和歌山に行ったときも、若手中心の支店でした。支店長も40歳ぐらいで、若い人の意見を尊重してくれ、ガンガン営業をやらせてもいました。入社3年目で仙台に行ったときは新店舗の立ち上げを担当し、マネジメントスキルも身につけることができました。
──就活のときにやったことで、よかったと思われることはありますか?
とにかく自己分析ですね。「周りを巻き込んで、どこの組織でも目標に向けて一翼を担う人間です」と伝えたと思います。
──どうやって分析されたんですか?
キャリアセンターに足繁く通い、恥ずかしさを捨てて、部活の仲間とも話し合いました。陸上は自分との戦いですが、タイムと向き合って、目標をクリアするというのは、実は周囲との関わりが大事です。部として共通の目標に取り組み、自分のモチベーションを高めることができます。仲間と話し合って、「自分のやりたい会社はここだよね」判断軸がぶれなくなりました。
──それがまさにKDDIの求める人財とピタッと合ってという。
合っていましたね。確かに。それが採用にもつながっていればいいなと思います。
 人気企業の採用担当者に編集長が直撃インタビューする「人事のホンネ」。携帯キャリア「au」などを展開する大手通信会社のKDDIの後編をお届けします。2020年に導入したKDDI版ジョブ型人事制度の目的は、変革の時代にあわせ社員1人1人がプロフェッショナルになっていくこと。実力本位の評価制度で、初任給から差がつくこともありますが、専門家としてのスキルアップだけでなくKDDI人としての人間力も評価の対象としています。KDDIで働くやりがい、自身の就活期の体験についてもくわしくうかがいました。(編集長・福井洋平)
人気企業の採用担当者に編集長が直撃インタビューする「人事のホンネ」。携帯キャリア「au」などを展開する大手通信会社のKDDIの後編をお届けします。2020年に導入したKDDI版ジョブ型人事制度の目的は、変革の時代にあわせ社員1人1人がプロフェッショナルになっていくこと。実力本位の評価制度で、初任給から差がつくこともありますが、専門家としてのスキルアップだけでなくKDDI人としての人間力も評価の対象としています。KDDIで働くやりがい、自身の就活期の体験についてもくわしくうかがいました。(編集長・福井洋平)


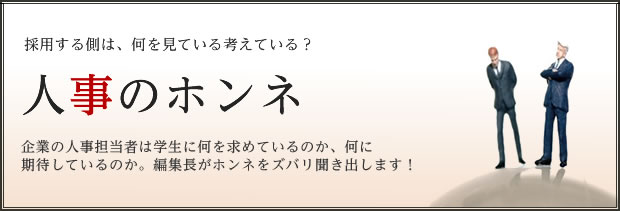
 ──なぜ、そのためにジョブ型制度を導入したのでしょうか。
──なぜ、そのためにジョブ型制度を導入したのでしょうか。 ■評価の方法
■評価の方法 ■社内副業
■社内副業 ■寺澤さんの就活
■寺澤さんの就活 ■KDDIの働きやすさ
■KDDIの働きやすさ









