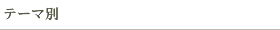■農業とカーボンクレジット
──前編では、山下さんがいま携わっているカーボンクレジット事業について詳しくうかがいました。さまざまな会社にカーボンクレジットを提案されているとのことですが、これまでのご提案で手応えのあった案件はありますか。
まだ本当に種まきの段階ですが、ある大企業に対して「御社だったらこういうことができるかもしれません。一緒にやっていきましょう」という提案をしに行ったところ、それまでは接点のなかった事業部やサステナビリティ室、海外事業部とも接点を持てるようになりました。複数の部署と接点を持てることで、IRや有価証券報告書、ホームページで見る以上の情報が手に入ります。その情報から、どういった提案を持っていくとさらに企業が発展しやすいのかと考えられるようになり、我々のビジネスに生きる可能性がすごく高くなりました。
まだそうした例は数社ですが、今度は種まきから芽を出す作業をしていきたいと思っています。
──その会社へ提案されたのは、何がきっかけだったのでしょうか。
その会社様が「生産者がカーボンクレジットを簡単に作成するためのシステムをつくった」というプレスリリースを出されたことがきっかけでした。その会社は農業関係のビジネスもしていますが、実は、農業からもカーボンクレジットは創出できます。CO₂を減らすには、例えば米作りの過程で「中干し」といって水田の水を抜くのですが、この期間を伸ばすという方法があります。ただ日本の農家は一軒一軒の面積が小さく、大型のプレーヤーにはなりにくい。またカーボンクレジットをつくったとしても一軒一軒の農家がそれを認証して、申請してとなると経費のほうが高くつき、赤字になってしまいます。そのため、農家を取りまとめてカーボンクレジットの申請事務代行をするスタートアップ企業もあります。
この会社は農業関連の生産管理アプリを立ち上げ、非常に普及しているのですが、これを使うことでカーボンクレジットの申請がしやすくなるのです。農業関係のカーボンクレジットの大半がこの会社に集まるくらいのポテンシャルがあると感じ、提案をしに行きました。
──その会社は、証券化したカーボンクレジットをどこで売ろうとしているのですか。
1つはこの会社が工場などで排出するCO₂にあてることも検討しているそうです。また、これは農業支援のカーボンクレジットなので、食品、農業、林業といった企業が社会貢献のためにカーボンクレジットを買おうとしています。 もちろん、数多くあるみずほの取引先も販路となり得ます。
我々は金融機関の中で唯一、1都1道2府43県に支店があります。地方創生に取り組んでいく中で、農業はポイントになると思います。カロリーベースの食料安全保障、耕作放棄地といった問題が深刻化しないためにも、カーボンクレジットは生産者が農作物に付加した収入を得られるため、持続的に農業ができる取組の中で非常に大事になってくると信じています。
 SDGs(持続可能な開発目標)関連の業務に携わっている若手・中堅社員に直撃インタビューする「SDGsに貢献する仕事」第23回。3大メガバンクの一角、日本を代表する金融機関であるみずほフィナンシャルグループ(FG)の後編です。「パラダイムシフトを起こしたい」という目標で就職活動を行い、若いうちに力がつけられる環境と考えてみずほFGを就職先に選んだ山下さん。カーボンクレジット事業推進に携わるいま、日本でパラダイムシフトを起こせる可能性が一番高いところにいると感じているといいます。就活生へのメッセージも聞きました。(編集長・福井洋平)
SDGs(持続可能な開発目標)関連の業務に携わっている若手・中堅社員に直撃インタビューする「SDGsに貢献する仕事」第23回。3大メガバンクの一角、日本を代表する金融機関であるみずほフィナンシャルグループ(FG)の後編です。「パラダイムシフトを起こしたい」という目標で就職活動を行い、若いうちに力がつけられる環境と考えてみずほFGを就職先に選んだ山下さん。カーボンクレジット事業推進に携わるいま、日本でパラダイムシフトを起こせる可能性が一番高いところにいると感じているといいます。就活生へのメッセージも聞きました。(編集長・福井洋平)


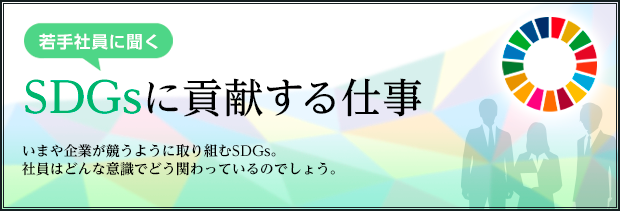
 ■農業とカーボンクレジット
■農業とカーボンクレジット ■仕事の大変さとおもしろさ
■仕事の大変さとおもしろさ ■山下さんの就活
■山下さんの就活 ■入社後の仕事
■入社後の仕事 ■事業開発の部署への異動
■事業開発の部署への異動 (写真・2024年7月3日にみずほ丸の内タワーで開催したみずほカーボンクレジットセミナーの様子=みずほFG提供)
(写真・2024年7月3日にみずほ丸の内タワーで開催したみずほカーボンクレジットセミナーの様子=みずほFG提供)