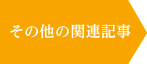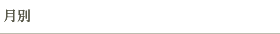アセトアミノフェンの使用最低限に、とアナウンス
 アメリカのトランプ大統領が、解熱剤などに含まれる「アセトアミノフェン」を妊婦に使うと子どもが自閉症になるリスクが高まるとして、使用を最低限にとどめるようアナウンスしました。ただ、アセトアミノフェンと自閉症の関係は科学的な評価が定まっているとはいえない段階で、医療系学会は相次ぎ反対の声明を出しています。
アメリカのトランプ大統領が、解熱剤などに含まれる「アセトアミノフェン」を妊婦に使うと子どもが自閉症になるリスクが高まるとして、使用を最低限にとどめるようアナウンスしました。ただ、アセトアミノフェンと自閉症の関係は科学的な評価が定まっているとはいえない段階で、医療系学会は相次ぎ反対の声明を出しています。
トランプ大統領は9月の国連総会で、気候変動対策に対して「詐欺」と言い放つなど、過激な発言を加速させています。これらの発言からは、トランプ大統領が、言いたいことを十分な科学的裏付けなく発言する傾向が強く読み取れます。大国のトップが科学軽視の姿勢を続けることは、世界の行く末にも大きな影響を及ぼすでしょう。トランプ氏発言の何が問題か、今回の発言を機に考えてみたいと思います。
(写真はiStock)
アセトアミノフェンと自閉症増加は「因果関係」あるか?
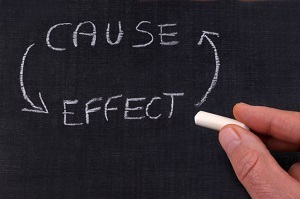 アセトアミノフェンは、日本では普通の薬局で買うことができる解熱鎮痛剤の「バファリン」や「ノーシン」などにつかわれる、ごく一般的な解熱鎮痛成分です。ほかの解熱剤に比べてやや効き目が弱いとされていますが、胃への負担がやさしく、また副作用が少なく子どもや妊婦にもつかいやすいという特徴があり、幅広く使われています。
アセトアミノフェンは、日本では普通の薬局で買うことができる解熱鎮痛剤の「バファリン」や「ノーシン」などにつかわれる、ごく一般的な解熱鎮痛成分です。ほかの解熱剤に比べてやや効き目が弱いとされていますが、胃への負担がやさしく、また副作用が少なく子どもや妊婦にもつかいやすいという特徴があり、幅広く使われています。
では実際に、妊婦がアセトアミノフェンを服用すると子どもが自閉症になるリスクは高くなるのでしょうか。今回の発言で根拠とされているのは米マウントサイナイ医科大学や米ハーバード大学が8月に発表した論文です。複数の発表済み論文の調査結果をまとめて分析する方法で、アセトアミノフェンと自閉症の関連性を裏付ける根拠があるとしたのです。一方で、論文は「研究の限界により因果関係を確定することはできなかった」ともしています。
ここで大切なキーワードが「因果関係」です。2つのことがらの関係性を考えるとき、一方のことがらが「原因」、もう一方のことがらが「結果」になるとき、この2つのことがらには「因果関係」があるということになります。水を飲む(原因)→のどの乾きがなくなる(結果)というのが、因果関係です。
(写真はiStock)
因果関係の認定には慎重に
一方で、あることがらが、もう一方のことがらに連動して動くとき、この2つのことがらには「相関関係」がある、といいます。ここで注意しなければいけないのは、「相関関係」があるのに「因果関係」はない、というケースがあることです。
たとえば、アメリカのある州ではマーガリンの消費量と離婚率に高い相関関係があったそうです。マーガリンの消費が多い年は離婚率が高く、低い年は離婚率も低かったのです。ただ、マーガリンをたくさん食べると夫婦は離婚したくなる、離婚した夫婦はたくさんマーガリンを使うようになるといったことは証明されていません。つまり、2つのことがらを「原因」と「結果」で結びつけることはできないのです。
アセトアミノフェンと自閉症の子ども増加についても、仮に相関関係があったとしても、本当に「因果関係」があるのかは慎重な判断が必要になります。自閉症が増えている理由はアセトアミノフェンではない可能性もあるからです。実際、スウェーデンの約250万人の子どもを対象にした調査では、関連性に否定的な結果も出ています。
自閉症と診断される子どもの数の増えていること自体についても、議論の余地があるとされています。米疾病対策センター(CDC)のデータでは、米国の8歳児の1千人に6.7人(2000年)から32.2人(2022年)と確かに大きく増えています。ただ、このCDC自身が自閉症の増加は定義の変更や診断機会の増加が影響した可能性があると指摘しています。
発熱放置すれば妊婦にとって危険に
 米国産科婦人科学会は会見直後、20年以上にわたる研究でアセトアミノフェンと自閉症の関連性は認められていないとして、「妊娠中の痛みや発熱を管理する上で、重要かつ安全な選択肢であり続けている」とする声明をSNSで発表しています。またアメリカのテレビ放送局CNNは、妊婦が副作用のある他の解熱剤を使ったり発熱を放置したりすることが、胎児や妊婦にとって危険な場合があると警告しています。
米国産科婦人科学会は会見直後、20年以上にわたる研究でアセトアミノフェンと自閉症の関連性は認められていないとして、「妊娠中の痛みや発熱を管理する上で、重要かつ安全な選択肢であり続けている」とする声明をSNSで発表しています。またアメリカのテレビ放送局CNNは、妊婦が副作用のある他の解熱剤を使ったり発熱を放置したりすることが、胎児や妊婦にとって危険な場合があると警告しています。
前述のように、アセトアミノフェンはもともと副作用が少ないため処方しやすく、妊婦にとってはありがたい存在でした。その使用を制限するような発言は、妊婦や子どもの体調に大きな影響を与えるでしょう。「因果関係」を裏付ける研究結果がない段階でのトランプ大統領の発言は果たして許されるものなのか、よく考える必要があります。
「温暖化は史上最大の詐欺」
 トランプ氏は9月23日にアメリカのニューヨークで開かれた国連総会で演説し、そのなかで気候変動問題を「史上最大の詐欺(con job)」と断じました。以前からトランプ氏は「気候変動はでっちあげ」といった主張を繰り返し、今年1月の就任直後には気候変動対策の国際ルール「パリ協定」からの脱退を表明。太陽光や風力発電への補助金を減らすなど、アメリカの気候変動対策を後退させてきています。
トランプ氏は9月23日にアメリカのニューヨークで開かれた国連総会で演説し、そのなかで気候変動問題を「史上最大の詐欺(con job)」と断じました。以前からトランプ氏は「気候変動はでっちあげ」といった主張を繰り返し、今年1月の就任直後には気候変動対策の国際ルール「パリ協定」からの脱退を表明。太陽光や風力発電への補助金を減らすなど、アメリカの気候変動対策を後退させてきています。
気候変動については、世界中の科学者でつくる国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が2021年、人間の活動によって温暖化が起きたことは「疑う余地がない」と結論を出しています。また、CO2などの温室効果ガスが排出されつづけることで更なる地球温暖化がもたらされ、「気象・気候の極端現象が拡大」すること、温室効果ガスの削減対策などが遅れることで将来の被害やリスクが増大することも指摘しています。アメリカが排出する温室効果ガスは世界全体の1割と中国に次いで多く、アメリカが取り組みを後退させれば温暖化対策そのものが停滞するでしょう。
アメリカは7月下旬に、現在の気候変動の科学に疑問を投げかける報告書を公表。気候変動に伴う気温上昇による経済的な損害は少なく、積極的な温室効果ガスの削減対策は不利益になる可能性があるなどとも主張しています。ただこの報告書には誤りも多く含まれていることが指摘され、論文を引用されたある学者は「数字と研究の一部の『チェリー・ピッキング』(都合のよい主張だけを選ぶこと)をしている」と述べています。気候変動についての研究は長年積み重ねられてきており、その議論をひっくり返すにはやはり相応のしっかりとした科学的裏付けが求められます。トランプ氏の行動は、重大な結果をもたらす割には科学的根拠が薄弱と言わざるをえません。
(写真・米ニューヨークの国連本部/朝日新聞社)
エビデンスに基づく政策立案=EBPMに注目
トランプ氏の科学軽視の姿勢については、4月の就活ニュースペーパー「時事まとめ」でも取り上げました。また、トランプ氏は8月にはアメリカの政策判断の指標となる「雇用統計」が急減速したことに不満を爆発させ、この統計を所管する労働省幹部を解雇しました。トランプ氏は、この幹部が昨年の大統領選で民主党候補のカマラ・ハリス前副大統領が有利になるよう統計を偽装したと、SNSで根拠を示さず非難しています。
統計や実験など、証拠(エビデンス)に基づく政策立案=EBPMが近年注目されています。多くの人に影響を与える政策の立案が、エビデンスのない個人の思い込みでつくられていく影響ははかりしれないものがあります。トランプ氏の主義、主張には賛否両論があると思いますが、その主張に見合ったしっかりとした根拠があるかどうかについては、厳しくチェックしていく必要があるでしょう。
◆朝日新聞デジタル版のベーシック会員(月額980円)になれば毎月50本の記事を読むことができ、スマホでも検索できます。スタンダード会員(月1980円)なら記事数無制限、「MYキーワード」登録で関連記事を見逃しません。大事な記事をとっておくスクラップ機能もあります。お申し込みはこちらから。
 アメリカのトランプ大統領が、解熱剤などに含まれる「アセトアミノフェン」を妊婦に使うと子どもが自閉症になるリスクが高まるとして、使用を最低限にとどめるようアナウンスしました。ただ、アセトアミノフェンと自閉症の関係は科学的な評価が定まっているとはいえない段階で、医療系学会は相次ぎ反対の声明を出しています。
アメリカのトランプ大統領が、解熱剤などに含まれる「アセトアミノフェン」を妊婦に使うと子どもが自閉症になるリスクが高まるとして、使用を最低限にとどめるようアナウンスしました。ただ、アセトアミノフェンと自閉症の関係は科学的な評価が定まっているとはいえない段階で、医療系学会は相次ぎ反対の声明を出しています。


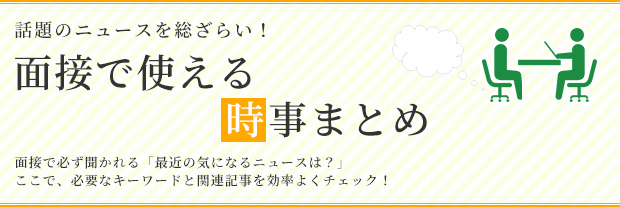
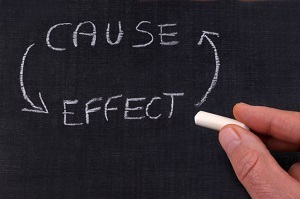 アセトアミノフェンは、日本では普通の薬局で買うことができる解熱鎮痛剤の「
アセトアミノフェンは、日本では普通の薬局で買うことができる解熱鎮痛剤の「 米国産科婦人科学会は会見直後、20年以上にわたる研究でアセトアミノフェンと自閉症の関連性は認められていないとして、「妊娠中の痛みや発熱を管理する上で、重要かつ安全な選択肢であり続けている」とする声明をSNSで発表しています。またアメリカのテレビ放送局
米国産科婦人科学会は会見直後、20年以上にわたる研究でアセトアミノフェンと自閉症の関連性は認められていないとして、「妊娠中の痛みや発熱を管理する上で、重要かつ安全な選択肢であり続けている」とする声明をSNSで発表しています。またアメリカのテレビ放送局 トランプ氏は9月23日にアメリカのニューヨークで開かれた国連総会で演説し、そのなかで気候変動問題を「史上最大の詐欺(con job)」と断じました。以前からトランプ氏は「気候変動はでっちあげ」といった主張を繰り返し、今年1月の就任直後には気候変動対策の国際ルール「
トランプ氏は9月23日にアメリカのニューヨークで開かれた国連総会で演説し、そのなかで気候変動問題を「史上最大の詐欺(con job)」と断じました。以前からトランプ氏は「気候変動はでっちあげ」といった主張を繰り返し、今年1月の就任直後には気候変動対策の国際ルール「