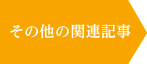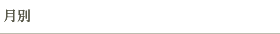「中野サンプラザ」再開発計画が頓挫
 東京都中野区、JR中野駅の前にそびえたつ「中野サンプラザ」。コンサート会場などとして親しまれ、2023年に営業を終了し解体、再開発が決まっていましたが、現在も工事は行われていません。当初予定されていた再開発計画が、建設費が高くなりすぎて頓挫したためです。今後サンプラザがどうなるのか、見通せない状況が続いています。
東京都中野区、JR中野駅の前にそびえたつ「中野サンプラザ」。コンサート会場などとして親しまれ、2023年に営業を終了し解体、再開発が決まっていましたが、現在も工事は行われていません。当初予定されていた再開発計画が、建設費が高くなりすぎて頓挫したためです。今後サンプラザがどうなるのか、見通せない状況が続いています。
世界的な資材の高騰に円安がくわわり、人手不足もあって、建設にかかるコストは年々上昇しています。みなさんの生活はもちろん、こういった大きな都市計画やイベントの進捗に及ぼす影響も大きくなっています。今後の社会人生活やビジネスを考えるうえでも避けては通れない「建設費」の問題について考えてみましょう。(編集部・福井洋平)
(写真・工事用のフェンスで封鎖された中野サンプラザ=2025年3月27日/写真はすべて朝日新聞社)
工事費が900億円値上がり
 朝日新聞デジタル版では、中野サンプラザ再開発が止まった経緯について検証記事を連載しています。記事によりますと、大手デベロッパーの野村不動産が再開発計画を請け負い、オフィスや商業施設、住宅が入る超高層ビル建設を予定していました。しかし当初数千億円規模だった事業費が2カ月間で900億円も値上がりし、計画の見直しを余儀なくされたというのです。中野区の人口約34万人で割ると、1人あたり26万円の値上がりです。
朝日新聞デジタル版では、中野サンプラザ再開発が止まった経緯について検証記事を連載しています。記事によりますと、大手デベロッパーの野村不動産が再開発計画を請け負い、オフィスや商業施設、住宅が入る超高層ビル建設を予定していました。しかし当初数千億円規模だった事業費が2カ月間で900億円も値上がりし、計画の見直しを余儀なくされたというのです。中野区の人口約34万人で割ると、1人あたり26万円の値上がりです。
工事を担うゼネコンが、工事費が900億円値上がりするという見積もりを野村不動産に出してきたのは2024年8月末。記事によると設備工事費は想定の3倍、エレベーター工事費は2倍となり、さらにいわゆる「2024年問題」で人件費もはねあがっていました。2024年問題は就活ニュースペーパーでも何度か取り上げていますが、トラック運転手などの残業時間が規制され、輸送力が不足するという問題のことです。野村不動産側もある程度工事費が上がることは予想していましたが、「過去に前例がない」と衝撃を受けたといいます。野村不動産はゼネコンに見積もり見直しの交渉をしたものの、ゼネコン側も実際に工事をする専門会社=サブコンから上がってきた見積もりが想定以上に高く、大幅な値下げは難しいと告げたそうです。
(写真・2023年7月に閉館した「中野サンプラザ」=2024年9月25日)
「タワーマンションだ」批判が噴出
野村不動産はビルに入る住宅の割合を4割から6割に増やし、オフィスを4割から2割に減らして収支を改善する計画をたてました。これにより、採算性が確保されるというもくろみでした。しかしこの計画が区議会に対して明らかになると、区議から「タワーマンションだ」と批判が噴出したのです。中野サンプラザは長年コンサートやイベントの会場として利用され、中野区のランドマークとしても親しまれています。その跡地がたんなる住宅地になってしまうということは、区民感情としても受け入れられない――という主張です。結果的に今年3月に野村不動産の案は拒否され、中野区長は「中野サンプラザのDNAを継承し、区民に愛されるような施設が実現できるよう取り組んでまいりました」としたうえで、野村不動産の案は「必ずしも十分ではない」というコメントを出しました。
事業が白紙になったことで、建て替えの時期は大幅に遅れることになります。サンプラザをそのまま使い続けるという意見もあるようですが、区は修繕にも100億円以上かかるという試算を示し、民間事業者と組んでの再開発という考え方は変えない方針です。建設費が上がったままでどう計画を見直すのか、今後の動きが注目されます。
全国各地で市民生活に大きく影響
 建設費の高騰は各地でさまざまな問題につながっています。朝日新聞の最近の記事を見ても、
建設費の高騰は各地でさまざまな問題につながっています。朝日新聞の最近の記事を見ても、
・兵庫県の三田市は、市民病院と近隣の済生会兵庫県病院(神戸市北区)を統合する計画をすすめているが、今年2月に決まった基本計画では整備費は521億円となり、2022年度に策定した整備費254億円から建設費高騰などの影響で倍増。三田市が市税で負担する額も68億円→198億円と3倍近くにふくれあがり、今後「市民サービスが削られることになる」という指摘も出ている。
・茨城県結城市の小学校5校を統合再編する計画で、建設費の一部13億円が盛り込まれた予算案が、多額の財政負担を理由に市議会で否決された。結城市に限らず、建設資材や労務費の高騰で建設予算がふくらみ、学校の新設計画を見直す動きが各地で相次いでいる。
・2027年に横浜市で開かれる国際園芸博覧会(GREEN×EXPO)の会場建設費について、博覧会協会は3月、これまでの320億円から97億円増え、最大417億円になると公表した。建設資材や人件費の上昇などが原因だという。横浜市は、会場建設費が大幅に増額し批判のまととなった大阪・関西万博を引き合いに、国際園芸博への批判が高まることを横浜市は警戒している。
など、全国各地で病院や学校、国際イベントといった市民生活にも関わる建築物に影響が出てきています。
(写真・国際園芸博の公式マスコット=2024年3月19日)
都心にタワマン、地方インフラはやせ細る?
建設費の高騰は、
・ウクライナ戦争に端を発する世界的な資材原材料の高騰
・円安による日本国内での資材価格上昇
・人手不足、2024年問題による残業規制による、人件費の高騰
といった要因で進行しています。為替はトランプ政権が登場したことで多少円高方向に進んではいますが、資材高、人件費高騰は当面おさまることはないでしょう。高騰する建設費を回収するために、人気の高い都心部の開発や、投資目的の購入も見込めるタワーマンションの建設ばかりに資金が投じられるようになるかもしれません。中野サンプラザをめぐる問題では、この流れがはっきり見えたと言えるでしょう。この先には、都心にどんどんタワーマンションがつくられ、反面、地方のインフラはどんどんやせ細っていくという未来がみえます。
野村不動産のようなデベロッパーや、大型建設にたずさわるゼネコンを希望される方はもちろん、街づくりにかかわりたい方、イベントづくりをしてみたい方など、建設費の問題は非常に幅広い業界にかかわってきます。公共施設の建て替えを通じ、みなさんの生活にも深くかかわってくる問題です。ぜひ建設費高騰の問題について、今後も意識してニュースをチェックしてください。
◆朝日新聞デジタル版のベーシック会員(月額980円)になれば毎月50本の記事を読むことができ、スマホでも検索できます。スタンダード会員(月1980円)なら記事数無制限、「MYキーワード」登録で関連記事を見逃しません。大事な記事をとっておくスクラップ機能もあります。お申し込みはこちらから。
 東京都中野区、JR中野駅の前にそびえたつ「中野サンプラザ」。コンサート会場などとして親しまれ、2023年に営業を終了し解体、再開発が決まっていましたが、現在も工事は行われていません。当初予定されていた再開発計画が、建設費が高くなりすぎて頓挫したためです。今後サンプラザがどうなるのか、見通せない状況が続いています。
東京都中野区、JR中野駅の前にそびえたつ「中野サンプラザ」。コンサート会場などとして親しまれ、2023年に営業を終了し解体、再開発が決まっていましたが、現在も工事は行われていません。当初予定されていた再開発計画が、建設費が高くなりすぎて頓挫したためです。今後サンプラザがどうなるのか、見通せない状況が続いています。


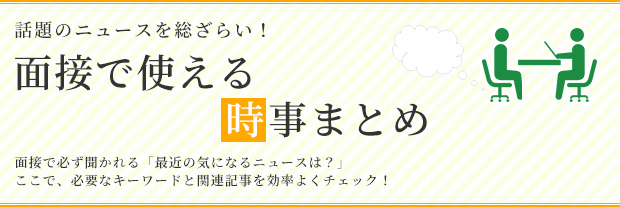
 朝日新聞デジタル版では、中野サンプラザ再開発が止まった経緯について検証記事を連載しています。記事によりますと、大手
朝日新聞デジタル版では、中野サンプラザ再開発が止まった経緯について検証記事を連載しています。記事によりますと、大手 建設費の高騰は各地でさまざまな問題につながっています。朝日新聞の最近の記事を見ても、
建設費の高騰は各地でさまざまな問題につながっています。朝日新聞の最近の記事を見ても、